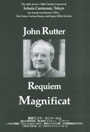 東京スコラ・カントールム創立20周年記念 第36回定期・慈善演奏会
東京スコラ・カントールム創立20周年記念 第36回定期・慈善演奏会
J. ラターの教会音楽
John Rutter ... REQUIEM & MAGNIFICAT
(1999/10/9、 指揮:黒岩英臣、 オルガン:花井哲郎、 すみだトリフォニーホール)
《プログラムノート》
1999年6月8日
東京スコラ・カントールム御中
John Rutter(自署)
拝啓
皆様の演奏会のご成功に向けて、心からのご挨拶をお送りします。そのプログラムに私の「レクィエム」と「マニフィカート」をお選びくださったことを光栄に思い、また嬉しく存じております。この催しが、いくつかのすばらしい慈善団体に益をもたらすことを、特に喜んでいます。
合唱団、指揮者と器楽奏者の方々、そして聴衆の皆様のご多幸を祈念いたします。
敬具
|
…John Rutter − 人と作品
ジョン・ラターは1945年、ロンドンで生まれました。ハイゲート・スクールで聖歌隊員としてはじめての音楽教育をうけ、後にケンブリッジのクレア・カレッジで音楽を学びながら、そこで初めての作品集を処女出版したほか、自らが指揮した演奏の初録音も行いました。
作曲家としての彼の初期作品には大・小の合唱曲、オーケストラ曲や室内樂曲、ピアノ協奏曲、子供のためのオペラ2曲、テレビ用の音楽などがあり、また、フィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルやキングス・シンガーズなどの作・編曲を手がけるスペシャリストでもありました。最近の比較的大きな作品としては「レクィエム」(1985)、「マニフィカト」(1990)、「サームフェスト(詩編集)」(1993)などがあり、英国や北米で何回も演奏され、他国でも数多く演奏されるようになりました。彼はまたデーヴィッド・ウイルコックス卿と共に、4巻の「聖歌隊のためのキャロル集」シリーズを編纂し、その後も「オックスフォード古典合唱曲シリーズ」の最初の2巻、「オペラ合唱曲集」(1995)と「ヨーロッパの聖音楽」(1996)などを編集しています。
1975年から1979年の間はクレア・カレッジの音楽監督を務め、その聖歌隊を指揮して、数多くの放送や録音活動を行いました。作曲により多くの時間を割くため、その地位を退いてからは、録音を主目的としたプロの室内合唱団「ケンブリッジ・シンガーズ」を組織し、現在は作曲と指揮活動に専念しています。客演指揮者として、あるいは講演者として、ヨーロッパ、スカンディナヴィア、北米、オーストラリアの多くの演奏会場、大学、教会、音楽祭やコンファレンスに出向くこともしばしばです。1980年には米国プリンストンの「ウエストミンスター・クワィヤー・カレッジ」の名誉顧問、1988年には「教会音楽家ギルド」の顧問に迎えられました。カンタベリー大主教が、彼の教会音楽に対する貢献を顕彰し、ランベス博士の称号を授与したのは1996年のことでした。
…「レクィエム」について
この作品はブラームスやフォーレが確立した流れを汲むもので、厳格な意味でのカトリックの「死者のためのミサ(Requiem Mass)」形式にしたがったものではありません。その代わりに、個人的な選択で死者のためのミサ典礼文の一部を転用したり、1662年版のイギリス国教会祈祷書の一部を借用して構成しました。
全体は7曲からなり、アーチ風の構造で生と死をテーマとする瞑想にいざないます。最初と最後の楽章は全ての人間に共通する祈りともいうべきもの、第2、第6楽章は詩編、第3、第5楽章はキリストへの個人的な祈り、そして中央の高みに配した第4楽章のサンクトゥスは、神の栄光を現します。
このレクィエムは1985年10月13日、テキサス州ダラスのラヴァーズレーン・ユナイテッド・メソジスト教会(音楽監督:アレン・ポート)で、サンクチュアリ聖歌隊および管弦楽団によって初演されました。
(著者:ジョン・ラター、翻訳:東京スコラカントールム、転載許可:Oxford University Press - 1999/5/26)
…「マニフィカート」について
マニフィカートとして知られる「ルカによる福音書(第1章46-55節)」の一節は、福音書記者ルカによるマリアの讃歌です。天使から、キリストを懐胎したことを告げ知らされたおとめマリアの、詩的な讃美のほとばしりであり、神により頼む者の喜びと信念です。これはカトリックの晩課や英国国教会の晩祷の一部として歌われ続けてきた聖歌ですが、そういう意義づけを超えて、最も親しまれ、常に愛誦されてきた聖句の一つです。この聖句を歌詞とする音楽はたくさんありますが、J. S. バッハ以降の作品で、彼が試みたような形で歌詞を拡張して作曲した作品は驚くほど僅かしかありません。
[訳注: バッハのマニフィカート初稿譜(BWV. 243a/変ホ長調)は1723年のクリスマス用に作曲され、ラテン語聖書の原詞に加え、4曲のラテン語とドイツ語によるコラールを織り込んで構成されています。]
私は長い間、この拡大版マニフィカートを作曲したいと思っていました。しかし、どのように着手したらいいのか確信が持てませんでした。おとめマリアを主題とする原詞との関連づけを定めることが着手のポイントとなります。スペイン、メキシコあるいはプエルトリコといった国々で、人々はこの「おとめ」の祝日に嬉々として街頭に繰り出し、歌い、踊り、行進をして祝います。
このような戸外での祝祭風景が、私の心と作品の隅にいくばくかの影響をもたらしているかもしれません。とはいえ、そのことに心を奪われていたわけではありません。それよりむしろ、バッハのように、礼拝用テキストにふさわしい追加歌詞の選定に関心を強めていたのです。その結果が「マリア」との連想を強める二つの歌詞、一つは第2楽章の美しい英詩の古典「Of a Rose(バラに寄せて)」と、他の一つは第7楽章への「Sancta Maria(聖マリアのとりなしを求める祈り)」というラテン語の祈祷文の採用です。そして第3楽章にも工夫をこらしました。「ルカによる福音書」の原典にはない、ミサ通常文の「Sanctus(聖なるかな)」を挿入したのです。そしてこの典礼文には Missa cum jubilo(喜びのミサ曲)という、グレゴリオ聖歌の旋律をつけました。そうすることによって、直前の聖句「et sanctum nomen ejus(そのみ名は尊い)」という言葉を敷衍することができると思えたからです。
[訳注: このグレゴリオ聖歌は別名 Missa de Beata Maria Virginis(祝されたおとめマリアの祝日のためのミサ曲)と呼ばれる名曲で、1月元旦の「聖母マリアの記念日」、3月の「お告げの祝日」、5月の「聖母訪問祭」、8月の「聖母被昇天祭」、9月の「聖母生誕祭」、11月の「聖母マリア奉献の記念日」、12月の「聖母の無垢受胎の祝日」などで人々に親しまれてきました。ラターは、その一部を転用しています。]
このマニフィカートの作曲に熱中したのは1990年初頭のことで、数週間を費やして完成させました。初演はその年の5月、ニューヨークのカーネギー・ホールで行なわれました。
(著者:ジョン・ラター、翻訳:東京スコラカントールム、転載許可:Oxford University Press - 1999/5/26)
常任指揮者・黒岩英臣先生インタビュー
『スコラの演奏会は灯火、灯台のように』
東京スコラ・カントールム(以下、スコラ)は5人のキリスト者の呼びかけから始まった。第1回の演奏会は1979年4月27日。修道院生活を経て音楽の世界に戻って間もない黒岩英臣先生とともに歩み始めて今年で20年。この記念演奏会を前に、スコラのユニークなところ、ラターの音楽について印象を語っていただいた。
(構成:服部浩巳、聞き手:記念誌編集委員会)
…創立当初のスコラ、そして今のスコラ
----- まず、最初の演奏会からずっと指導されてこられたのですが、この20年を振り返って、スコラの印象は先生の目にどのように映っていたのでしょうか?
いろんな団体がある中で他と違って、小笹さんたち(注1)がつくった理想があって、キリスト教の音楽を主体にやるというポリシーをもっていることに、まず親近感を覚えました。そういうものをずっとやっていこう、ということに対して情熱的なものを感じていましたからね。僕は嬉しく、ある賛嘆の念を抱いていたんです。
例えば、今年はこの国の音楽をやると、来年はどっか別の国のをとやってましたね。それも面白くて印象的だったんです。要するに、いま自分たちがやりたいと思って、それを先の方までヴィジョンをもってこういう形で実現してやり遂げようとしてるっていうことに関してね。これまでこういう世界って僕は知らなかったから、素晴らしい世界だなと思ったことは事実です。
僕自身は大学3年のときに洗礼を受けたんです。学校を卒業するまでは歌曲の伴奏とかそういうのを別にすれば、歌を指揮するチャンスはあまりなかったんです。もっぱら器楽ばかりだから。それに、合唱というものは、その後の修道院時代に聖歌隊で初めて親しんだわけで。スコラのおかげで今までやったことのない曲を振らせてもらえたので良かったです。
反面、音楽としての実力がちょっと伴っていない面も感じました。音楽的にも、技術的にも、感覚的にも、皆が大人の合唱団としてもっている立派なものを、普通のオーケストラだとか合唱団とか、すごくいいレベルのものと何とか近づけられないかなという気持ちを、僕としては抱いてました。
というのも、子供のころからずっと専門的にやってきたものだから、そうじゃないっていうことにあまり慣れてないっていう面があったので、幾分欲求不満もありました。だけど、それと目指してるものっていうのは、反発するんではなく、結び合って段々向上していくんだなっていう姿勢がありましたから。その時、僕がびっくりするくらいうまいっていうもんじゃないとしても、そういうものを皆努力して、これから先も歌っていこうと思ってるんだなという意識に僕自身ずいぶん啓発されました。
また、聴いてくれる人に対して、そういう世界を自分たちが心から愛しているんだっていうことをいつも訴えかけながら演奏会に臨むっていう姿勢にも好感を持っていたんです。プログラムを読むと、ちょっと普通の合唱団と違うでしょう。プログラムやコンティヌオ(注2)をずっと読んでいて、あれを一冊にまとめて印刷したらきっといい読み物になるだろうなって常々思ってたくらいだからね。
(注1)小笹和彦、岩崎次郎、斎藤成八郎、杉原泰雄、竹下弓子の5人が発起人
(注2)スコラの会報のこと
----- 最初のころは先生も練習から指導してくださっていましたし、指揮される時は通常の燕尾服ではなく白い祭服のようなガウンを着てくださってました。最近は先生に振っていただくのも数年に一回という風になっています。
黒岩先生のほうから、スコラがちょっと遠くなった、というようなことはありますか? たまに指導に来られて、顔ぶれだけでなく、雰囲気とか情熱とか昔とずいぶん変わったんでしょうか、あるいは当初から脈々と流れているものがあると感じていらっしゃるんでしょうか。
変わったなって思うことは、人が少し変わったくらいで、創立以来からのメンバーと新しい人との断絶感は全然ないですね。それよりも、「おっ、うまくなったな」って感じるわけだから、確かに脈々と流れてると感じています。前から女声はある一定のレベルを持っていたけど、男声なんか声がポキポキしていた。だけど、今は声の質というのか、声を出した時にこっちまで伸びてくる音が非常に艶やかに伸びるようになってる。前よりも自由自在で艶やかになったって思う。
それに、声だからきれいに出さなければいけないけれども、生きてる人間としてはきれいごとでは済まない部分って必ずありますよね。本気なんだ!っていうものっていうのは聴いてもらうにあたっては、絶対必要です。音楽として、魂がこもっていないと。綺麗だったから、それでどうなの?ということになってしまうから。
僕はやっぱり練習にあたって呼びかけてるのは、そういうことです。つまり、僕は皆が本当にやろう、と思って集まってるということは、信じられるんだ。信じられて、皆の顔を見てると、それが分かるんです。だけど、そうではなくて、音楽に対して沈滞した感じになってるんだったら、もう全く面白くないけど…。そういうことは全然なくて、すごくいいムードですよ。気持ちの向きが一致してるっていうことでね。
そして、ここ10年ぐらい前から僕は思い始めたのかもしれないし、この前(注3)もそうだと思ったけれど、20年前と比べてみれば、やっぱり今回もうまくなっていますよね。皆それだけ場数踏んできたわけだからね。
また、1曲の音楽をどんどん深く掘り下げて、皆が納得をして歌って一つの演奏会を作り上げていく、というスタイルがぜんぜん変わっていないってところもいいと思う。スコラが演奏会をするっていうことは、もちろん演奏するんだけれども、演奏ってものは何か一つの灯火のようであったり、灯台のようであって、世の中にはこういうことが現にあるんだという宣言みたいなものだと思うんだ。
そうすると聴いてくれる人は、合唱団が本気で取り組んでいることに対して、「この人たちは本当にこう信じていて、こういうものを愛して、こういう生き方をしているんだな」と感じてくれるだろうと思う。
だから人数が増えても、顔ぶれが変わっていっても、スコラの味の素になってるもの、これが自分たちの合唱団の焦点なんだってものを皆で注意深くできるだけ意識し、そういうのが好きだ、愛することができるっていう気持ちがあればこれからも大丈夫だと思う。そういうものがないとやっぱり薄まってしまう。それぞれの合唱団は、ある焦点を結ばなくちゃいけないと思うけれど、スコラはもう創立当初からそういう色のある団体だったんですよね。
(注3)'95年の32回演奏会。シューマンを取り上げた。
----- 幸いなことに、スコラの演奏会はこの20年、いつもお客様の善意や精神的なつながりを通じて、いいものができてきたと思います。今回初めてスコラを聴く人たちも多いと思うんですが、先生からのメッセージというものは?
スコラはいつもチャリティでやっているでしょう。これは一つの大きなメッセージなんだと思うんですね。たまたまいつかそういうことをやったというのと違って、ずっとやっている。それもこの団の特徴の一つになっている。
それはこの団の精神の表れであって、音楽が好きっていうこととが結びついている。たまたま余ったお金を寄付する、というのとは全く違って一つの目的とする部分なわけだから。
僕が立派だと思うのは、例えば自分がそういうことを個人的にやろうとして長い間やり続けられるかっていうと、なかなかそうはできないんじゃないかと思うから。そういうことって本当にやるに値するものなんだなっていうことを実感してもらえる演奏をしたいな、と思うわけです。だから我々としては精一杯やるしかなくて、そういうものが伝わればいいですね。
聴いてくれる人は、自分たちの生活の一部を切り取って、それまで生きてきたことのある頂点の時間に会場へ来るんですよね。それぞれの生活の中からそこに来合わせるわけだから、何かそっちのほうから我々に出てくるものっていうのも在るだろうしね。聴くっていうことは、きっとそういうことだろうから。
演奏する側がまず働きかけなくてはいけないことはもちろんだけれど、聴く側も知らず知らずのうちに自分が培ってきたものとか、関わっているものだとか、要するに生まれてこのかた、一切がそこに反映されてるよね。絶対にね。
人間は一人一人生きているなかで、この演奏会のように、一つのものを作るために心をかけるという作業を繰り返してきて人生を形づくるわけでしょう。そういう一人一人が生きているってこととまともに渡り合って、それと言葉を交わすことができるほどの演奏でありたいと思う。それができたらすごいことだろうなと思います。
…ラターの音楽について −−− 縦と横の十字架
----- 最後に、今回演奏会のラターの音楽について、お感じになっていることをお聞きします。 「レクイエム」「マニフィカート」はともに大きな曲です。今までいろんな時代の曲を演奏しましたが、今回はまだ存命の作曲家を取り上げています。ジョン・ラターはグレゴリアン、ルネッサンスから現代のものまでCDをたくさん出しており、作曲家というよりは演奏家、指揮者として有名です。しかし日本ではあまり知られていないようですが、英語圏では教会音楽家として、また作曲家として非常にポピュラーな存在です。また、最近日本の合唱界では若い人たちの関心と人気が高まっているようです。
ラターってどういう人か知らなかったけれども、今回思ったのは、曲も大きいし、大作だなって思ったんです。例えば、時間的なこと。違う現代の作曲家っていうところから、グレゴリアンチャントまでずっと使ってるでしょう? うんと古いものから今の様式までのいろんな橋渡しをやってるな、ってのが一つの特徴ですね。
また彼はヨーロッパ人、イギリス人でしょう。だけど、「レクイエム」では黒人霊歌っぽいものを使ったり、「マニフィカート」は太鼓の入るようなのもあるし、現代っぽいっていう以上に、中近東か、アフリカのどこかか何かそういうようなものも感じるんですよね。
昔のヨーロッパ人の画家たちは、マリア様の賛歌を非常に美しく描いたでしょう? ちょっと言い過ぎかもしれないけれども、それをなにかしら「野蛮チック」というべきか、バイタリティー溢れるものにしてみたりね。ヨーロッパから中近東、アフリカ、それからアメリカ大陸まで、地域的な広がりを目指して、縦と横の十字架みたいな広がりっていうものを感じているのです。それが彼のライフワークなのか、あるいはこれを書くにあたっての意図なのか、それでいて非常に美しい旋律をあとからあとから出してきてちょっと辟易するようなところもある感じも…。
ところどころミュージカルみたいなところもあるけれど、それは多分昔の聖堂の中でやる教会音楽とは、ちょっと時代の様式だとか、いわゆる教会音楽とかクラシックだとかいうものとちょっと違う横の糸に、そういう世界も取り入れたりしているのかなとも思うんですよね。そこには彼の意図があるんだと思うし、あの人の体質に合っているのかも知れないと思う。意図だけで書くと、やっぱり頭の先で書いたものになって干からびてしまうと思うのね。それは何かしらあの人の本音から出てきてると思う。それが彼の現代性っていう、自然に現れる何かなのかもしれないですね。
先頭へ戻る
Activities へ戻る
トップページへ戻る
|
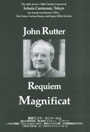 東京スコラ・カントールム創立20周年記念 第36回定期・慈善演奏会
東京スコラ・カントールム創立20周年記念 第36回定期・慈善演奏会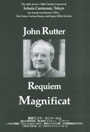 東京スコラ・カントールム創立20周年記念 第36回定期・慈善演奏会
東京スコラ・カントールム創立20周年記念 第36回定期・慈善演奏会