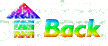2009年06月30日(火曜日)
(09:53)こんな事ってあるのですかね。コンピューターに詳しい方にお聞きしたいのです。
実は小生が家で一番使っている大きめのラップトップの電池の件です。リチウムイオン電池で、持ち運ぶことは全くないのにずっと電池をはめて使っていた。停電(日本ではないのですが)の時に直ちにコンピューターがダウンしなくて良いだろう、と思って。
しかし買ってからこの方ずっと充電状態にも関わらず、最近電池アラームが点滅したりして「おかしいな」と思っていたのです。ついさっき、「電池に問題あるからコンピューターを休止状態にする」旨のメッセージが出た。「おかしいな」という感じ。だってずっと充電中の状態にあるわけで、電池の電気がなくなるはずがない。
そこで、「電池なんていらない。外そう」と思ったのです。外したら「休止状態」が解除されて、直ちにコンピューターは復活、しかも「このマシンは古いから仕方がないか」と思っていた全体の遅さが解消して、実にサクサクと動くようになった。こちとら狐に鼻をつままれたようなものです。
持ち歩いているラップトップは、しばしば電源のないところで使っている。だからどうしても電池は必要です。だから電池を填めて使っているのですが、以前こんなこともあった。それは買ってからずっと充電状態で使っていたまだ新しいコンピューターのリチウムイオン電池が死んでしまった。つまり蓄電しなくなったのです。しょうがないから新しい電池を買った。これがまた高いのです。
ということは、いつも電源を入れた状態で使っているラップトップの電池は、実は「電池は外しておいた方が良いのか」、という問題意識。どうでしょう。日本は停電なんて少ないのだから、机の上に置いたままのラップトップからは電池を外していた方が良いような気がする。
どなたかアイデアがあったら教えて下さい。それに、不具合の電池を外したらなぜコンピューターがサクサク動くのか。もう驚くほどなんです。

2009年06月29日(月曜日)
(23:53)村上春樹の小説と同じような発想を持った小説を読みました。「会社が消えた日」です。何が似ているか、似ていると感じたかというと、一種の「ダブル・リアリティ」という発想。
「1Q84」では「月が二つに見える」ということがその象徴として書かれているが、この小説では「昨日まで務めていた役員一歩手前の男の在籍実績が全く消されて社会に放り出される」「それによって全く今まで経験したことのないもう一つの世界に落とされ、経験する」という状況設定となっている。まああと戻るのですが。
村上春樹の小説はテロ集団あり、宗教団体あり、異常な能力を持つ超能力者ありの世界だが、「会社が消えた日」で出てくるのは現実に両サイドにいる人間です。どちらが上と言うことではなく。その両サイドで生きているようでも、一瞬にしてそれが入れ替わる可能性、危険性があると説く。
小説としての完成度は、明らかに「1Q84」の方が高い。しかし「会社が消えた日」の方は正社員でも職を失い、所得を失う危険性が高まっている今の経済危機の現実に似た設定で話が進む分だけ、リアリティがある。
この小説を読むと、「そうか一回職を失うと保証人を探すのがそれほど難しいのか」とか、「なるほど最後はパチンコ屋か」とか、「離職票というのが必要なんだ」とかに気付かされる。著者の水木さんは相当取材したのでしょうね。
主人公が最後に選ぶ道の話はしない方がよいと思うから書かないが、この小説を「自分の身」の問題として考える人は、「1Q84」の読者より多いかも知れない。もしこの両方の小説を同じ数の読者が読んだとしたなら。
同じ時期に同じような発想を持った小説が出来た、ということが興味深い。それはもしかしたら時代状況の中に、「もう一つの現実、もう一つの世界」といった発想、恐れ、願望が出てきていて、それが作家さん達の発想の中に同時的に生じてきた可能性がある。この同時性に私は興味を持ちました。
それにしても、昨日もそうですがまだ「1Q84」を読んでいない人が多いのには、私としては驚かされる。昨日も総勢4人で食事をしましたが、私以外の人は読んでいなかった。しょうがないから「会社が消えた日」との対比を両方の話をしながら私が説明しないといけない。
「村上春樹の新しい小生は爆発的に売れている」とよく言われる。でもどうなんでしょう。私の身近の分析によれば、「買って置いてある」という人が多いのでは。先週の木曜日に食事をしたインテリジェンスの高い女性の方々もそういう方だった。
まあ読む、読まないは勝手です。しかしこの二つの小説をほぼ同時に読んだ私としては、「この二冊の小説を書いた二人の作家の発想がここまで似たこと」に興味がある。

2009年06月28日(日曜日)
(23:53)ははは、同乗者が「あいつ、何かもっているな.....」と。ゴルフの石川選手の事です。
途中から音声でテレビを聞いたので12番の「4」でOBを打ったことは知っていましたが、2連続OBだったとは、夜のニュース番組で知りました。「4」で「9」ですか。素人でもちょっと真っ青になるスコア。貯金喪失。しかしそこからの復活。
「あいつ、何か...」というのは、むろん16番の第三打でのチップイン。素人仲間のチップインのパーでもバーディでもない、イーグルですからね。あの強さでは、ピンの本当の芯を喰ったときのみ下に落ちる。それが出来たと言うこと。これで3勝ですか。楽しみな選手ですね。
マイクロソフトの芯、おっと「新」OS「7」については、大勢の方からメールを頂きました。先行予約なのだが、今は「売り切れ」である旨。大勢の方に感謝。しかし在庫がたまったらまた再開するかも、とも。
既にRC版(製品候補版)を使っている方からは、「うちのスペック古めのデスクトップに入れてみましたが、非常に快適に動きました。うちでは未だにXPでVistaは入れていないのですが、おそらくVistaより快適だと思います。ただ、ノートパソコンの場合は設計が特殊なので、ドライバーが一部対応していないなどの不都合が生じる可能性があります。7が発売されても、ノートパソコンにはすぐにはインストールせず、メーカーのホームページで対応状況を見つつ、1か月ぐらいは様子を見るのが賢明かと思います」とのメールも頂きました。有り難うございました。
テレビでは、40歳にして米独立リーグに行った伊良部の特集をやっている。月給1500ドルで投手をやっているそうだ。それにしても、「これが伊良部?」と思えるほど顔が笑っている。ま、ハマの叔父さんこと工藤は46ですからね。
と思っていたら、以前ジャイアンツにいた三沢が出てきて、「去年MLBを目指してアメリカに来た」と。同じチームに居るという。知らなかったな。何時か活躍してくれれば良い、と。

2009年06月27日(土曜日)
(23:53)「7」の宣伝が多くなりましたね。10月ですか。待ち遠しい。
とにかく今一台だけあるビスタマシンがどうしても遅いのです。何としかして欲しい、というかしたい。XPに戻そうとしたらそれも出来ないスペックだという。だったらアップグレードするしかないわけで、「はよう次が」と思っていたら、やっと「そう遠くない時期に」出る。
出たらアップグレード版を買ってビスタマシンをゼロにしようと思っているのです。ま、「7」の使い勝手は知りませんが、ビスタよりはましでしょう。ところで、新聞に今マイクロソフトのアップグレード版をオーダーすると1万円以上のところが7777円でと書いてあったような気がしましたが、同社のサイトには「今ビスタを買うと3000円で7にアップグレード」というのだけが目に付くのですが、どなたかご存知 ?
「そう遠くない時期」を巡って、またまた総理は変節を繰り返しておられるようで。細田幹事長と今夜会談。多分安倍さんとの会談の直後には、「7月2日以前の解散」を決意したと思われる節があるのに、細田さんと会談したらどうやら都議選後ということらしい。受け取る側の問題もあるのかも知れないが、とにかく「腰の定まらない人」だ。
都議選後ね。相当大変でしょうね。都議選は「予想外の勝利」というのは、かなり難しいとも考えられる。そもそも自民党と公明党の候補が重なっているところもあるわけで。今、「民主党」という本を読んでいますが、今は公明党は自然と自民党とくっついていますが、随分と自民党とは対立するところにいた。そもそもは。
自民党が使えないと思ったら、公明党は公明党で動く余地はある。時間をかけながら。まあ、今の自民党の動きでも分かるとおり、この政党は相当延命のためには努力するでしょうが。
まあこの政治の混乱ぶりにしては、日本の経済はよくサバイブしているとも言える。

2009年06月26日(金曜日)
(14:53)大きなニュースが朝に飛び込んできた一日でした。「マイケル・ジャクソンが病院に担ぎ込まれた」というニュースがTBSのニュースルームに入ってきたのは午前6時50分くらいですかね。私の出番まであと10分という時間。
入ってきた瞬間は皆で「また何かやらかしたのか」といった冗談を飛ばしていた。しかし藤井君が持ってきてくれた英語の速報を見たら、「at that time he was not breathing」と確か書いてあった。つまり呼吸をしていない、ということだから、これは大変だということになった。
それからニュース集めをして、7時の頭でこれを扱ったのですが、その時はロイターとアメリカの芸能専門TMZが「死亡」を報じていただけで、最初に入院を報道したとされるロサンゼルス・タイムスを含めてアメリカの有力テレビ、紙誌の多くは「病院に担ぎ込まれた」段階だった。「死亡」が広く報じられたのは、午前7時20分を過ぎてからですかね。
ジャクソン・ファイブのころから知っていますが、最初は小さな、いかにも黒人の可愛い男の子という印象だった。森本さんによれば、小さい頃からスイッチャーがどれだけカメラを変えても、どのカメラがONになっているか瞬時に理解して、そちらに顔を向けたという。小さい頃から、メディアの世界を知り尽くしていたと言うことだ。
暫く見ないと思っていたら、あの独特の踊りとスリラーという曲で出てきて、最初は「あれがあの小さい子の成長した姿か」と思ったものです。世界的スターになった代わりに、奇妙な好奇心の対象になり、また自身も変わった性癖を見せるようになった。
みそらひばりさんの有名な言葉(永六輔さんの本で読みましたが)に、「スターが幸せであるはずがない」というのがあるのですが、それを地でいくような人生だったのかも知れない。それにしても、「50才でのこの世との別れ」は早すぎる。
アメリカではマイケル・ジャクソンに先立ってファラ・フォーセットも亡くなった。70年代の後半にアメリカにいた頃、ABCだと思ったのですが、「チャーリーズ・エンジェルズ」という番組があって、英語が完全に分かったわけではないが結構美的に良かったので見ていて、それをイギリス生まれの英語の先生(アラ還の厳しい人でした)に、「チャーリーズ・エンジェルズが好きで見ている」と言ったら、「あんな英語を覚えちゃ駄目だ」と酷くしかられたのを今でもよく覚えている。
「イギリス英語が英語だ」という立場を変えなかった人です。でもファラ・フォーセットも62になっていたのですね。そりゃそうですね、それだけ時間はたっている。この二人はアメリカの人々にとっては大きい。存在が。いずれもちょっと早い死なのが残念ですが。

2009年06月25日(木曜日)
(14:53)CNNの報道によれば、ワールドカップのアジア予選で改革派の象徴である緑のリストバンドをして戦った4人の選手が代表からの「引退」を余儀なくされたという。無期出場停止ということで、多分国内のリーグ戦にも出られないのでしょう。
国の成熟度、体制の成熟度は「反対をいかに受容するのか」という点にあると思うので、今のイランの体制はデモ鎮圧を含めてどう見ても抑圧的、専制的な体制だということが分かる。
有権者数より多くの投票が見つかったところが随分とあったらしいし、事実上は無理かも知れないが、ベースとしては「国際機関監視による選挙のやり直し」しかないように思う。もしイランがそれを出来たら、体制はおかしかったが国はそれを是正する力があったということになる。
不正があったことが明らかな選挙を放置すると言うことは、次の選挙でもそうしたことが行われる可能性を示唆し、ということは今の対欧米強硬・保守派が今後しばらくは「選挙による正統政権」の地位をイランでとり続ける危険性があるからだ。
一方でイランのアフマニネジャド政権、それを支える同国保守派に対する批判姿勢を強めているアメリカのオバマ大統領は、自国の景気に関しては従来の「明るい光が見える」論調は改め、「実は厳しい」論に立ち戻っているようだ。特に失業率の二桁台上昇を「明らかだ」と述べたという。
以前から仲間で「今のアメリカ政権の楽観論は危険だ」と話していたので、やっと見方を現実に戻したのか、という気持ち。不思議なもので、こうした転換を行うと逆に株式市場などでは「政府は正しい見方をしている」として、「正しい政策が取られるだろう」ということでプラスに評価する可能性が高い。
政権を取っているのだから楽観論を振りまきたいのは分かるし、国民の鼓舞したいのでしょうが、「根拠なき楽観論」はいつでもそうですが、事態を良い方向には向かわせない。むろん、「根拠なき悲観論」も駄目です。
今朝テレビ出演中に、東国原さんが以前の「そのまんま東」で首相になったら、それを翻訳すると「East As It Is」になるな、なんてどうでも良いことをちらと考えていました。意味はありませんが(^-^)ニコ。

2009年06月25日(木曜日)
(04:53)住宅ローン担保証券や米国債の買い入れ額を前回声明(4月時点)と全く同じで増額しなかった、期間も延長しなかったからでしょうかね。それともまだ強気になるには調整が不足していた ?
FOMC声明を受けたニューヨークの株価の動きです。引値はどうなるか分かりませんが、朝方は100ドル近く上がっていたダウ平均は一端下がった。小幅ですが。景況判断は第一パラグラフで読めるとおりです。まだら模様と言うことでしょう。
For immediate release Information received since the Federal Open Market Committee met in April suggests that the pace of economic contraction is slowing. Conditions in financial markets have generally improved in recent months. Household spending has shown further signs of stabilizing but remains constrained by ongoing job losses, lower housing wealth, and tight credit. Businesses are cutting back on fixed investment and staffing but appear to be making progress in bringing inventory stocks into better alignment with sales. Although economic activity is likely to remain weak for a time, the Committee continues to anticipate that policy actions to stabilize financial markets and institutions, fiscal and monetary stimulus, and market forces will contribute to a gradual resumption of sustainable economic growth in a context of price stability.The prices of energy and other commodities have risen of late. However, substantial resource slack is likely to dampen cost pressures, and the Committee expects that inflation will remain subdued for some time.
In these circumstances, the Federal Reserve will employ all available tools to promote economic recovery and to preserve price stability. The Committee will maintain the target range for the federal funds rate at 0 to 1/4 percent and continues to anticipate that economic conditions are likely to warrant exceptionally low levels of the federal funds rate for an extended period. As previously announced, to provide support to mortgage lending and housing markets and to improve overall conditions in private credit markets, the Federal Reserve will purchase a total of up to $1.25 trillion of agency mortgage-backed securities and up to $200 billion of agency debt by the end of the year. In addition, the Federal Reserve will buy up to $300 billion of Treasury securities by autumn. The Committee will continue to evaluate the timing and overall amounts of its purchases of securities in light of the evolving economic outlook and conditions in financial markets. The Federal Reserve is monitoring the size and composition of its balance sheet and will make adjustments to its credit and liquidity programs as warranted.
Voting for the FOMC monetary policy action were: Ben S. Bernanke, Chairman; William C. Dudley, Vice Chairman; Elizabeth A. Duke; Charles L. Evans; Donald L. Kohn; Jeffrey M. Lacker; Dennis P. Lockhart; Daniel K. Tarullo; Kevin M. Warsh; and Janet L. Yellen.

2009年06月24日(水曜日)
(23:53)たまたまですが、駅で買った新書の中に最近話題を集めた製品、そのメーカーに関する本が2冊あったので、それを平行して読みました。二冊の本とは
両方とも面白かった。よいしょ感覚もあまりなく。「ハイブリッド」はトヨタの代表的ハイブリッド車であるプリウスが生まれるまでの話。面白かったのは、20世紀が始まる頃にポルシェ博士がハイブリッドを試していて、実際にハイブリッド車が走っていたと言うこと。
まあハイブリッドは「合成物」「混血」ですから、動力源を二つ以上抱えていれば、どういう組合せであれハイブリッドですから当時からあってもおかしくない。この本にも出ていますが20世紀が始まった頃は、蒸気とか内燃機関とか電気などの動力源が並立していた。
もう一つは「プリウス」の名前の由来が分かったことかな。プリウスとは「〜に先立って」という意味なのだそうです。まあそう言われれば、「pri....」ですから、「の前」という意味なんでしょう。ラテン語だそうです。
それにしても、この本はプリウス誕生に至る数多くの人間の奮闘が描かれる。この本を読むと、1997年の発売の最終段階までプロジェクトに参加していた人々さえ「モノになる」という確信がなかったという。それでも一様は量産、量販できるだけの規模に出来て、トヨタはプリウスによってそれまでの「準一流」のイメージを著しくアップして、世界のトップメーカーになってもおかしくない企業になった。
「アップルの法則」は、そもそも起伏の多い会社としてのアップルが、今の隆盛を迎えるまでの原則、法則、あり方を論じている。なぜアップルの製品は人々を惹き付けるのか、という問題にも触れている。なかなか良い表現だと思ったのは、
何か問題を解決しようとする時、最初に思い浮かぶ解決法は非常に複雑なものだが、多くの人はそこで考えるのを止めてしまう。しかしここで考えることを続け、問題をさらによく見て、タマネギの皮をもう少し剥いていくと、しばしばよりシンプルでエレガントな解決策にたどり着くことがある。多くの人々はそこにたどり着くための時間や労力をかけていないのだ。かな。これはジョブズの言葉を引用している。まあアメリカのメーカーとしては非常にメンタリティが優れていると言うことでしょう。というより、ジョブズの才能かも知れない。そういう意味では、ジョブズなきアップルがどうなるかは関心がある。体調が悪くなっているようですから。
二冊の本を読んで思ったのは、「常に現状に満足しない心」「新しいモノに取り組む切っ掛けを与える企業トップの力」「こんなの無理だ、と思いながらそれはどうやったら可能かを考え続けた企業の構成員達」という事でしょうか。
「なぜそれが出来ないか」を考えるのは易しい。しかし「どうしたらそれが出来るのか」を考え続けることの重要性。それにしても、トヨタのプリウスに関わった人の数は多いし、トップが投げかける時に無謀な期限や要求に従業員が振り回されたり、ふて腐れている様子まで描かれていて面白い。まあ今でもトヨタの社内がそういう雰囲気だったら、この会社は大丈夫なんでしょうが。

2009年06月23日(火曜日)
(23:53)河村さんが国会議員を辞めて名古屋市長になったとき、そりゃ「480分の1でいるよりも、1分の1になったほうがいいよな」と思ったものです。県知事もそう。少なくとも知事とか市長は「1分の1」です。
自民党の古賀選挙対策委員長が宮崎に行って出馬を要請したのがまず驚きですが、それに対する東国原知事の発言がふるっている。「自民党総裁にしてくれるなら」。ははは、驚きをと通り越して、「自民党もそこまでなめられたか」と。
党内からも同じ声が出ているようですが、そりゃそうでしょう。「どうしても政権を民主党に渡すわけにはいかない」と古賀氏。そんなこと言ってないで、国民の支持を失ったと思ったら、戦うだけ戦って野に下れば良いのです。
比例に担ぎ出して「大量得票を」と狙ったのに、とんでもない条件を出されて、おたおたというのが実体。全国知事会の7項目提案というのも、地方自治に関する見直し案ですが、まあ自民党は飲めないでしょうね。
東国原さんは「722分の1」と衆参両院の議員の数を言っているようですが、今更陣笠議員はやるつもりはないでしょう。本人が本当に国政に関心があったら、細川さんのように新党立ち上げが良いのでは、と思います。
それにしても、古賀さんは今回の醜態をどう正当化するのか。

2009年06月22日(月曜日)
(23:53)都議選に対する麻生首相の応援が始まったようですが、テレビに繰り返し写される「ナマの麻生太郎を今日初めて見た人」という問いかけは、一体何を言いたいんでしょうね。私には皆目分かりません。
あれだけ異なったシチュエーションで同じ発言をしているというのは、繰り返し繰り返し、行くところ行くところであれを言っていると言うことでしょう。「必勝」と言うべきところを「惜敗」と言ったり、オバマと言うべきところをブッシュと言ったり。麻生首相は本当に言葉には忙しい人です。
「政治とは畢竟言葉である」とは有名な言葉ですが、もしそうだとすると、麻生首相はかなり政治家としての資質をそもそも欠いていると言うことになる。もっとも今の日本のその他の政治家を見ても、「言葉に信頼が置ける」と感じることが出来る人は少ないから、それは日本の政治家の政治力の低下を指していると言えないこともない。
講演会をすると最近は「政治はどうなっているのでしょうか」という質問が多い。これが困るんですよ。光明が見えない。全体的に言えることは、「国民のサイドの政権交代願望は強い」と言える。もううんざりしているんですな。多くの人が。ここ数年の政治に。
問題は例えば民主党中心の政権が成立した後です。実際にどんな政治が行われるのか。一体一つの問題について一つのスタンドを取れるのか。問題は次の次の衆議院選挙というわけです。投票するサイドの国民の悩みは深い。

2009年06月21日(日曜日)
(13:53)人口が僅か66万人に過ぎず、主な輸出品が電力(インド向け)と農産物という貧しい国なのに、GNH(国民総幸福量)が世界一というブータンをちょっと調べ始めました。今年8月末から一週間弱訪れることにしているため。
海外の国を調べるには
などから入るのが普通ですが、これだけ見ていてもこの国が極めて特徴的な国であることが分かる。一昨年行ったモンゴルも人口270万人の小国でしたが、ブータンはもっと少ない。日本の一番人口が少ない鳥取県(59万2000人)よりほんの少し多い程度。
しかしGNHなど大きな特徴があるし、人々の面相は非常に日本人に似ているという事実もある。楽しみです。過去情報は日本人の旅行記がいっぱいあるのですが、とりあえずその種のモノはあまり読まずに
Kuensel
Bhutan Broadcasting Service
などの現地ナマ情報を中心に情報集めをしようと思っています。危険情報もあるのですが、今回の旅ではその地方には行かない。まあまだ時間があるので、ゆっくりと。先日一緒に行く人達との顔合わせがあったのですが、なかなかパワフルな方々です。主催は過去に何回も一緒に海外に行ったこの団体です。
旅行社が推奨する「持ち物」がまた面白い。停電が数多くあるので、「ヘッドランプ」なんてのも入っているし、もちろん変換プラグが必要ですし、実に久しぶりにネットのない、ケイタイもなかなか通じない地帯に入ることになりそうです。
ところで、今日の「世の中進歩堂」には、世界発の立体ディスプレイが登場します。今日は午後9時半からです。お楽しみに。

2009年06月20日(土曜日)
(09:53)なにげにテレビのBS1をつけたら松坂と川上が投げあっている。ボストンとブレーブスの試合。松坂が6点も取られていて、「今年は不調だな」という感じ。まあ彼は実績がありますから、一年くらいダメでも地位は揺るがない。下に落とされる危険性はありますが。
川上は地位を確定する途上にありますから、今日のベイに一本打たれただけのピッチングはなかなか良かった。久しぶりに自信がみなぎっている印象だった。上原と川上の大リーグは「微妙だ」と思っていたので、この二人が勝つと「良く勝った」と褒めてやりたくなる。
松井はマーリンズとの試合に出ていない。DHがなければダメだな。今年の末の松井はどうなっているのか。早く守れるようにならなければ、行き場が狭まってしまう。取りたいチームはあると思いますよ。アメリカでも。しかし守れないということは走れない訳で、選手としては完全ではない。セリーグの某チームの話もあるが、DHがないのでどうなるか。
厚生労働省の職員の机から現金400万が見つかったという話は、「どうしちゃったの」ということでしょう。やましいお金ではないそうだが、しかしどう考えても「(事務机に)現ナマ400万円」は尋常ではない。入れていた職員も気になっていたでしょうに。「尋常ではない職場」ということか。
本を二冊紹介しましょう。
最初の本は私も女子大の非常勤講師をしていたことがあるので、その当時を思い出しながら。しかし私がもらっていたレポートは相当酷かったが、この本には「文章は格段にうまくなった」と書いている。その理由は、「彼女らは毎日メールで膨大な文章を書いているから」とある。
うーん、そうかな。「タブーがなくなった」というのはそうだろう。「ヤバイ」はこの本でも取り上げられているが、今に至っては非常に複層的な意味を持つ言葉です。「微妙」の次の大ヒット。
後者の本は著者から贈ってもらった。内藤君は本当によく本を書く。私からすれべちょっとまどろっこしい内容も多いが、確かに初心者には役立つと思う。投資が難しい時代。先を照らす本なら歓迎です。

2009年06月18日(木曜日)
(23:53)グリーンに関して最新事例がふんだんに書き込まれていて、頭をアップデートできる本を紹介しましょう。「グリーン・ニューディール」です。副題は、「環境投資は世界経済を救えるか」。
この本は、NHKの記者が自ら取材した範囲を一人一人が一章を担当する形で記述している、という面白い仕上がりの本になっている。自分で取材した分が多いだけに、話が具体的で、アメリカと日本で環境に関する技術、当事者の思いが今どうなっているかが非常に分かりやすい。
グリーンに関する情報は日々アップデートされている。そういう意味では、日々の新聞などの報道に関心を払うしかないのだが、この一冊の本を読むとまず最新情報が頭の中に一列に並んでくれるという意味で読む価値のある本である。
ところで、最新エッセイがアップされました。伊藤洋一の『BRICsの衝撃』です。49回ね。ほぼ2週間に一回書いていますから、2年続いていることになる。BRICsの首脳会談も始まり、その存在感はますます増大している。

2009年06月17日(水曜日)
(16:53)火曜日のこのコーナーで取り上げた「金正雲氏が極秘訪中 金総書記の特使、胡主席らと会談」という朝日の記事については、今日になって中国外務省の秦剛副報道局長が定例記者会見で、「中国側は、この件に関する状況を承知していない」と述べ、事実上否定したという。
まああの後世界中のどのメディアも後追いしませんでしたし、そもそもニュースのソースが相当怪しかったこともあって、「違うのでは」と思っていたのですが、この件に関しては17日付の中国の国際問題専門紙・環球時報(英語版)も一面トップで、北京の北朝鮮大使館員が報道について「そのようなことは聞いたことがなく、まったく根拠のない報道だ」と否定した、と伝えているという。
そもそも「世襲反対」の姿勢の中国が、金正雲に会うと言うことはある意味で「お墨付きを与える」ということですから、ちょっと考えられない。まあ今後ともいろいろ動きが出てくるのでしょうが、相当先走った報道だったように思う。
午後3時からの党首討論を見ましたが、入り口に入ったところで終わった印象。お二人の一言一言が長い。それにまだ議論がかみ合っていない印象もする。麻生さんが最後の最後に第七艦隊云々の話を持ち出したのは、あの問題に触れて民主党の政権担当能力への不安を想起してもらうということだったのでしょうが、確かにちょっと唐突でしたね。
まあ何回かやっていくうちもうちょっと具体的な話になっていくのでは。12兆1000億の話を延々としていたりして、あれは数字を実際に調べたことがないと分かりませんからね。あまり有益な45分だったとは思えなかった。
ところで、こっちの方が重要だと思うのは、メドべージェフが「歴史的な会談」と言っているBRICs首脳会談です。今年はロシアで、来年はブラジルでやるらしい。ブラジル(ルラ)、ロシア(メドべージェフ)、中国(胡錦濤)、インド(シン)の4カ国は、世界のGDPの15%、世界の金・外貨準備の40%を保有、かつ世界の人口の40%を占める。しかしこの4カ国の相互貿易の数字などはまだ非常に小さい。インドと中国など貿易が再開されたばかりです。
まあそれでも伸び盛りの4カ国がどういうことを考えているかを声明に見ておこうと思ったので、ネットを調べたらガーディアンのサイトにサマリーがあった。それを備忘の為に掲載しておきます。
最後に「国連改革」に触れていて、この4カ国のうち2カ国は国連の常任理事国、2カ国はそれ入りを目指しているという関係から、BRICsとしてインドとブラジルのaspirations(常任理事国になりたいという熱意)を支持すると明記している。その他の声明の中味は特にビックリするようなことはない。「こういうだろうな」という線。
INTERNATIONAL FINANCIAL REFORM
"We are committed to advance the reform of international financial institutions, so as to reflect changes in the world economy. The emerging and developing economies must have greater voice and representation in international financial institutions, and their heads and senior leadership should be appointed through an open, transparent and merit-based selection process. We also believe there is a strong need for a stable, predictable and more diversified international monetary system."TRADE AND THE DOHA ROUND OF TRADE TALKS
"We recognise the important role played by international trade and foreign investments in the world economic recovery ... We urge the international community to keep the multilateral trading system stable, curb trade protectionism, and push for comprehensive and balanced results of the WTO's Doha Development Agenda."ENERGY
"We stand for strengthening coordination and cooperation among states in the energy field, including amongst producers and consumers of energy and transit states, in an effort to decrease uncertainty and ensure stability and sustainability."UNITED NATIONS REFORM
"We express our strong commitment to multilateral diplomacy with the United Nations playing the central role in dealing with global challenges and threats. In this respect, we reaffirm the need for a comprehensive reform of the U.N. ... We reiterate the importance we attach to the status of India and Brazil in international affairs, and understand and support their aspirations to play a greater role in the United Nations." (Editing by Stephen Nisbet)

2009年06月16日(火曜日)
(14:53)46才にしてなんであれだけプロ野球の世界で残って活躍できていられるのだろう、とずっと不思議に思っていたので、工藤公康選手(ベイスターズ)が書いた「現役力」という本を新幹線の中で読みました。
結構面白かったな。多分語り写しなんでしょうが。彼がプロ野球界の後輩達を見る目、その基準などが「そうなんだろうな」といった感じでひしひしと伝わってくる。29才の筑波大学での出会いが彼を大きく変えているのですが、彼にはその他にも非常に多くの出会いがあって、それが今の彼を作り上げているのが分かる。
作り上げているという意味では、初めて知りましが彼のお父さんの話や、家の話は面白かったな。根性一徹の、しかしわがままなお父さんの話は特に面白かった。「家がもうちょっと余裕があったら200勝はなかったかも」とも。
しかし普通の選手が彼の年齢の10才前で引退しておかしくない46才で今も活躍していられる理由がこの本で分かる。この週末にもNHKだかが彼の特集をやっていましたが、ずっと先発をやっていたのに、ベイスターズで今年からリリーフ。何時肩を作るのかなど、投手を長くやっていても今まで経験のないことは分からない。だから聞く、と。
年齢的には一回り以上上ですから、工藤選手が名古屋電気高校のころから知っているわけです。ライオンズに入って、FAでホークスに行って、そして次にジャイアンツに行って、今はベイスターズ。そのどこでも実績を残し続けている。素晴らしい。
スポーツの話では、今朝の朝日新聞に載っていたオシム監督のインタビューは面白かった。90キロと67キロの話も面白かったし、世の中で不可能なのは「木製の暖炉だけだ」というのも笑えた。
あそれから、忘れないように書いておこう。紙ヒコーキって英語でなんて言うか。井上陽水の曲にありましたよね。紙飛行機。英語では、「origami plane」と言うそうです。知らなかった。

2009年06月16日(火曜日)
(05:53)今朝のネットサイトはなかなか”特ダネ”的なものが多くて興味深い。まだ朝刊を読んでないので分かりませんが、先にネットを見たので。アップ時間が午前3時過ぎが多いのですが、それはもしかしたらそれらは特ダネでネットに載せるのを遅らせたのかも知れない。
まずは「金正雲氏が極秘訪中 金総書記の特使、胡主席らと会談」という朝日の記事でしょう。「両国を往来する金総書記に近い北朝鮮筋と、北京の北朝鮮関係者が明らかにした」という書き方で、私が見た限りでは他の新聞には似た記事はない。
金正日の三男である正雲氏が既に金総書記の特使として中国を極秘に訪問、胡錦濤国家主席らと初めて会談、後継者に内定したことを直接伝えた、としている。中国は一貫して世襲に反対していたはずだ。正雲氏が訪中したとしたら、その際中国側がどういう態度を取ったのかに興味がある。この記事には核、ミサイル、六者協議復帰などの記述はあるが、「中国が世襲にどういう態度を取ったのか」に関しては記述がない。
対北朝鮮の経済制裁が強化されようとしているが、結局国境を接した中国がどう対応するのかが重要です。この国境が緩ければいくら他の国が制裁を強めても意味がない。国連安保理で決議に参加しながら、中国が緩衝地帯欲しさに北朝鮮を密かに援助するようなことは監視しないといけない。
北朝鮮関係では、毎日新聞のサイトに「韓国のKBS(韓国放送公社)テレビは15日、北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル)総書記(67)の後継者に内定したとされる三男正雲(ジョンウン)氏(26)の側近が、中国・マカオ滞在中の長男正男(ジョンナム)氏(38)の暗殺を計画したが、先週初めに中国当局に察知され、失敗した」という報道もある。三男かその側近が長男の暗殺を謀る。もし本当だとしたら、日本の戦国時代のよう。
やっぱりそうか、と思ったのは読売新聞のサイトにある『新作「1Q84」オウム裁判が出発点』という村上春樹発言。この記事は不思議で、「村上春樹氏(60)が今月上旬、読売新聞の取材に東京都内で応じ......」となっている。ということは、読売新聞はこの記事を書くかなり前からそれを知っていたが記事にはしなかった。今になってした、ということになる。なぜ遅らせたのか。今はもう6月中旬です。
文章もちょっとおかしい。例えば「」の締めがないものも。『、「オウム裁判の傍聴に10年以上通い、死刑囚になった元信者の心境を想像し続けた。』と開けはあるが締めがない。
まあ細かいことは別にして、1Q84はオウムも念頭に置いているのだろうということは読んでいれば分かります。例えば「優秀な若者が次々にその団体に入った」的な表記があったと思うし、登場する団体の気持ち悪さはオウムそのものだ。読後感が悪い。その意味もあるのだろう、この小説はある意味で、読後感が悪い。

2009年06月14日(日曜日)
(15:53)今週の「世の中進歩堂」は、医療ロボットです。
番組のHPが「超高齢社会に突入した現代の日本。老人福祉に対する人手不足は日を追うごとに問題視されている。その問題を打破すべく、早稲田大学の藤江研究室では高齢者や障害者の自立を支援する“医療福祉ロボット”を開発している。まるでウォーキングマシーンのような歩行支援ロボットから、ナビゲーションシステムを搭載した杖まで、工夫を凝らした画期的なロボットを次々に紹介する」としているように、今後の日本にとって非常に重要な「介護の現場を助けるロボット」。
よく、老人は子供と同じ、とか老人は子供に帰る、と言いますよね。しかし介護をしたことがある人間として言えば、「老人と子供は決定的に違う」「それは重さである」というもの。お年寄りは大人ですから、実に重いのです。
むろん介護ロボットは色々な仕事をします。しかし介護者を助けるという意味では、この老人の重さをどう扱うかが重要でしょう。この分野の進歩を実感していただければ幸甚です。

2009年06月13日(土曜日)
(19:53)午後7時のNHKニュースを見て、やっと「こういう事だったのか」と会得がいきました。何かというと、地下鉄シリーズのメッツ対ヤンキースの試合。
この試合はずっと朝から見ていたのです。松井が一度は逆転のスリーラン(誕生日弾)を打つなどまずまず活躍。しかし7−7の同点から出てきたリベラがあっという間に点を取られて、メッツ8対ヤンキース7となった。そして9回の裏のヤンキースの攻撃も1、2塁ながらツーアウト。
そこで打順が回ってきたのがアレックス・ロドリゲス。しかし本人も打った瞬間にがっかりするフライ。そこで出掛けなければならないこともあって、私はテレビをぶちっと切ったのです。そして出掛けた。
しかし松井の会のメンバーである目原くんからしばらくして、「一応サヨナラですよね」と。こっちはびっくり。9回裏ツーアウトから打者が平凡なフライを打ち上げたら、「試合が終わった」と考えるのが自然でしょう。しかしケイタイの試合結果を見ても、ヤンキースが勝っている。
その段階から、「あのフライを誰かが落としたのだろう」と想像は出来ましたが、どう落としたかは分からなかった。それをNHKのテレビが映してくれたのです。KロッドもAロッドが打ち上げた瞬間に喜びの歓喜の声を上げているのに、メッツの二塁手は多分グラブの上に引っかけたのでしょう。落とした。
ツーアウトだからランナー二人は走っている。一挙に2点入ってヤンキースは逆転。想像を絶することが起きるものですね。野球の試合とは。
同じスポーツでは、「プレミアム8」の「アリ対フレージャー」が非常に面白かった。1975年の対戦。うっすらと覚えています。しかしどっちが勝ったのかは忘れていた。ああいうことだったのか、と。
それにしても、この「プレミアム8」というシリーズは面白い。「米喰う人々」は上下を見ましたが、非常に面白かった。なかなか良い番組だと思う。

2009年06月12日(金曜日)
(09:53)新型インフルエンザがフェーズ6(世界的大流行、パンデミック)に引き上げられたこと、しかし新設された「健康被害の深刻度」(3段階)では、真ん中の「中度」(モデレート)に設定されたことは既に今朝の新聞に載っている通りです。しかし問題は、この最高度のフェーズがいつまで続くのか、どういう形で新型インフルエンザが終息するのか、です。
この点に関して、今朝の東京新聞のネットサイトはWHOの進藤奈邦子医務官の興味深い発言を伝えている。彼女は「今後3年間はパンデミック状態が続く」と述べ、警戒水準(フェーズ)が最高位の「6」に長期間据え置かれるとの見通しを明らかにしたという。
同医務官は「今後は(冬を迎える)南半球の動向を注視する必要がある」と指摘。事実オーストラリアではこの10日間ほどで、感染者が激増した。筆者は他の開発途上の地域などでは、実は捕捉が進んでいないことで実体が分かっていないだけなのではないか、と思っているのです。いずれにせよ、今南半球で起きていることは、秋からの北半球で起こりうる事態である。
進藤医務官は、「感染者は米国など北半球でも増加し、新型ウイルスが衰える気配はない」と安易な終息ムードを戒めているが、では今後はどういう形で収束・終息するのか。ここが面白いのですが、記事は「フェーズ6の期間中、世界の多くの人が新型ウイルスに感染して免疫を獲得したり、ワクチンで感染被害を抑え込むことなどにより、患者数は徐々に減少」とかかれている。つまり広がって、そしてワクチンの効果などもあって多くの人に免疫が出来て初めて収まるというのである。
広がらなければ、そして多くの人に免疫が出来て初めて収まる、というところが面白い。進藤医務官は、「新型ウイルスはその後、通常の季節性インフルエンザウイルスと同じ扱いになる」と述べる。
つまり長期戦になるということです。願わくば、新型インフルエンザが遺伝子変化を起こして毒性を強めないこと、タミフルを使いすぎて耐性が出来ないこと、世界が恐れた鳥インフルエンザがパンデミックにならないこと、捕捉ができない途上国で大きな被害が出ないこと、などなどでしょうか。

2009年06月11日(木曜日)
(18:53)久しぶりに都内でロケを。2時間くらいですかね。六本木などで。局はテレビ東京ですが、何時放送されるのかまだ聞いていないので、また決まりましたら。前回はテレビ朝日の「大人のソナタ」だったかな。どこでも寝られる、という話でした。
ところで、今面白い本を読んでいます。『日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか』というのです。日本人の正当な別れの挨拶は、つい最近まで「さようなら」だったように思う。
しかしずっと「違うな」と思っていたことがあって、それは英語も中国語も「また会いましょう」が別れの挨拶の基本なのです。「see you」がアメリカでは主流だと思うし、中国語では「再見」が基本です。日本語では「また」「じゃまた」があるが、これはどう考えても別れの挨拶の正式な表現ではない。
どうして日本語は違うんだろう、「さようなら」とはどういう言葉だろうと思っていたのです。なぜ日本人は「また会う」ということを言わないのかな、ということです。
そういう基本的な疑問があったものだから、今週火曜日に大阪に向かうときに東京駅の書店でこの本を見付けて直ぐに買ってしまった。読み始めていますが、ちょっと脱線気味の本ではあるが、私の疑問には答えてくれている。
それによると、元々この言葉は「さようならば」という接続詞からの「別れ言葉」への変化だというのです。同じように「さらば」は「然らば」からの分かれ。接続詞としての「然らば」は、「ということであるならば」という区切りの、「そうであるならば、私はこうする」という言葉です。「然らば、もうこの世には未練はない」のような。
「see you」や「再見」には、過去と今からさらには未来という区切りはない。しかし元々「さようであるならば」「さようならば」をベースとする「さようなら」にはそういう意味合いがある、といったことが面白い。
この本はその辺から、日本人の死生観にまで話を広げている。まだ読んでいる最中なのであとがちょっと楽しみ。しかしとりあえず「さようなら」がどこから来たのか分かったのは良かった。
うーん、いまつらつらと思い返したら、「さようなら」と正式に言って人と別れたことは最近あまりないな。「じゃ、また」が一番多い。良いことか悪いことか分かりませんが。

2009年06月09日(火曜日)
(18:53)今日覚えた一番面白い単語は、「衛生仮説」でしょうか。火曜日なので関西にいたのですが、関西テレビさんに賞を取った番組があるというので、それは面白そうだと思ってDVDをもらって見たら確かに興味深かった。その中に出てくる言葉です。
番組の名前は、リンク先のように「4000万人の国民病”アレルギー”のヒミツ」というのです。そういえば確か私も花粉症です。ではなぜ昔に比べて日本人ばかりでなく世界中でアレルギーの患者が増えているのか。それに対する回答の一つが「衛生仮説」だという。
それにしてもアレルギーで急性で亡くなる方もいるとは。深刻です。それに対処する用具も出来ているようです。「衛生仮説」についてはネットを調べたらこんなPDFもあるのですが(あれ番組に出ていた先生では)、要するに幼児期の衛生状態があまりにも良くなりすぎて、幼児期に形成されるべきアレルギーに抵抗する力が現代人は弱くなっているという説。
この仮説が生まれる切っ掛けは、田舎、特に農家に育った子供の方が、小綺麗な都会で育った子供よりはアレルギーになりにくいという調査結果かららしい。ドイツの例が出ていた。ウイルスやらいろいろな菌がいっぱいいる。そういうところで育った子供の方が、結果的にアレルギーになりにくい、と。T1だとかT2とか出てきましたが、覚えられませんでした。
まあでもこれは我々の日常的な常識でもある。あまりにも大事に育てられた子供は弱い、とよく言われる。新型インフルエンザでもそういう事が言えた。1957年以前に生まれた人はなんらかの免疫を持っていて、新型にかからないといった。
しかし番組の中で先生が、「じゃ、昔の不衛生な状態に戻せば良いかというと幼児死亡率が高くなる。結局なんらかの形で対処しながらアレルギーとも付き合っていく必要がある」と述べていたのが、「なるほど」と思いました。
無菌も良くない、かといって菌が多すぎるのも困る。なかなか難しいと言うことです。それにしても、この番組の山本、村西、豊田各アナウンサーばかりでなく、PからD、それにADまで総出で番組に取り組んでいたのは笑えたな。ははは。
うーん、放送は終わってしまったんでしょうが、ちょっと自分や家族がアレルギーで悩んでいる人は見た方が良いような。

2009年06月08日(月曜日)
(08:53)実に久しぶりに大きなホールでジャズ、特にピアノをフィーチャーしたセッションを聞きました。「100 Gold Fingers」というのです。なぜ「100本の黄金の指」なのか。ピアノ演奏者が10人だからです。
ジャズはいつも骨董通りの「Body and Soul」などクラブで聞くことが多い。入っても100人といった規模の。その方がライブの生々しさが伝わるからです。ニューヨークだったらビレッジのあの有名なクラブとか。大ホールでのジャズなど音が散って嫌だと思っていたのです。
しかし今回は逆に小さなクラブでは出来ない試みがあって、それはそれで面白かった。演奏したのはジュニア・マンス、シダー・ウォルトン、ジョアン・ドナート、ドン・フリードマン、ケニー・バロン、テッド・ローゼンタール、サイラス・チェスナット、ベニー・グリーン、山中 千尋、ジェラルド・クレイトンで、正直言って名前を聞いただけで直ぐに「あの人か」と言える人はいなかった。しかしもう10年以上も毎年やっているイベントらしい。日本各地も回っている。
面白いと思ったのは、ステージにはグランド・ピアノが2台置かれていて、セッションによっては3人のピアニストが登場して、二人がかけあいの演奏をし、もう一人がリザーブでそれが適宜入れ替わっていく時間があったこと。これは面白いと思いました。小さなクラブではグランド・ピアノを二台入れるスペースはない。
ピアノだけの時も、ベースとドラムが入るケースもあり、山中さんが小さい身体(アメリカの男性陣に比べれば)を一杯に使って演奏した前半の半ばから会場は盛り上がって、最後は日本としては珍しい「一部スタンディング・オベーション」でのエンド。ははは、あれはあれで楽しかった。
個性溢れる方々でした。「歩けるのかい」と思える巨漢から、ちょこっとニューヨークから帽子をかぶってやってきたという感じのおじいちゃんまで。依然としてクラブでのジャズの方が良いとは思うのですが、今振り返ると良かったなと。
もっともこのセッションに間に合うように家を出たので、NHKが中継していたゴルフを最後まで見られなかったのは残念でした。「ゼロゼロ・ボーイ」を応援していたのです。昨年の獲得賞金ゼロ、優勝経験ゼロ。もうすぐ41歳の五十嵐選手。
最終組が17番のティーショットを打つところまで見た。その時点で前の組の五十嵐選手は1打差で負けていた。首位を走っていたのはIJジャンという韓国の選手。その選手が17番、18番の両方でボギーを打ったそうな。彼は前の日もそうでした。夜のニュースではどうしてそうなったのかどこもやってくれない。経緯が分からないわけです。分かったのはスリーオンして最初のパットを外したのだろう、ということ。
五十嵐選手は今まで獲得した賞金が2500万ちょっと。今回の優勝で賞金3000万円と5年間のシード。ははは、凄い凄い。うーんでもな、過去の大きな大会で突然花が咲いたものの、その後活躍しなくなった選手っていうのは何人もいるんですよ。
例えばジュン・クラシックで尾崎と優勝を争って最後の18番でバンカーからパットを使った郷田選手(といったかな)。その後ダメですね。今回も名前を探したがなかった。私はバンカーでパターを使うのを「ゴーダショット」と呼んでいる。
今回の記録を見ていて「へえ」と思ったのは、かつて活躍した加瀬秀樹という選手が、+19くらいで最下位に沈んでいたこと。ちらっと見ただけですが。結構強い選手でしたが。まあこの大会に出ていると言うことは、まだ全体的には頑張っているのでしょう。
ジャンボはどうなっているのでしょうか。倉本さんは。石川君はNHKに持ち上げられすぎて居心地が悪そうでした。

2009年06月07日(日曜日)
(13:53)ははは、「世界を驚かす覚悟がある」とはなかなか良いスローガンではないですか。本当に「風」を起こして欲しいと思います。日韓共催の時の韓国のように。または野球のWBCのように。
ずっと見ていましたが、後半は殆ど攻められっぱなしと言う感じ。もっとも審判は明らかにホーム寄り。岡田さんが怒るのは無理ない。それでも勝ったというのが、「勝負強くなった」ということでしょう。そういう意味で、「やっとスタート台」(岡田監督)というのは心強い発言です。
「南アフリカを除いては最初に出場を決めた」といったことはあまりどうでもよい。もう今日になったら韓国も、オーストラリア、オランダも出場を決めているわけだし。4大会も連続出場しているのなら、ちょっと「世界を驚かして」欲しい。それが存在感というものでしょうから。
そう言えば昨日も今日も暇さえあればスポーツを見ていた。ダルビッシュの防御率が1.32になったのは、昨日取られた3点が響いている。マー君が1.23だったから。まあこの二人はパリーグでは突出している。1点台はこの二人だけです。
そういえば中継はなかったが、イチローの28試合連続がなるかどうかもMLBのHPで見ていました。四球が一つあったかな。イチローが最後の打者で、三振で終わり。今日はまた4ー3で勝利に貢献している。
心配なのは松井ですよ。今のまま、つまり守れない、チャンスに打てない状況が続けば今季末でヤンキースを出るのでしょう。どこに行くのか。新天地で活躍する手もある。

2009年06月05日(金曜日)
(16:53)今日一番笑えたのは「世も末だな」という高校生の言葉でした。おばあちゃんからお金を奪おうとした人間を捕まえたら、それが警察官だったことを知った二人の高校生の一人の発言。
しかも彼は、テレビのインタビューにぶすっとして「世も末」という雰囲気を醸し出しながら言っている。つい吹き出してしまいました。まあ笑える以上に、「どうなっているの.....この国は?」という深刻な問題ですが。
もう一つ、つい笑ってしまうのは、次の北朝鮮の指導者になりそうな金正雲と言われる20代後半の人物の写真が、どうみても小学生の時代のものであり、しかもそれが決まって一枚しかないということ。
「なんという閉鎖された国か」と思うわけです。これはもうあるポイントを通り越していて笑える。どんな人物か知りませんが。正男さんは「粛正が始まった」として、もう北朝鮮には帰らないそうです。じゃ正哲さんはどうしているのだろうか。

2009年06月04日(木曜日)
(16:53) 今日見たテレビ番組(といってもオンデマンドでしたが)では、「中国の絶美は“玉”にあり」というハイビジョン特集が面白かったですね。「切磋琢磨」が玉を切り、大体の形にし、磨き、そして仕上げる中国での作業工程全体を指すとははっきり認識していなかったように思う。
今日見たテレビ番組(といってもオンデマンドでしたが)では、「中国の絶美は“玉”にあり」というハイビジョン特集が面白かったですね。「切磋琢磨」が玉を切り、大体の形にし、磨き、そして仕上げる中国での作業工程全体を指すとははっきり認識していなかったように思う。
中国の歴史における「玉」の位置づけが分かって面白かったし、今活躍している中国の名工が何人も登場したのは中国における「匠」の話として興味深かった。玉人、玉液、玉兎などなどを覚えました。
最後に玉を教えていた先生が生徒に「玉不琢不成器、人不学不知道」と教えていたのが、「なるほど」と。崑崙山脈から切り出したり、川で見付けた玉を石の特質や色合いから「こういう作品にしよう」と構想し、そこから凄まじい時間をかけて仕上げていく。この番組では、「完璧」も玉に関係した言葉だと紹介していた。
そう言えば今日は天安門事件から20年ですね。戦車の前に立つ人のビデオを見ると、江袋さんを思い出します。彼がホテルのベランダから撮った絵です。それにしても、真実を明かさずに今でも異常なまでに事件の報道を遮る。中国の体制の限界がよく出ている。
ところで新しいエッセイがアップされました。ポスト京都議定書論議を取り上げました。

2009年06月03日(水曜日)
(23:53)村上春樹著によるこの小説(1Q84)の最後の方にはビックリしたな。高円寺、その南口、環七沿い.....ははは、私が週末にチャリでうろうろしている場所です。家からも近い。青豆と天吾がニアミスする場面です。あの公園かなという連想もできる。六階建ての新築マンション.....。
新幹線の移動時などを利用して読み終えましたが、一気に読み終えたいと思わせ、事実読み終えてしまったという意味では非常に良くできた小説です。極めてミステリアスであり、事実ミステリー仕立てのところが強くあり、sexuality は実にふんだんに、かつ多様にあり、物語のマージの仕方は良く計算されていて、作者の知識の豊富さにしばしば感心でき、「これは何を言っているんだろう」と頭を傾げる場面もいっぱいある。登場人物達のその後も気になる。
ジョージ・オーウェルの例の1984年を発想の原点の一つにしていて、ビッグ・ブラザーに対するリトル・ピープルが物語の大きなキーです。しかしそれが必ずしも何かは分からない。読んだ人によって違うでしょうし、時間の経過の中で理解が変質してくる可能性もある。
ただし読んでいて思ったのは、1984年ですから四半世紀前の話であり、ケイタイ電話も登場しない一昔前の話に思えなくもない。当然ですが、過激派とか宗教団体などが頻繁に登場するのも、今の我々には「やや通り過ぎた」感じがする時代背景です。むろん、小説のテーマは今日的ですが。
あと思ったのは、登場してくる人物がいずれも尋常ではない過去を持つ尋常ではない人で、むろんその種の人種の登場は必要なのだが少し多すぎるのではないか、という点。「ノルウェーの森」の時の方が自分を投影できる人間がもっと多かったような気がした。かなり忘れていますが、緑ちゃんは好きだったな。むろんこれは、今回の小説の登場人物には自分を投影できない、と言っているのではなく。
しかし重いですよ。いや複層的な意味で。関西に2冊持って行って、2冊もって帰ってきたのですが、これが重かった。もう結構、という感じ。新書を読むケースが多い私としては重かった。それでも読み始めると止まらなくなる。考えてみたら実に久しぶりに長編小説を読みました。ある意味では愉しかった。
それにしても青豆と天吾はなぜ短時間にあれほどお互いが思う仲になったのか。小さかったからだろうか、それとも同種の人間だったからか....なんてまだいろいろ考えてます。ははは。尾を引く。

2009年06月02日(火曜日)
(09:53)予想したとおり、新聞の紙面はGM一色ですね。まあ世界中の新聞がそうでしょう。北朝鮮など一部を除いて。
しかし肝心な点は「人々は何かしら車を買うときはワクワク感を欲するものだ」ということです。「ワクワクする車」さえあれば、ガバメント・モーターズの車でもかまわない。しかし政府がお金をつぎ込むだけでは、「ワクワクする車」は出来ない。そこがポイントです。
だから私は今の情勢だと、イギリスのブリティッシュ・レイランドが結局は行き詰まって切り売りされたように、早ければ2〜3年後にはシェビーとキャデラックの2部門がどこかの企業に切り売りされ(この二つはアメリカ人の心だ)、GMが本当の意味で命脈を絶つと思う。私の勘です。そうなっても、アメリカ経済には壊滅的な打撃にはならない。アメリカは産業を捨てることを厭わない国です。他に産業を生む。
それを政治が曲げようとしても(例えばバイアメリカンなどの動きで)、無理でしょう。多分。そういう気がする。聞こえてくる情報によれば、GMからは既にかなりの技術者などなどが会社を去っている。私の従兄弟はそれで忙しいと言っていた。オバマは大きな賭をしたと思う。これしか選択肢はなかったのでしょうが。
ところで、暫くお休みしていた「伊藤 洋一のRoundup World Now」を7月3日から再開します。以前と同じ形で、ラジオ日経さんとポッドキャストで。これからも世界経済、日本の経済、それに世界の政治情勢は大きく動くでしょう。私なりの解説をお届けできればと思います。お楽しみに。

2009年06月01日(月曜日)
(16:53)GMが正式に連邦破産法11条申請の書類を持ち込むのは日本時間の月曜日午後9時(米東部時間の午前8時)だそうです。ニューヨークの南地区破産裁判所に。その瞬間にGM、あのアメリカを代表する民間企業だったGMは国営企業になる。例え数ヶ月間にせよ。
やはりこれは重いし、思うことはいっぱいある。なぜこうなったのか、どうして止められなかったのか、アメリカは本当にUSSA(United Socialistic States of America、またはUnited States of Socialistic America)になってしまうのか、など。
大まかの手順は以下のようになるらしい。GMを二つに切り分ける。良い資産を残した「新生GM」とそれ以外の「旧GM」に。新生GMの資本構成は政府72.5%、債権者10%、UAW17.0%。しかし債権者グループは、新生GMの時価総額が上がる過程で、まず7.5%のワラント(新株発行)を受領・行使(確か時価総額が150億ドルだったか)、次にもう7.5%を受領・行使(うろ覚えですが340億ドル)する。この段階で債権者グループの持ち株比率は25%になる。
最後に時価総額が740億ドルに達したときにUAWが2.5%のワラントを受領・行使し、資本構成は政府55%、債権者グループ25%、UAW20%となる。つまり債権者グループの持ち株比率がUAWを上回る。
この点が重要でした。そもそもGMに対しては債権者グループが270億ドル、UAWが200億ドルの債権を持つとされた。その債権者グループに対して当初はどうころんでも10%の持ち株権利しか付与しなかった。17.5%を与えられたUAWより小さい。これは強引でした。そのまま突っ走れば破産法を適用しても債権者との関係がこじれ(事前調整が出来ずに)、あまたの裁判を起こされる懸念があった。
で債権者グループの権利を引き上げることによって、報じられるところでは「半分」からは「それでok」というゴーサインをもらったらしい。「事前調整が進んだ」ということです。UAWとの間でも、「労働賃金をどう下げる、どのくらい下げる」といった事前調整を政府とGMはかなり進ませた。その上での月曜日午前8時での連邦破産法(日本で言う民事再生法)11条適用申請です。だから「事前調整型、pre-packaged」と呼ばれる。
しかし、山ほどリスクがありますよ。テクニカルなリスク、そして根源的なリスク。テクニカルなリスクは、まだ訴訟リスクを抱えているという問題です。クライスラーはベンツと一緒の時もあって、そこからファンドに買われたので実は株主は機関投資家が圧倒的に多かった。しかしGMは多数の個人投資家を抱えている。債権も非常に小分けされているケースがある。訴訟リスクにどう対処するか。
明日からはどう考えてもGMは国営企業になる。しかし工場を切り離し、労働者を解雇しなければならない。国がそんなことを冷徹に出来るのか。また新しいGMは誰が経営するのか。今までのヘンダーソンでいいのか。ヘンダーソンの下にはワゴナー時代の部下が一杯いるが、それでいいのか。もっと重要な問題は
などなど。最後が一番長期的に重要です。電気自動車のボルトもどうやら動きは鈍そうだ。
そもそも、「破産法11条申請→再生手続き→一応の復活」と事が運んだ企業の多くは、「結局は4〜5年たつとまた行き詰まる」という説もある。リストラクチャリングなどがうまく行かないし、市場との折り合いが付かないため。
確かに過去はそういう例も多かったし、GMも消費者が欲する車を敏速に市場に投入できるかどうかを考えると怪しい。「新GM」となったあともGMが長きにわたってアメリカの自動車市場で存在感を示し続けるかどうかは不明だ。
オバマはGMの国営化で非常に大きなリスクを背負ったと言える。「やっぱし潰した方が安かった」となったら今の判断を問われることになる。以前調査したことがあるが、アメリカ国民はGMに対しても非常にクールでしたから。