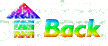2013年11月29日(金曜日)
(23:25)ちょこっとお台場の「東京モーターショー」を覗きましたが、凄い人出でしたね。開始から既に数日が経ているというのに。
「世の中には車好きがこんなにいるのか」という気分になると同時に、これだけのファンがいるのなら「車の産業はまだまだ大丈夫」という気がしました。本当はもっと部品とかいろいろ見たかったのですが、あの広大な東西に分かれている会場を全部回るのはなかなか骨が折れる。

ホンダのブースではバイクが一杯出品されていて、「うーん一度乗ってみたいな」というのが一杯。知り合いのナナハンに乗ったのはもうかなり前ですが、とにかく一人で起こせなかったことを覚えている。それじゃダメでしょう。
しかし最近はいろいろなタイプが出てきていて、「へえこんなのも」という印象があった。青山のホンダの本社のショールームに飾ってあるのはごく一部であることがよく分かる。
それと見た中では軽自動車の進化には目を見張りました。最近の高速道路では追い越し車線において軽が普通車の後ろを追尾し、時にまくっている姿がよく見られますが、今日はその車内のスペースの広さにも関心。普段あまり入ったことがないので。
中でも面白いと思ったのは、もう街を走っているそうですが、ダイハツのココアという車は、名前も面白いし「なかなか良く出来ている」と思いました。技術の進歩がこの分野でも面白い車を作っている、と思いました。ちょっくらかわいい。
UDトラックというあまり聞いたことのないトラックメーカーがあったので「あれ」と思ったら、以前の日産ディーゼルでした。今はボルボ傘下だとか。その一番大きなトラックの運転席に登りましたが、その高いこと。「上からは世界がこう見えるのか」と思いました。
燃料電池車や電気自動車も展示されていて、ニュース的にはそれらの方が大きく扱われていましたが、私の場合はそれらはこれまで取材で嫌と言うほど見てきたので、今回はスタイルとか運転席の乗り心地中心に見ることが出来たのが良かった。
また来年も盛大にやってほしいな。もうちょっと時間を使って見て見たい。

2013年11月28日(木曜日)
(16:25)まあこのニューヨーク・タイムズの記事にもありますが、ミスカリキュレーションでしょう。まだまだ国際政治に疎い国という言い方も出来る。
もし「戦っても良い」と考えるなら別です。しかし大部分の軍事専門家は中国の空軍力はアメリカや日本を敵にして勝てないと踏んでいる。それは装備でもあるし、パイロットの能力でもある。
にもかかわらず空戦をして負けたら、「中国の夢」は無残なことになる。そんなリスクは習近平政権がもっとも犯してはならないリスクです。間違ったら、「戦って負けた」ということで、一気に体制崩壊になりうる。
静かに引き、識別圏は撤回せず、せいぜいアメリカ軍や自衛隊の偵察機や戦闘機のあとを嫌らしくつけるといったことがせいぜいの筈です。それでも潜在的な常在危機を抱えることが出来る空軍は「だから俺の所にも権限と予算が必要だ」と主張できる。
中国にはもっとやらなければならないことが一杯ある。「世界第2位」と言ってはばからないが、国民一人当たりでは何位だろう。せいぜい数千ドルです。先進国は総じて3〜4万ドル。とても進んだ国とは言えない。
課題が山ほどある故に、体制は安定しない。安定しないからなんとか国民が一つになる課題を作る。作ってもその課題が中国の思惑通りに進めば良いが、時々彼等の思惑を超えて事態が動く。
彼等にとって一番恐いのは、国内情勢が予想外に動くことでしょう。アメリカが何か言っているとかはあまり中国の指導部は気にしないはずだ。何よりも国内の人々がどう動くかだと思う。
リーマンショックの時に世界中の指導者が胡錦濤の所に行って「世界経済を助けてくれ」と言ったことが、中国が過剰な自信をもった一つの要因だったという話を聞いたことがある。多分それは正しい。
だから世界も「中国次第」といった事実と違うことは言わない方が良い。富を行使している消費者の数ははるかにアメリカよりも少ない。それにしても、「身についてしまった過剰な自信」ほど危ないものは無い。日本もそれの恐ろしさを経験した。
中国には早くそれに気付いて欲しい。

2013年11月27日(水曜日)
(06:25)今朝目を覚まして何本かのニュースを見て、「アメリカはちゃんとやるべきことをやっているな」と思ったのは、このニュースです。
すなわち、アメリカは中国が突然設定した「防空識別圏」を完全無視する形で、月曜日の深夜(米東部時間)に同圏内での二機のwar planes(一部報道ではB52らしい)による訓練飛行を実施し、尖閣諸島の上空を事前予定通り飛行した、というもの。中国側からは何のコンタクトも、何のアクションもなかったと。
アメリカは、中国の突然の発表に強い不快感と警戒感を示し、それがアメリカ軍の飛行・訓練区域とも重なることから、むろん飛行計画を中国側に提出することもしないし、中国機が接近してきてもその指示に従うことはしない、という方針を明確にしていた。
今回のアメリカの行動は「言葉を行動で担保した」ことになって、ナイスだと思う。日本の航空会社も台湾線などでいったん行った中国側への飛行計画の提出を中止したらしいが当然だろう。
言葉は勇ましいが、中国の指導部はもし何らかの軍事アクションを起こして、万が一日本やアメリカに負けたらそれこそ体制に影響が出ることをよく知っていると思う。今回の措置は中国という国、というか軍部を抑えきれない共産党独裁の国の危険性を世界にしらせしめた、という点で中国には大きな失点になったと思う。
「ちゃんとやるべきことをやっていないな」と思ったのは、安倍自民党です。福島で公聴会を開いた翌日に、特定秘密保護法案を衆議院の委員会と本会議で強行採決した。あり得ないでしょう。公聴会に参加した福島の人達は、「アリバイ作りに使われた」と思う。
公聴会を何のために開くかと言えば、そこで聞いた意見を法案に生かすということです。昨日の今日では生かすことも出来ない。安倍首相は「国民の不安はよく承知している」と。だったらその不安が低下するまで審議を尽くせばよいのに。
ちょっとがっかりですね。こんな政局運営をしていたら、安倍人気は案外近い将来に急落する可能性がある、と思う。

2013年11月25日(月曜日)
(14:25)うーん、難しい問題ですね。改築すべきか、そのまま残すべきか。でも私は改築派かな。寂しいが。
道後に一晩いたあと、午前中に昔から好きだった「鷹ノ子温泉」に行ったのです。湯質が凄く昔から良かった。松山周辺の温泉では完全な鷹ノ子ファンだったので、久しぶりに。

最近その鷹ノ子温泉がリニューアルしたと聞いた。「いつか行こう」と思っていたのですが、この週末にチャンスが出来た。久しぶりに来てみたら、「田んぼの中にぽつねん」という感じでは全く無い。
近くにはホテルまで出来て、温泉の建物もとっても奇麗になった。湯船の数も増えたように思う。サウナも出来て、湯質は相変わらずつるつるでナイス。しかし昔を知っている人間には、「かつての寂びたたたずまいも良かった」と思える。

対象的なのは、道後の温泉です。神の湯と霊の湯の二つの湯に、一階、二階、三階の待合から入る方式は昔から変わらない。神の湯も霊の湯も晩と朝に二回入りましたが、以前と全く変わっていない。
しかしいかんせん古いのです。最初にこの温泉に入ったときから「こりゃ古い」と思っていたのですが、最近は磨きがかかってきた。廊下はぎしぎしいうし、階段はこれ以上ないというきつさ。
お客さん同士が言っているのです。「改築したいらしいけど、お金がないらしい」とか、「でもこのままがいいじゃない」とか。うーん、私は改築派だな。銀座の歌舞伎座方式かな。
歌舞伎界の人が、「本当にあそこまで忠実に修復してくれて感動した」と言っていた。その方式ではどうだろう。もしお金があれば。思うのは、鷹ノ子さえ入るのだけで650円で、「妥当だな」と思う。
しかし道後の温泉は一階の神の湯だけに入るのなら、もっと安かったように思う。これでは回収費用は貯まらない。何らかの工夫をしないといけないように思う。改修にもいろいろある。写真にもある独特の景観を壊すのは反対だが、内部の改修はやるべきでしょう。

2013年11月25日(月曜日)
(05:25)ほう、イランと六カ国(米・英・仏・独・中国・ロシア)が、イランの核開発について「暫定合意」ですか。オバマ大統領は、「最初の第一歩の合意」と評した。日本時間日曜日に、約10年に及ぶ on and off の会談の後に合意した。
中味は英FT紙によれば、
しかし同紙は「Key oil, banking and financial sanctions would remain in place and be enforced during the interim deal.」(石油、銀行取引など金融に関する対イラン制裁は、この暫定期間中は実施されたままとなる)とも報じているので、今後6ヶ月はイラン国民が必要とし、イランで品薄な70億ドル分の商品は流入することが出来るものの、イランが解除を望む石油輸出や金融取引に関しては制裁が続く、というやや中途半端なもの。
「5%云々」に関しては、今までの国連安保理の決議は、「イランは濃縮活動を凍結」となっていたので、確かに6カ国サイドは譲歩したことになる。
イラン国内の受け止め方はどうなんでしょうね。まだメディアにもその辺の反応は出てきていない。部分的に濃縮が認められたのは勝利と取るのか、それとも石油、金融の制裁が続くのを負けととるのか。
あくまでも”暫定”なので、包括合意に進めるのかどうかがポイントでしょう。多分査察などを巡って今後もいろいろあるし、イランの国内情勢がどう動くかも予測が難しい。
しかし興味があるのは、このイランと主要6カ国の合意が、例えば北朝鮮などの核開発スタンスに与える影響です。イランが済めば主要国の関心は北朝鮮に向く。北朝鮮がどう反応するかも注目。
オバマ大統領が言うとおりの「一歩前進」なのか、でも実際にはインドなど核開発国が増えている中では、”一歩”までは行かない前進なのかは難しいところです。

2013年11月23日(土曜日)
(08:25)今週に入る前のニューヨークの株式市場の関心は、ダウが16000ドル、SP500が1800、そしてNASDAQが4000の水準を越えるかでしたが、金曜日の取引でこのうち二つは達成。ニューヨークの株式市場は史上最高値圏での週の終了。
各指数の引けは、DJIAが16064.77で+54.78、Nasdaqが3991.65で+22.49、S&P 500が1804.76で+8.91 0.50%。今週はほんとにたくさんの米金融当局者がおしゃべりをし、そして10月末のFOMCの議事録も出た。結局のところ「QE3が縮小しても、FRBは実に慎重に”超”緩和状態を続ける」との確信が強まった、というのが大きな流れだったのだと思う。
それにしても「景気対策は中銀頼み」という状況が強まっている。日本とアメリカでは「ゼロ金利」「非伝統的な量的緩和」を含む“超”金融緩和状態で景気浮揚を図ろうとしているし、今まで「0.5%」という比較的ビジブルな金利を保っていたECBもゼロ金利に近い「0.25%」に政策金利を下げた。
過去に世界の経済がこれほど「中銀依存」になったことはない。ECBではマイナス金利の検討も始まっている。しかし財政が動けない状況では、そして短いインターバルで”危機”(リーマン・ショックなど)が起きる現状では、こうした金融依存は今後も進行する。
もっともそれに支えられている面も強いが、日本でもアメリカでも結構企業業績が良い。それも株高の背景。しかし今週のFOMC議事録でも明らかになったが、QE3はいずれ縮小される。縮小に伴う新たな緩和措置の検討はしているにしてもである。具体的には、「過剰準備に対する利子率の引き下げ」など。マーケットとの対話が重要だ。
11月から12月は例年株が上がりやすい。ヘッジファンドの決算は過ぎたし、いろいろな面でお金が投資家に入ってくる。だから上値を追う可能性は日米で高いが、危うさが伴うことは確かだ。

2013年11月22日(金曜日)
(19:25)午後一瞬「あれ」って思ったのです。米上院で多数を占める民主党が野党の議事妨害(filibuster)を防ぐ目的で、上院承認人事に必要な票数を今までの60票から単純過半数(51)にした、と聞いたからです。
「ということは、上院の銀行委員会の承認を得たイエレン次期FRB議長の上院承認は確実になったのでは.....」と思ってウォール・ストリート・ジャーナルを見たら、やはりそうでした。
記事には「Janet Yellen's confirmation as the next Federal Reserve chief became a virtual lock Thursday when a Senate committee approved her nomination and Senate Democrats eased the confirmation process for most presidential nominees.」と書いてある。
米上院銀行委員会は14対8でイエレン次期議長を承認。その後もほぼ大丈夫だが、それでも何かあるかも知れない、「60票必要だから」と思われていた。しかしそれが51票になれば民主党議員だけの賛成でOK。「a virtual lock 」というわけです。
イエレン承認もあって、週初のザラ場で16000ドル台に乗せたニューヨークのダウ平均はその後数日安い展開だったが、木曜日になって初めて引けで大台乗せ。史上最高値です。今週の議事録公表のあとに書きましたが、「QE3は縮小しても、なにやかやと強力な緩和措置を続ける」のがイエレン次期議長でしょう。そういう意味では、マーケットは安心し始めている。
それにしても米民主党もここに来ていろいろ攻勢を強めている。今アメリカはこの問題で大騒ぎ。PBSを見ていたら、両党の議員が出てきて喧嘩状態。明らかに野党の妨害工作は難しくなる。アメリカでも政治は混迷ですね。民主党は混迷を打破しようとしたのでしょうが。

2013年11月21日(木曜日)
(23:25)東京新聞で「国の税収、2兆円上振れ 13年度、企業収益拡大」というニュースを見た後、為替市場を覗いたらドル・円が101円台に入っていました。
長く100円台に乗っては落ちていたドル・円相場。ドルの上抜けという感じなんでしょうかね。日本の貿易収支赤字が大幅な上に定着し、アメリカの金利が上昇気味であり、そして国内の機関投資家が外債投資スタンスを強めた....。それだったらドル・円は上に行く。
ドル・円が上に行けば、総体的には輸出型の企業は同じ海外売り上げでより多くの円が入ってくる。しかし液化天然ガスの輸入には、スポットを中心により多くの円を支払わなければならない。全体的には今程度の円安は日本経済にはプラスなんでしょうね。
東京新聞の記事は、「2013年度の国の一般会計税収が、今年1月時点の見積もりより2兆円程度上振れし、45兆円台となる見通しであることが21日分かった。円安などを背景に企業収益が拡大し、法人税収が想定を上回る見込みとなったのが主因。」と。
さらに「政府は税収の上振れ分を、12月中旬に編成する13年度補正予算の財源に充てる。補正予算は消費税増税に備えた経済対策を盛り込み5兆円規模となるが、12年度決算の剰余金なども活用して国債の追加発行は見送る。」と。
「追加発行を見送る」とはナイスじゃないですか。今日は黒田さんが記者会見していましたが、ちょっと一本足打法に疲れている雰囲気も見えたな。表情に。それなりきに成果は出始めてはいるんですが.....続くかどうか。

2013年11月21日(木曜日)
(06:25)FOMCの10月29〜30日の会合議事録もなかなか読み応えがあったので後で取り上げますが、私がそれよりも興味を持ったのは、このFTの記事かな。タイトルは「Yellen’s path to Fed is eased by support of key Republican」というもので、この結果彼女は上院での承認に必要な60票を確保しそう、つまり次期FRB議長になることになりそう、というもの。
この記事は、FRBの”超”緩和政策批判の急先鋒だったボブ・コーカー上院議員(Bob Corker, テネシー州選出共和党上院議員)が、「In the end, I do believe she has the qualifications necessary to be the Fed chairman and plan to support her nomination」という声明、詰まりイエレン支持の声明を出したことを取り上げている。
重要なのは、FRBの今の金融政策に反対なのに、なぜ彼が彼女を支持するに至ったかです。FTには、「Mr Corker said his conversations with Ms Yellen had persuaded him that she recognises the downside of Fed asset purchases and will be willing to end them in due course.」と書いた上で、さらに彼の言葉として「“She understands that monetary policy is a blunt object, that distortions are occurring, and that the affluent disproportionately benefit from easy money policies. During our discussions, she made a commitment to moderate purchases as soon as she believes the data supports that action and shows that the current status cannot continue.She believes, to a certain extent, that the Fed may have become a prisoner of its own policies.”」と書いてある。
つまり彼女は、非常に重要な共和党上院議員の支持を得るために、「データが正当化したら、時間を置かずに量的緩和の縮小に着手すると約束した」ということです。
この上院議員が述べている興味深い点は、「the affluent disproportionately benefit from easy money policies」という点で、彼女が持つ「とにかく成長を高めて雇用の改善を図らねばならない」という視点とは異なっている。しかしそれはこの記事にもある通り、重要な政治的問題です。
イエレンが次の議長になるためにややリップサービスを余儀なくされている中で、あと任期が2ヶ月ちょっとになったバーナンキは、結構自由に喋っている。例えばこのウォール・ストリート・ジャーナルの記事によれば、「short-term interest rates may stay near zero "well after" the jobless rate falls below 6.5%」と。これまで米金融政策における「失業率6.5%」は、ゼロ金利解除のシュレショールドと解釈されていたので(実際に彼はそう言っていたと思う)、「そうじゃないよ」「そうはならないのでは」と述べたことになる。無論イエレンはQE3について語り、バーナンキはゼロ金利に関して述べている。違うが、「どっちなの」という雰囲気。
そこで議事録です。発表直後からニューヨークの株価を落としたのは、次の部分です。
During this general discussion of policy strategy and tactics, participants reviewed issues specific to the Committee's asset purchase program. They generally expected that the data would prove consistent with the Committee's outlook for ongoing improvement in labor market conditions and would thus warrant trimming the pace of purchases in coming months. However, participants also considered scenarios under which it might, at some stage, be appropriate to begin to wind down the program before an unambiguous further improvement in the outlook was apparent. A couple of participants thought it premature to focus on this latter eventuality, observing that the purchase program had been effective and that more time was needed to assess the outlook for the labor market and inflation; moreover, international comparisons suggested that the Federal Reserve's balance sheet retained ample capacity relative to the scale of the U.S. economy. Nonetheless, some participants noted that, if the Committee were going to contemplate cutting purchases in the future based on criteria other than improvement in the labor market outlook, such as concerns about the efficacy or costs of further asset purchases, it would need to communicate effectively about those other criteria. In those circumstances, it might well be appropriate to offset the effects of reduced purchases by undertaking alternative actions to provide accommodation at the same time.マーケットは最初の数行、つまり「They generally expected that the data would prove consistent with the Committee's outlook for ongoing improvement in labor market conditions and would thus warrant trimming the pace of purchases in coming months.」しか見ていないようだが、ここから数パラは結構読んでいて面白い。
例えば、この中には新しい金融緩和策の検討をFOMCが内部でしていることも分かる。
Participants also discussed a range of possible actions that could be considered if the Committee wished to signal its intention to keep short-term rates low or reinforce the forward guidance on the federal funds rate. For example, most participants thought that a reduction by the Board of Governors in the interest rate paid on excess reserves could be worth considering at some stage, although the benefits of such a step were generally seen as likely to be small except possibly as a signal of policy intentions. By contrast, participants expressed a range of concerns about using open market operations aimed at affecting the expected path of short-term interest rates, such as a standing purchase facility for shorter-term Treasury securities or the provision of term funding through repurchase agreements. Among the concerns voiced was that such operations would inhibit price discovery and remove valuable sources of market information; in addition, such operations might be difficult to explain to the public, complicate the Committee's communications, and appear inconsistent with the economic thresholds for the federal funds rate. Nevertheless, a number of participants noted that such operations were worthy of further study or saw them as potentially helpful in some circumstances.つまり過剰準備に対する利子の引き下げです。当然お金は他に出ていくので、「さらに金利が低くなる」という効果がある。しかしこれは議事録自身が指摘しているように、「効果は小さい」という判断。あとはバーナンキも述べた「6.5%以下まで....」をフォワード・ガイダンスの面でも明確に述べるかどうかを委員達は検討。
しかし議事録公表の前にバーナンキが実質的に喋ってしまった。まニューヨークの株価がこうした米金融政策を巡る一連の「divide」を見て、「おや、また12月にも量的金融緩和の縮小があるかも」と思って下げたのは、同株価が「一度きちんとコレクションをしておく必要がった」のに口実になったということでしょう。何せダウ工業株30種などは、高値からまだ100ドルも離れていない。
しかし分かったことは、量的金融緩和の縮小はちょっと早くなるかも知れないが、バーナンキの言葉を借りれば、「それこそゼロ金利は相当しばらく続く」ということであり、場合によってはFRBは今のゼロ近傍の金利をさらに下げることも検討している、ということでしょう。色気もなく言ってしまえば、「相変わらずデータ次第」ということですが、昨日のアメリカから発表された小売売上高などなども、「米国経済はこっちを向いている」と一言では言えない。

2013年11月20日(水曜日)
(23:25)ははは、久しぶりの人に会えて良かったな。高校時代以来。大学も同じだったが、彼は留学などして年次は一年ずれた。その後彼はほぼずっとアメリカ住まい。このままアメリカに骨を埋めるつもりとか。私はアメリカに居住していたのは、4年だけ。
会ったのは「The Monterey Institute of International Studies 」というアメリカでは珍しく「外国語に強い学生を集めた大学」で先生をしている赤羽君。一時帰国中。彼は基本的にはアメリカの政治が専門で、最近の同国は分からない事だらけなので、私が矢継ぎ早に質問をぶつける展開かな。
ま、面白かった。モントレーというカリフォルニアに長く住む人の感触が良く伝わってきたし、アメリカの今の政治状況も。共和党の今後とかいろいろ話しました。やはり中国からの留学生が多いが、その大部分はアメリカに残る意向とか。
日本の大学の先生よりは、雑用がなく、なかなかよさそうです。お手当は日本の教授さんたちとあまり変わらないようですが、生活費がアメリカは安いので、同じ額面のお給料でも日本の先生の「1.5倍くらいですかね」と。
話していて、お互いにあちこちに行っている人間なので、結構話しは広がりました。彼の場合、結局「国際関係」という領域ですから、世界中のあちこちの大学から学科開設などで呼ばれるようなんですよね。で、世界各地に行く。
日本での短い滞在が終わると、ウラジオストクに行くそうで、それも大学関係の仕事だと。話していて思ったのは、同じ領域の人間として情報交換など今後面白いことが出来そうだ、ということ。
ところで、彼のお嬢さんは今東京に居て、モデル活動をしているという。既にいろいろなところで露出があるようですが、赤羽光子さんのサイトでも分かるように、ペンや鉛筆を使って書く「絵」も好きなようで、「(絵は)その時の雰囲気で」ということですが、「一日一絵」とはなかなか面白い試みだと思う。彼女のフェースブック・サイトも面白い。

2013年11月20日(水曜日)
(00:25)朝日に載っている「篠田プラズマが事業停止 曲がる大画面ディスプレー開発」はショックなニュースだな。2010年の夏だったと思ったのですが、取材させてもらったこともある会社ですし、面白い技術だと考えていて、その後も私として気になっていたので。
「ycaster 篠田プラズマ」で調べたら、ありました。ここです。「日本には良い会社があるな」と思いながら取材しただけに。
理由については「研究開発費がかさむ一方で販売は振るわず、赤字続きで資金繰りが悪化していた」と朝日。心配なのは、「事業を停止し、約30人の全従業員を解雇した」とある点。その後の付き合いでSNSで接触を続けている方もいますので。
一つの望みは、「取締役5人が残り、スポンサー企業を探して再建を目指すという」ということ。富士通さんを含めて是非スポンサー企業が出現することを望みます。ポイントは小型化と価格引き下げ余地でしょうか。ディスプレーは伸びる分野だと思いますので。HPは今は見れないようです。

2013年11月19日(火曜日)
(03:25)上げ相場を強める中で、先週末の段階でダウが16000、SP500が1800、そしてNasdaqが4000に接近していたニューヨークの株式市場。それぞれにとって、過去にない高みですが、週明け早々にうち二つはザラ場で達成のようです。
これを書いている今現在で各指標の「この日これまでの高値」を見ると、ダウ工業株30種平均が16030ドル、Nasdaqが3995、SP500が1802。あくまでザラ場なので、引けがどうなるかは分かりません。大きく反落するかも知れないし、もう一度高値を追うかも知れない。
しかし「全般的にはニューヨークの株は強い」ということでしょう。ただし為替市場を見ると、ドル・円は100円前後で昨日とあまり変わらず、円はその他の国の通貨に対しても大きな動きはない。
年末接近の中で、ニューヨークの各指標は今年は20数%上昇しているのかな。株価を支えているのはニュース的には、
などでしょうか。しかしニュースにならないが重要な要因があると思う。それは、株への代替投資先がない、ということだと思う。世界的に低金利は極みに接近している。ということは株と並ぶ投資対象としていつも考えられる債券にはなかなかこれ以上お金を入れられない、という現実がある。
株と債券が「流動性の高い投資」の代表選手ですから、その一方が行き詰まると、投資資金を持っている向きは、もう一方(株)を買うか、流動性の落ちる他の投資対象に目を向けるしかない。金とか不動産とか。しかし投資家は流動性を好む。
大台替わりは、投資家を惑わせるんでしょうね。常識的には。「ちょっと足が速い」と考える人も出てくる。しかし「他にないのだから」と考える向きもあると思う。今の相場は「イエレン相場」とも言えるなかで、株という資産価格の上昇をFRBがどう考えるかが、今後を考える一つのポイントでしょうか。
しかし今のところは、「雇用情勢の改善」にFRBの目は向いているように思える。

2013年11月18日(月曜日)
(05:25)「今年の冬はすっごく早く来ている」というのが、この週末に持った印象でした。
久しぶりに北関東をうろうろしたのです。伊香保とか日光とか。ひょっとしたら紅葉が綺麗かも知れない、と思って。しかし伊香保の有名な河鹿橋も既に終わりに近づいていたし、その後に行った日光の中禅寺湖からいろは坂も既に紅葉はなし。調査不足でした。ま、目的は温泉ですが。
もっとも印象的だったのは群馬県から栃木県に抜ける移動をしたのですが、金精道路などは既に山頂に近い一部が積雪していて、通常タイヤではようやく慎重に通れるくらいに危なくなっていたこと。
今になって資料を見ると、この珍しい名前の道路は冬季閉鎖の対象のようですが、昨日の段階で通常タイヤではちょっと危ない状態のところもあった。バスなどは途中で止めてチェーンを巻いていました。
私はといえばその用意もなかったので、前の車との車間距離をとって慎重に移動。正午近くでしたが、依然として日陰で雪が残り、数カ所ですが危ない箇所がありました。私はどちらかと言えば雪道、氷結道路に比較的慣れているのですが、「危ないな」と思いました。
北関東や積雪が多い地方に行く方は、雪がいつもの年よりも早く来ていることをお忘れなく。実は去年も、関東南部の車が通常タイヤで北関東や東北でスリップ事故を結構起こした、と聞きました。
というわけで全くの印象ですが「今年は冬が早いのかな」と感じました。兎に角秋が短かった印象がする。これが残念です。

2013年11月15日(金曜日)
(05:25)上院銀行委員会の公聴会で明らかになった一番のポイントは、「オバマ大統領が次期FRB議長に指名したイエレン副議長は、特に大きな問題もなく来年2月から次期議長になる」ということでしょうか。
今までナンバー2としてバーナンキを支えてきた人ですから、「今までの政策を変える」などと言うはずもない。それは冒頭声明でも明らかです。まずは「Under the wise and skillful leadership of Chairman Bernanke, the Fed helped stabilize the financial system, arrest the steep fall in the economy, and restart growth.」と前任者を褒め称えた。
そして「私もその政策を続ける」との趣旨を述べて、政策の継続性を強調。つまり現行の毎月850億ドルの債券購入を「コストと有効性のバランスの上で」続けると述べた。開場中に行われたこの公聴会を聞いた株式市場は、これを好感。株価は各指標で史上最高値を更新し、アメリカの一部メディアのアナウンサーはこれを「イエレン効果」と呼んだ。
しかしイエレン新議長の話を聞いていて、筆者は継続性云々の話の前に「彼女は明らかにバーナンキよりもハト派、つまり緩和継続に乗り気」と写った。まず、「the Federal Reserve plays a role too, promoting conditions that foster maximum employment, low and stable inflation, and a safe and sound financial system.」と述べて、物価の安定よりも「maxmum employment」をFRBの役割として先に持ってきたこと。失業問題は、彼女の専門であり、彼女は率よりも中味を大事にする。
であるが故に、今の量的緩和の解除に関しては、バーナンキのように失業率が7%になったら量的緩和が終わるようにしたいとか、6.5%になったらゼロ金利の解除に着手したいというような「目安」を示さなかった。私が見た限りでは、です。議員とのやりとりの中でも述べなかった。
彼女は冒頭声明で「 I strongly believe that monetary policy is most effective when the public understands what the Fed is trying to do and how it plans to do it」といいながら、「どのような条件で(量的、金利抑制政策の解除を)」という点を曖昧にした。つまりthe publicには明かさなかった、ということです。
というような態度であるが故に、米短期金利の先物のレベルはこのところずっと下がってきている。イエレンの議長就任を予期してのことである。彼女のこれまでの発言を勘案すれば妥当なプライス・ムーブメントだと言える。
失業率のレベルなどの目安を示さないイエレンFRBの政策は、短期的には無論株価を押し上げる。しかも安定的に。やはり失業率が7.0%に近づくとバーナンキFRB下では「taperingが近いのでは」という緊張感が生まれた。今後のイエレンFRBでは、「そうでもなかもしれない」というイメージが強いから、有価証券市場にはフェーバーである。彼女のいくつかの発言を拾っておくと....
彼女の真価が問われるのは、例えばリーマンショックなど危機が訪れたときに何が出来るのか、何をするのかということになると思う。今日のところは、株式市場で株価が史上最高値を付け、債券相場も上げ、金相場が上昇し、原油相場が下落し、そして対円などでドルが強い(書いている時点ではドル・円は100円15銭)、という展開。あまりない展開です。

2013年11月14日(木曜日)
(13:25)昨日でしたかね、もっと楽しいことがあったのに、どうしても対応しなければならないことがあって、その時間の合間を見て火曜日の朝ダウンロードしたポール・マッカートニーの「NEW」を全部聞いていたのです。
「Queenie Eye」はコンサートで出た....、「New」はアルバムタイトル....などと思いながら。そしたら最後に「Struggle」という曲名が出てきた。「闘争」とか「苦労して何かやる」「苦闘」とか言う意味です。普通は。英語的にはもっと軽い印象もあるのでしょうが。
でも.....ですよね。ですから「あらら、今更彼は何を苦闘しているのだろう」と思いながら曲の演奏時間を見て驚愕した。「7:59」とある。つまりほぼ8分の曲なのです。これはとっても長い。「NEW」そのものが15曲57分のアルバムですから、その15パーセント弱を取っている。ビートルズの曲の中では長い「A day in the life」でも5分05秒くらいの曲ですから。
で興味を持って、ビートルズの曲で一番長い曲はと思って調べてみたら、 ビートルズの各種記録サイトに「The Longest Beatles Song Is Revolution 9--The White Album Which Goes On For 8 Minutes And 15 Seconds」とあった。
特に覚えていないが、確か「ホワイトアルバム」にはそのような曲があったような気がした。「Struggle」はそれに近い。それで歌詞を見たのです。結構パワーのある歌詞となっている。
Want to get you in my heart again
Want to love you once more
Want to have you in my heart again
Want to get you once more
If you wanna love, if you wanna fight
It doesn't really matter, I want you tonight
When I get you home, what I wanna do
Babe, I wanna sample everything with you
Yes, I wanna love you, I don't wanna fight
I can think of something when I get you home tonight
All I want is loving, anything will do
I'm your glass of poison and I'm acting up on you
If you wanna love, if you wanna fight
It doesn't really matter, I want you tonight
[x2]
Yeah, you know what you got here
You got the same old story happening again
The eternal struggle, the destiny of man
It's the same old story, it's happening again
Life's eternal struggle, the destiny of man
If you wanna love, if you wanna fight
It doesn't really matter, I want you tonight
All I want is love, anything will do
I'm your glass of poison and I'm acting up on you
It's the same old song
Being sung in the background, being sung up front
But if you wanna get it right, you gotta listen
Heed my words, listen to me!
Anytime you want me, I'm not hard to find
I can't get your loving, I can't get you off my mind
But if I need you sometime, you got me here right now
We can work it out together, we'll get through this somehow
It's the same old story, it's happening again
Life's eternal struggle, the destiny of man
[x4]
It's the same old story, it's happening again
Life's eternal struggle
どうしてなんでしょうね。この曲全体は「Japan bonus track」として存在している。ここで明らかですが、ということは.....。
歌詞を書いた人は、「ああ、もうこの曲は終わり」と思ったのか、それとも実物アルバムの歌詞部分にも収録されていないとか。私のはダウンロード・バージョンなので、そこは確認出来ない。
でも聞く分には、何回聞いても全く上の歌詞とは違う曲なのです。トーンも違う。最後は確か「How much you mean to me」かな。ちょっとミステリアスでした。なぜ ?

2013年11月12日(火曜日)
(15:25)フィリピンの台風被害に関する記事は数多くありますが、今日の新聞を読んでいて「これが一番リアルだな」と思ったのは、日経の体験記です。『「暴風、日本とケタ違い」 フィリピン台風で邦人駐在員 』。
この記事は、「不二製油」のレイテ島タクロバンの南10キロにあるヤシ油工場で唯一の日本人として働く岩本さんの証言をもとにしたもの。体験を語った記事ですから、災害が発生してから現地に行った記者の書いた記事とはやはり迫力が違う。今朝の新聞記事で一番読み応えがあった。
それにしても凄まじいですね。風速90メートル。想像がつかない。70メートル以上の風速の暴風を持つ台風を「スーパー台風」と呼ぶそうですが、70キロと90キロでは車を運転していても全く違う。だから実感としては今回の台風30号は「スーパースーパー級」でしょう。
記事には、「屋根のトタンなどが空を舞っていた」との記述がある。5メートルの高潮というのも、実は津波と同じほどの威力があるのではないか。今朝の出演番組でビデオを見ていたら、船が陸地にある。気仙沼と同じだ、と思いました。
日本に向かう台風は、海水温がそうはいっても低いために勢いは弱まるらしい。しかし同じ「台風」ですからね。26号とかは日本に来ていた。31号がほぼ確実に生まれる、と。
ハリケーンも台風も一部f凶暴化するばかり。危険な気象環境が形成されつつあるような印象がする。残念ですが。ま出来る準備だけしておきますか。

2013年11月12日(火曜日)
(11:25)「It's just unbelievable !」というのが、昨日のポール・マッカートニーの大阪公演の印象です。
あの歳(71)にしてステージウォーターを全く飲まずに歌い続け、ベースからギター、ウクレレ、そしてピアノまでの楽器を何回も替えながら使いこなし、集まったファンの為に大阪弁を頻繁に使ってみせ、「(誰かの)ため」に何曲も歌い、足を上げ国旗を掲げてステージを移動し、ジョークをぴっちり入れ、そしてアンコールには二度も応えた。全く疲れを見せなかったダイナミックな約2時間40分でした。

しかし何という声の張り、そして頭の回転。かっこよかったですよ。こちらが5曲ぐらいか一緒に歌ったら喉ががらがらになったのに比べて、なんと強靱な。午後7時10分前に舞台に登場して、それから2時間。ずっと見ていたが、水を全く口にしなかった。その後のステージでも。プロだと....。

顔の皺は進行した。彼が最初にドームの大スクリーンに登場したとき、ファンからは「オー」という声が。それは容貌の少しの変化は見えたものの、しかしそのしっかりとした顔の輪郭、そしてしっかりと歩き、ポール・マッカートニーとしての変わらぬ存在感を示した事への(観客の彼への)感嘆だったと思う。

次がジョージの作った「Something」を歌った。「僕もそうだがみんなジョージが大好きだった」と 述べながら。ポールとジョージの一緒の写真が山ほど出てきた。写真の数はジョンのそれよりジョージのそれが圧倒的に多かった。
最初の奥さんだったリンダと今の奥さんのナンシーさんに対する曲もあったが、確か二番目のヘザー・ミルズさんに対する曲はなかった。当然ですが。ナンシーさんは今月20日が誕生日だそうな。だから九州場所に行くかも.....と。ポールは相撲好きだが、彼女はどうかな。

観客サービスは徹底していた。「得意な英語」を日本の観客に分かってもらうために、両サイドのスクリーンの下に同通を付けた。まるでオペラの方式のように。
「もしかしたら今日はそうではないかも知れない」と思っていたが、少なくともアリーナの客は開始と同時に全員立ち上がり、最後まで。明らかに年齢層は高かったが、誰一人座ることなく。
私は知らなかったが、11日の大阪公演の最初に彼が歌った「Eight days a week」は、過去の演奏会では一回も歌われたことがないそうな。最後は「Golden Slumbers→Carry that weight→The end 」という展開。
だから私の印象では、2回のアンコールは事前に予定されていた、ということになる。何という体力。ただ「oldies」を聞かせただけのコンサートではなかったことがナイスだったな。
だから今朝一番に私は itunes store に行って、「NEW」というアルバムを1700円で買ってしまった。ははは。コンサートに行く前に読んだ記事ではこの日経の記事が一番良かったが、その中で子供の驚くべき能力として「“N.E.W.”はNumerous Epic Words(壮大な叙情詩)と理解した」という話しがあって、これがが面白かった。
彼の最後の言葉は、「また会いましょう。See You Next Time」でした。うーん、そうは思わないで行ったけど、ビートルズ曲の歌詞をもじって言えば「He will never die.
」という気もするな。何よりも彼はあと5回ある今回のジャパン・ツアーを全く問題なくこなすと思う。そしてまた10年後...........

2013年11月11日(月曜日)
(14:25)あれだけ騒いだのに、始まったら全く報道がなくなりましたね。今朝は新聞もないし。
何の話しかというと「三中全会」です。正式に書くと「中国共産党第18期中央委員会第三回全体会議」というらしい。9日から12日までだそうですが、始まる前はいっぱい日本の新聞に記事が載ったのに、今ネットを見てもなんもない。
まあ会議中ですから「情報が出てこない」ということはあるのでしょう。一般的には「国有企業の管理体制強化」「競争促進のため一部の大企業の分割」などが主要議題らしい。当然「治安の悪化」も議題でしょう。
しかし実は私は会議そのものにはあまり興味がない。だっていくらでも作文できるんでしょう。中国の政治なんて、何かあれば直ぐに方向転換する。天安門、山西省の事件で「これも難しくなった」などという記事を読むと、「その程度か」とも思う。
大体、中国の過去のスローガン、例えば「小康社会」とか「和諧社会」は今はどこにいってしまったのですかな。「小康」とは「ほっとできる」ということらしいが、今の中国に一番ないものでしょう。
「和諧」ね。「皆仲良くしよう」でしょうが、今の中国のどこにあるのか。指導部が掲げたスローガンはそれはそれで少しは価値があるのかも知れないが、一番大事なのは「一体何をするのか」だと思う。
「李克強は右(自由化)を向き、習近平は左(党による統制強化)を向いている」今の中国で、クリアカットな今後の方針を決めるのは、実は容易ではない。だから私は会議で「国営企業をどうする....」とか出ても、「ああ、そうですか」という感じかな。
重要なのは、その後実際に中小企業が育つのか、各業界で競争条件が担保されるのかを見たい。そこまで見ないと、今回のいわゆる「三中全会」が持つ会議としての意味合いは不確定ですね。多分情報がちっとも出てこないのは、会議自体ももめているんだと思う。

2013年11月11日(月曜日)
(12:25)昨日はフェースブックに教えてもらったな。もっと具体的には「お友達に」ですが。
11月になったからでしょう、あちこちでクリスマスのイリュミネーションが始まっている。その中で、六本木ヒルズ周りのけやき坂などの有名数カ所も11月月初から開始のようです。
で、日曜日にテレビ朝日で「いま世界は」(BS朝日毎週午後7時から 私の出演は月一回程度)があって、午後6時過ぎにテレ朝車庫前に着いたら綺麗な赤と金色のイリュミネーションが見えた。

しかし、近くに住む知り合い(お友達)の方から、「あれ? 日によって例年通りの青×シルバーだったり、赤×ゴールドだったりするのは何故!?」というコメントが。「へえ、そうなんだ」と私は思った。「週末だけ赤とか」というのが私の発想だった。
私はそのまま番組→食事で調べないでいたら、その方から「ググったら判明。10周年のセレブレーションカラーのレッド アンバー キャンドルは毎時、0分から10分だけだそうな。あとの50分間は今までどおりらしいです」と調査結果が。
帰りも午後11時直後だったので、再び綺麗な赤基調のイリュミネーションを見られた。ですから皆さん、ヒルズ近く、とくにかやき坂のイリュミネーションを見るなら、例年のブルーではなく「セレブレーションカラーのレッド アンバー キャンドル」がいいですよ。とっても。
時間を調整しながら、ブルーに変わる前に、出来たらブルーから赤になる瞬間から見るのが良いのではないでしょうか。でも赤は確か電気代が全く違うんだったと思った。だから一時間置きに10分だけ赤+ゴールド、アンバー(琥珀)色にしている、とも考えられる。
それにしても、六本木ヒルズも「10周年」ですか。ネットで調べたら「2003年4月25日 - 開業(街開き)」とあり、当時の小泉首相が「この東京の新たな街づくりに極めて刺激的、魅力的な六本木ヒルズが誕生したという、この誕生に立ち会うことができたのは幸運だと思います」と祝賀挨拶したそうな。
そういえばあの一体は、以前は細かな路地が多いあまりに細々した住宅街だった。だからヒルズの前のあの地区はあまり記憶にない。今となれば、六本木ヒルズがずっとあそこにあったように思う。
いずれにせよ、今年の六本木ヒルズの毎時最初の10分間のセレブレーションカラーは見物です。ぜひ一度......ということは、来年からあのブルーに戻ってしまう....?

2013年11月10日(日曜日)
(16:25)それにしても、アメリカの経済統計ってどうなっているんでしょうね。そして予想する側はなぜあれほどそろいもそろって予想を外すのか。とっても不思議です。
先週の金曜日。本来より一週間遅れの雇用統計。政府機関の一部閉鎖があった10月分ですから凹凸はあるだろうなと思ったのですが、予想が12万とか12万5000人の非農業部門就業者数が、実際には20万4000人と出た。
かつ8月分、9月分も合計6万人上方修正されて、「予想外に米雇用は強い」ということになった。自宅待機を要請されていても給与が後で出るので「就業者数に入る」というのは事前に分かっていた。それでも予想は低かったわけです。しかし出た数字は大きかった。
7.3%と出た10月の失業率に関しても、もっと大きな数字を予想した向きが多かったと思う。7.5%なんて予想もあったな。自宅待機組は家計調査では「失業者」のカウントだった。しかし出てみれば先月とほとんど変わらない7.3%。
今回の雇用統計だけではない。GDP統計も予想外だったし、各種統計が予想を違えることが多い。別にマーケットを弄んでいるわけではないのでしょうが、マーケットは確実に弄ばれている。
当局が持っている数字は包括的で、予測機関が持っている数字は選択的なことは確かですが、このコンピューター時代にあまりにも違う数字が予測と実体の間で出てくると、「そもそも予測に依存して良いのか」と思う。
というのは、「予測」がマーケットでは非常に重要な存在になっているからです。企業の業績もそのものの良さ悪さではなく、「予測との乖離」で相場が動く。だから「予測」が極めて重要な訳です。
実体と違うから「予測」だというのは分かるが、毎回毎回発表される数字が大きく違うと、「for what ?」となる。その分マーケットは右往左往。それがまたマーケットの流動性を高めている面もあるのでしょうが、「不正確な予想」は今後も続くんでしょうね。

2013年11月08日(金曜日)
(16:25)うーん、このFTの取り上げ方は針小棒大だと思うが、一般に「アベノミクス」と呼ばれている安倍政権の経済政策に対するマーケットの評価が、大きな曲がり角に立っていることはその通りだと思う。
それは日々のマーケットの動きや感度を見ていれば分かる。時間の経過が政策の新鮮度を奪うことは常ですが、その政策にマーケットが頼っているほど、政策からの驚きの剥落や実体の露呈は、マーケットの失望を誘いやすい。
今私が思っているのは、「アベノミクスというのは、結局金融政策の一本足打法か」という点です。財政出動は最初の段階で終わったし、それは良い。次の金融政策は効いている。しかしその後の産業政策は尻つぼみのような状況になっている。FTもそこを突いているわけです。
昨日は大きく落ちたし、金融相場が別に良いと思っているわけではない。しかし、一方のニューヨークの株式市場が定期的に史上最高値を更新するのに対して、日本の株はレンジにしっかり入ったまま。「この違いは何だろう」と時々思う。
そしてその一つの原因は、「三本の矢」というキャッチフレーズで始まった安倍政権の政策は、実際には「金融政策のみ」の状況になっていることが一つだと思う。そしてそれを私はとっても残念という以上に、長い目で見ると景気の腰折れの原因になると考える。企業が元気にならないと。
次に思うのは、日本の企業とアメリカの企業、その文化の差というようなものも思っています。ツイッターの初値にあのレベルがついたことには、私も正直ビックリした。需要供給で売り出し株数が少なかったからという見方もあるが、重要なのはあれだけあの会社の株を「買いたい」と思った人がいたことだ。
フェースブックが上場したのは一年半前。その時もいろいろあった。Nasdaqの取引が停止になったり。でもあのときも考えたが、「でもこういう会社が次々に出てくるのがアメリカ経済のダイナミズムだ」と思った。その事を思い出す。
日本でも新規上場はある。しかし世界で注目されるような上場はあまりない。それだけ日本の企業が静的なんだと思う。良かろうが悪かろうが次々と企業が出てくるというのがアメリカで、それが日米のマーケットの違いか。
としたら、それは政府の政策の違いと同時に、企業文化の違いでもあると思う。どちらが良い悪いではない。しかし、お金を動かしている人にとっては、「次々に大きな、世界的に知られた新顔」がマーケットに出てきた方が面白いに決まっている。
日本の「一本足打法」とよべる政策は、来年くらいにまた何かするかも知れない。しかしそれでまた終わりでは、もうマーケットは一年前の高い興味を示さないだろう。少なくとも二本の足(+産業政策)で立つようにし、かつ少しでも活発な企業文化を創り出さないといけないように思う。そうでないと、この日米格差は縮まらないのではないか、と思う。

2013年11月07日(木曜日)
(23:25)「世界的な低金利」も極まってきました。日米が「ゼロ金利」を続ける中で、今まで0.5%という比較的ビジブルナな金利水準を保っていたヨーロッパがそれを引き下げて、限りなくゼロに近い0.25%にした。刻みから言えば、「次はゼロ」。
ECBが7日に開いた理事会で予想外に決定・発表。ヨーロッパで見えてきた景気回復の兆し(スペインなど)よりは、ヨーロッパの物価水準が「危険なほど低い」という事態に対処した。つまりデフレ対策。無論、日本やアメリカの政策の有効性の有無を考えても、それ(利下げ)がどのくらい有効かは今後の問題だ。
ECBは主要金利の0.25%引き下げに加えて、緊急貸出金利(emergency lending facility)も0.25%引き下げて0.75%とした。準備預金に対する利子金利はゼロ。この措置を受けて、今のところヨーロッパの株は軒並み急騰。フランスでもドイツでも株価指数は1%以上の上昇となっている。
一方で、ヨーロッパの長期金利は低下。予想外の利下げだっただけにマーケットは大きく反応している。しかし引けにどうなるかは不明です。外国為替市場ではまずはユーロ安が誘発されたが、その後は円安が進行中。ドル・円は99円台の半ば。
この調子だと、ニューヨークの株価はまたまたの「史上最高値の更新」となる可能性がある。対して日本の株価はレンジを行ったり来たり。今日は100円以上下がった。これはまた書こうと思うのですが、日本は「三本の矢のアベノミクス」と名称は付いているが、実は「金融政策の一歩足打法」の様相だからだと思う。
個々の企業のガバナンスの改善、成長戦略の明確化も不足しているような気がする。それが日本市場の低迷に繋がっているように思う。

2013年11月07日(木曜日)
(11:25)ははは、昨日は面白かったな。就活イベントがあって、夕方から市ヶ谷へ。楽しみにして行ったのです。何と言っても何時も相手をしているおじさま達ではなく、20才をちょっと過ぎたくらいの方々。
私自身にとっては「就活」とはもうかなり懐かしい言葉ですが、最近は大変らしい。どういう顔をして集まってくるかがまず私の関心事でした。女性が3割くらいでしたかね。活発に質問する奴、黙って聞いているだけの学生。
まあでも猫被っているだけで、結構普段は明るい連中なんではないかな、という気がしました。一番前の列に座る人は、他の人とは違います。熱気が。それが面白い。いろいろ話して面白かったが、これだけは言い忘れた。
「良かったね、今日の講師は全員髪の毛がふさふさで.....」。何のことはない。良かったと思うレベル、幸せのレベルはちょっと低めの方が人生うまく行く。「あまりバーを高くするな」と言いたかっただけです。が言い忘れた。
大橋さんとは初めて会いましたが、会ったときに一瞬「内山理名さんか」と思いました。リンク先のサイトに掲載されている写真は、かなり実物と違う。この写真は少し上から映している。
私が学生達に強調したのは、「就職雑誌を手に取るより、本を読んだり映画を観たら」ということです。きっと話題が豊富になるし、自分の頭で考えるようになれる。
というわけで、今日は本を三冊ほど紹介しましょう。たまたま全て新潮新書です。最近新幹線の中などで読んだ。第一は、『「いいね!」が社会を破壊する』です。著者が潰れたコダックにいたこともあるのでしょうが、まあ暗い本ですし、人間社会の複雑系を捨象して一直線に結論に到達しようとしている。
人間社会の複雑性は例えば「経団連が賃上げを提唱」という一点にも現れていて、今までのトレンドだけで人間社会の先行きを頭の中だけで考えて「こんな悲惨な事になる」と考えるのは間違っていると思っていて、この本はその前提で読むと良いと思います。
次に「カネ遣いという教養」という本は、「何を訴えたいのか不明」という印象がする本ですが、「お金を急に持った人がどう行動するのか」を見る上では面白いかも知れない。
三番目の「日本人には二種類いる」はこの三冊の中では一番面白かった。この本の主張に賛同できることもあるが、何よりも経済を見ている人間としては「戦後の日本のデータが豊富」ということ。初任給がどういう上昇カーブを描いたのかとか、いろいろ数字が揃っている。

2013年11月06日(水曜日)
(16:25)最近サンケイ新聞がITに関していくつか面白いニュースを流している。誰か結構詳しい人出も加わったのかな。
一つは『PCロックし「解除には金が必要」 身代金型ウイルスご用心 5カ月で160件』という新手のウイルス情報。まだ遭遇したことはないが、ちょっと注意したに越したことはないと思う。身代金型ウイルスね。
次に「コピー複合機、情報丸見えの恐れ、大手2社が注意喚起 政府、調査へ」は面白かった。以前ほどコピーはしなくなりましたが、まだ使われている方は多いのではないでしょうか。
これは言われなくても、「その危険性はあるな」と思う。資料を数多く作る必要のあるところは大変ですね。デジタルは皆繋がりますから、何事においても大変です。

2013年11月04日(月曜日)
(16:25)天安門で起きた車両の突入・爆発・炎上事件に関しては、10月の末以来私はずっと「家族としての復讐」との見方でした。切っ掛けは「車の中で死亡した3人のうち一人は70才の女性だった」という報道を目にしたからですが、ここに来て「一家の復讐説」を裏付ける報道が次々に出てきている。
一つはRadio Free Asiaの「Tiananmen Crash May Have Been a 'Revenge Attack'」という記事であり、もう一つは香港の新聞の「突入の女性は妊娠 香港紙、親族射殺が動機か」というものです。対して中国政府は、『独立派組織「東トルキスタン・イスラム運動(ETIM)」が関与していると主張』している。
しかし中国はその主張を裏付ける根拠を全く開示していない。ETIMは米政府がそうだと認定した「国際テロ組織」ですが、中国が根拠を示さない以上、また第三者による認定が下されない以上、私はこの事件は「家族としての復讐」との説を採り続けようと思っています。
なぜなら、「ETIMの犯行だ」と主張することには、中国政府(共産党)には都合が良すぎる背景があるからです。
と論理は続く。しかし一家の復讐説を採れば、中国の同地区に対する今までの締め付け、仮借なき「弾圧のブーメラン」という視点が浮かぶ。
大体において、組織が引き起こす「自爆テロ」というのは犯人は単独です。なぜなら、事件を遂行する戦士は貴重だからです。それが今回は一挙に3人もの人がなくなっている。テロ組織はこんなことはしない。9.11のターゲットは多数だったからあれだけの人数が必要だった。しかし今回のターゲットは一つです。組織がやったのなら、一人の戦士を選任していたはずです。
次に「70才の女性」による自爆ということはあまり聞かない。それまで生きてきたと言うことは、そもそもその女性は過激な思想に染まっていないということを意味すると思う。思想ではなく、その女性を駆り立てた何かがあったはずです。
その女性の息子がいたという報道が事実だとすると、それも極めて希有なことです。普通は「先に行く私を許して下さい」と息子の方が犯行を起こし、母は悲嘆にくれるというパターン。かつその結婚相手の女性(妊娠中とも)も一緒だったとされる。
この3人をバンドするものがあるとしたら、それは「組織の論理」などではありえない。きっと「一家として中国政府を許せない事情」があるはずです。私はそう考える。
ということは、今回の事件は、いかに中国が新疆ウイグル自治区で苛烈な治政をしているかの証拠であり、それを緩めない限りまた「一家の復讐」が起きることを意味していると思う。
今の中国の新疆ウイグル自治区、さらにチベットに対する圧政は間違っている、ということだ。

2013年11月03日(日曜日)
(22:25)予想が完全に当たると言うことはない。でも自分でもビックリ。結構当たっていたな。私が金曜日に立てた予想は以下の通りでした。
土曜日の試合(第六戦)はマー君が出てきても打たれて5−2で巨人が勝つ。巨人打線が意地を示す。しかし日曜日の試合(第七戦)では楽天が踏ん張って1点差くらいで終盤を迎え、そこで抑えにマー君が登場。巨人打線を抑えて、楽天優勝........
土曜日の巨人の勝利は「4−2」だったということと、日曜日の試合の「終盤1点差」。この二つは違った。しかし大枠はあっていたように思う。
いろいろな思いがある。誰がだめだったとか、良かったとか。しかし楽天の選手は最後まで思いが一つだった。投手も打者も。対して、巨人の選手がチームとしてバットをしっかり振れていたのは、難敵・田中相手の第六戦しかなかったように思う。
全体的に言うと、予想が当たったという以上に、2013年という年の日本シリーズとしては、一番良い終わり方だったのではないでしょうか。ファン心理は別にして。テレビを見ていて、一番私の心に響いた、残像を残した言葉は「東北」でした。そう今の日本人の誰にとっても心に重い単語。
その「東北」を冠した創設10年もたたないチームには、心のどこかに「応援したい気持ち」があった。かつ重要な事は、他チームの気遣いではない「実力で日本一になる力を蓄えた」と言うことだと思う。見ていて思ったのは、
「勝つという意思」
「勝ちたいという気持ち」
がどうみても楽天の方にあったと言うことです。この2チームを長期間戦わせたら多分ジャイアンツの方が勝ち越したんだと思う。しかし、短期の戦いは別のファクターがある。
結局ジャイアンツの選手達は今年は、「楽天劇場の引き立て役」になってしまったということです。でも例え田中が大リーグに行ってしまっても、来年の日本のプロ野球は凄く面白くなるような気がする。
来年各チームがどのようなチーム作りをしてくるのか楽しみ。

2013年11月02日(土曜日)
(16:25)大阪でちらっと見たネットに気になるニュースが。豆腐店、続々廃業「365日働いても利益ない」と見出しが。
ちょっとショッキングです。「豆腐業者が倒産や廃業に追い込まれるケースが増えている。大豆価格の高騰に加え、スーパーから値下げを求められるなどして経営が悪化し、豆腐業者はこの10年間に全国で約5000軒が廃業。今年8月に破産申請をした都内の業者は「365日丸々働いても利益が出なかった」と苦しい日々を打ち明けた。」と。具体的に悲しい話しも。
1957年創業の豆腐業者「仙台屋本店」(東京都三鷹市、8月に自己破産申請)の及川英一さん(37)は、大学を卒業した3年後から、祖父が開業した同店で父親とともに働いてきた。従業員は最大20人で1日2000丁を製造してスーパーに卸すほか、10年前には杉並区のJR阿佐ヶ谷駅近くなどに三つの直売店を開設。豆腐を加工した食材なども手がけ、好調な時は年4億円を売り上げた。「うなぎ」の次が豆腐では悲しすぎる。どちらも好きな食べ物で、「なくては生きていけない」といっては過言ですが、悲しいですね。この記事には最後に資料も載っている。それは以下の通り。だが、5年前から輸入大豆の価格が高騰。豆腐の一部を別の業者から安く仕入れて費用を下げるなどしたが、3年前には3店舗とも閉鎖。デフレの影響でスーパーからも値下げの要請を受けたが、経営が苦しいため、むしろ値上げしてほしいと相談すると、取引が打ち切られた。
スーパーの中には協賛金の名目で売り上げの7%の「上納」を求めたり、売れ残った分は買い上げてくれずに丸ごと負担させたりするところもあった。今年になって、外国産大豆はさらに値上がりし、1〜9月末の平均価格は1キロ当たり84・2円で、この10年で最高値となった。国産大豆もそれに合わせて値上がりし、経営を圧迫した。
厚生労働省の集計では、全国の豆腐業者は12年度は9059軒となり、03年度(1万4016軒)より4957軒減った。全国豆腐連合会(東京)は、来年4月からの消費増税分を価格に転嫁できるよう流通業界に理解を求めている。同会は「年間500軒のペースで業者が廃業している。食の安全、安心を守るためにぎりぎりの経営を続けていることを知ってもらいたい」と話している。

2013年11月01日(金曜日)
(09:25)私はこう思うんですよ。「今年最高の日本シリーズの終わり方」。
土曜日の試合(第六戦)はマー君が出てきても打たれて5−2で巨人が勝つ。巨人打線が意地を示す。しかし日曜日の試合(第七戦)では楽天が踏ん張って1点差くらいで終盤を迎え、そこで抑えにマー君が登場。巨人打線を抑えて、楽天優勝........
ははは、どうですか。一試合引き分けて、第八戦があるというのもありかな。最高でしょ。大方の予想通りこのままマー君が第六戦で勝ってしまったら面白くない。加えてこのままマー君が勝ち続けてアメリカの野球に行くのは癪じゃないですか。だってそのマー君がアメリカであまり通用しなかったら(とけ込みの問題や英語の問題もあって)、「日本の野球のレベルは....」という事になる。そうなったら”癪”。
以上は私の勝手な”望ましい予定”で、そのままになるとは限らない。しかし5戦戦って24安打の巨人ですからね。まだヒットもろくに打てていない選手が数人。楽天には「この選手は活躍していない」という印象がする選手がいなくなったのに比べて大違いです。だから、第六戦で決まる可能性は8割ほどある。
それにしても、スポーツ全体で言えるんでしょうが、結局は
「勝つという意思」
「勝ちたいという気持ち」
なんでしょうね。同じプロの土俵ですから。ワールド・シリーズを勝ったファレル監督が「なぜ勝てたのか」と監督記者会見で聞かれて、「will to win」と答えていた。昨日もドームの試合を見ていて、「楽天の選手には勝ちたい気持ちがもろ出ている」と思いました。
2011年のシーズン開始前に東北の人たちに誓った「勝ちます、日本一になります」という約束の未達成。遅れている。リーグのお荷物と言われた創立以来の過去。全国ベースでは名前も知られていな選手の集団。彼等は全国区になりたがっている。
マー君だけは例外ですが。正直、私も「銀次」なんてつい最近まで詳しくは知らなかった。スポーツ・ニュースを見て「変な名前の選手がいる」くらいしか。彼等は見ていて、「勝ちたいんだな」と分かる。岡島もいい。嶋のあの泣きそうな顔。
ボストンにも「勝ちたい理由」があった。去年の屈辱的な地区最下位。そしてボストン・マラソンでの爆破テロ。プライドの高いボストンの選手には「今年は」という気持ちがあったはず。今年も事前予想は低かった。アメリカの新聞記事を読んでいると、「前年のビリからワールド・シリーズに勝った」チームは過去1度しかなかったそうな。
巨人の選手に「勝つ意思」への誘因があるとしたら「連覇」なんでしょう。監督がそう言っている。それは素晴らしい。しかし「東北の人たちへの感謝」に比べれば、やはり弱い。無論巨人には力が潜在的にはあるから、それは発揮されるかも知れないし、第六戦はぜひ頑張って欲しい。しかしエンディングは「楽天優勝」がいいな。個人的には。
メリットは多い。「日本の球団層が厚くなる」ことが一つ。広島の頑張りもそう。そういう意味では、DeNAは来年はもうちょっと頑張る必要がある。芽はあると思う。パリーグはいつの年でも接近していておもしろ。アメリカが終わっちゃったから、土曜日は楽しみだな。どうなるか。
ダルビッシュが実感を込めて言っていたな。「(楽天は)強くなりましたね」「それにしても土曜日の試合は面白くなりました。マサヒロが無傷で優勝に行くか、ジャイアンツが彼を打つか....」と。その通り。