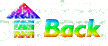2015年01月31日(土曜日)
(03:55)気になるニュースが多い夜なので、夜中にちょっと起き出してネットを見ていたら、「あ、きたな」と思いました。ウォール・ストリート・ジャーナルの一面を見ると、ドイツの10年債の利回りが日本のそれを下回っている。いつか来ると思っていたが、案外早かった。欧州の方にデフレ懸念が強まった証拠です。
下の表の左が私が見たその時点での各国の10年債利回りです。ドイツのそれは0.269%と日本の0.282%を下回っている。実は私の記憶を辿っても、過去にあったのか、なかったのか、という話。あったにしても随分以前です。あとで調べます。
「日本時間8日夜段階」と書いてあるのは、私が今年1月8日の夜に同じような関心を持ってレートを採取したときのもので、要するに一ヶ月もしない間に世界の長期金利はこんなに下がった....と確認するために表示している。
30日のニューヨーク午後 日本時間8日夜段階そうなる理由は十分にある。EU統計局は30日、1月のユーロ圏の消費者物価指数(速報値)が前年同月に比べて0.6%下落したと発表した。マイナス幅は昨年12月に比べて0.4ポイント拡大。2009年7月に記録した単一通貨ユーロ創設以降で最大の下落率に並んだ。
U.S. 10yr 1.666% 1.996%
German 10yr 0.269% 0.493%
Italy 10yr 1.580% 1.897%
Spain 10yr 1.450% 1.705%
U.K. 10yr 1.335% 1.634%
Japan 10yr 0.282% 0.289%
ユーロ圏の消費者物価の下落は2カ月連続。1月はエネルギー分野が前年同月に比べて8.9%落ち込みとなった。これは大きい。エネルギーを除いた指数でも0.4%の上昇にとどまり、上昇幅は前月から0.2ポイント縮小した。EUのインフレ率目標は2%弱です。
これに先立ち、ドイツ連邦統計局は29日に同国の1月の消費者物価(EU基準)が前年同月に比べて0.5%下落したと発表していた。09年10月以来のマイナスだった。EU統計局によると、昨年12月時点でユーロ圏19カ国(1月にユーロを導入したリトアニアを含む)のうち、すでに12カ国で消費者物価が下落していたが、「1月はさらに範囲が広がった可能性が高い」という。
日経は、「1999年のユーロ創設以降、ユーロ圏では09年6月から5カ月にわたって消費者物価が初めてマイナスに落ち込んだ。原油価格の動向次第の面もあるが、景気低迷の長期化や雇用回復の遅れで、今回の物価下落局面は長期化し、本格的なデフレに陥るリスクもある」と書いている。
世界では利下げの動きも続いている。びっくりしたのは、今週のシンガポールの金融緩和。その前はカナダ、今日はロシア。同国中銀は30日、主要政策金利を17%から15%に引き下げ。あの危機の中なので予想外。市場は据え置きを予想していた。
当たり前だが2%引き下げてもロシアの金利は世界の中で突出して高い。ロシア中銀は昨年、為替市場の混乱やインフレの進行を受けて政策金利を計11.5%ポイント引き上げていた。昨年12月中旬には緊急理事会を開催、政策金利を6.5%ポイント引き上げ17%としていた。ルーブル安があっても、ロシアのインフレ率が落ち着くと考えたのか。
デンマーク中銀も果敢だ。同行は先週19日、主要政策金利である譲渡性預金(CD)金利を0.15%ポイント引き下げ、マイナス0.20%にした。スイス中銀によるフラン上限撤廃に伴い進行する通貨高を抑える狙い。
こうした中での決定を迫られるFOMC。30日に米商務省は2014年10〜12月期の実質国内総生産(GDP、速報値)が、年率換算で前期比2.6%増えたと発表。これは予想の「3.2%程度のアップ」を下回る。消費は好調だった。何が悪かったと言えば、「輸出の鈍化や政府支出の落ち込み」。米成長率は7〜9月期の5.0%から減速した。
米企業決算を見ても、「ドル高」の影響は大きい。ドル高は「米金利先行き高」を反映している。ドル高はまたFRBがもっとも気にし始めたインフレ率を押し下げる。難しいですね、FRBの利上げ判断は。だから私は後ずれすると考えているのですが。

2015年01月30日(金曜日)
(14:55)朝の番組が終わって局から送ってもらう途中。雪が激しく降っていたので、当然「雪の日の東京の車」「スタッドレスタイヤ」の話になった。
そのハイヤー会社の車は11月の末には全部タイヤをスタッドレスに替えるのだそうです。3年ほど前から。その前は変更はしていなかったらしい。だって一本クラウンクラスの車だとスタッドレスタイヤは5万円以上するというのです。4本替えて20万超。おまけにそのタイヤを「どうやって保存するのか」が大きな問題だったらしい。大きくて重い。
ところが3年ほど前から「中古のスタッドレスタイヤを買い取る業者が出現した」というのです。買い取ってくれるということは、タイヤを翌年に残すスペースがいらないし、キャッシュも戻ってくる。そこでこのハイヤー会社(タクシー部門もある)は、「冬はハイヤー全部についてスタッドレスを履かせる」ということで統一したらしい。
例えば5万円で買ったスタッドレスタイヤを、業者がどのくらいの価格で買ってくれるのか知りません。しかしハイヤー会社には二重に嬉しい。「多分、個人向けに北で売っているではないか」というのです。
東京のハイヤー会社のスタッドレスタイヤは、11月末に装着して、使って3ヶ月半。まだ使えるでしょう。だとしたら売れる。実際に自宅で車庫がある人は別ですが、マンションなどの狭い車庫にスタッドレスを4本キープ出来る人はいない。私も同じ。その事情はハイヤー会社でも同じだというのです。だから都内の大部分のカーオーナーは、「降ったらもう乗らない」が原則です。しかしハイヤー会社はそうはいかない。
中古のスタッドレス。多分それは通常の「東南アジアルート」では売れない。だって日本より南のアジアの国では雪は降りませんから。だから「行ってロシアかな」とその運転手さん。大部分は国内 ?
運転手さんはもっと面白い事をおっしゃる。それは、最近はドバイからスタッドレスタイヤを買う個人が増えているらしい、と。ドバイ、スタッドレス。ちっとも繋がりませんよね。しかし通販で買うと安いと運転手さんはおっしゃる。
運転手さんと別れて「そんなことがあるだろうか」と思って、「ドバイ スタッドレス」で検索したら、三番目に面白い情報があった。このサイトです。「今話題の.....」とか書いてある。「あるんだ」とビックリ。ジーテックというらしい。
サイトには「スタッドレスタイヤとしての実績はまだまだ少ないブランドではありますが国産スタッドレスタイヤより圧倒的に低価格なことから選ばれ始めています。」と。なかなか素直じゃないですか。
でもなぜドバイ.....と。疑問が解けたわけではない。でも今朝は朝から面白い話で盛り上がった。あととっても面白かった記事は、匿名でも特定できちゃうと。まあそうなんでしょうね。

2015年01月29日(木曜日)
(10:55)久しぶりに絵画館前の通りを通ったのです。そしたら、大量の枝が切り落とされている場所があった。青山通りから見て右側の奥です。ああ、剪定しているだと思って上を見たら、全く違う。


ところで、今しがたちょっと中央日報の日本語サイトに久しぶりに寄ったら、見出しに全く知らない単語が出てきてビックリし。「火病(鬱火病)」というのです。
wikiを調べたら、「朝鮮民族特有の精神疾患」と書いてあって、さらに「火病または鬱火病は、怒りの抑制を繰り返すことで、ストレス性障害を起こす精神疾患を指す。ヒステリーと類似した症状を発症する」と書いてあった。
この記事の最後にも、「火病は「くやしいことにあったり恨めしいことを体験して、積もった怒りを抑えることができずに表れる身体や精神のさまざまな苦痛を称する言葉だ」と書いてある。
韓国のサラリーマンは大変なんだ、と思いました。だって「90%が悩む」とはいくらなんでも酷いでしょう。ほぼ全員ということ。原因については『1位は「上司や同僚と
この新聞を見た時のトップは「朴大統領の支持率29.7%…就任後最低」と。韓国は実は国内の方が大変だと言うことです。

2015年01月29日(木曜日)
(05:55)発表されたFOMC声明を読んで、「この声明の政策的意味合いは何か」と考えたとき、やはり「利上げは少し後ずれした」と考えるのが自然だと思う。
なぜそう考えるかというと、前回は3人もいた声明に対する反対者(その中には「とっとと利上げせい」という人も含まれる)がゼロになったこと。「反対者ゼロ」は最近の声明では珍しい。最後の1パラです。このパラが短くなっている。
前回(昨年12月のFOMC)どうだったかというと、「Voting against the action were Richard W. Fisher, who believed that, while the Committee should be patient in beginning to normalize monetary policy, improvement in the U.S. economic performance since October has moved forward, further than the majority of the Committee envisions, the date when it will likely be appropriate to increase the federal funds rate; Narayana Kocherlakota, who believed that the Committee's decision, in the context of ongoing low inflation and falling market-based measures of longer-term inflation expectations, created undue downside risk to the credibility of the 2 percent inflation target; and Charles I. Plosser, who believed that the statement should not stress the importance of the passage of time as a key element of its forward guidance and, given the improvement in economic conditions, should not emphasize the consistency of the current forward guidance with previous statements.」となっていた。長い。
なぜ反対者がゼロになったかというと、理由は簡単です。この反対者3人は去年末までのメンバー交代で全員がFOMC委員ではなくなったからです。3人とも今回のメンバーに入っていない。そして入ってきた人もイエレンの方針に反対しなかった、ということです。
とっとと利上げしろと言ってたリチャード・フィッシャーのようなメンバーの交代は、FOMCの雰囲気を変える筈です。「忍耐できる」の忍耐の度合いを高めると考えるのが自然です。むろん6月まではない。秋かな。
「for a considerable time」が声明から落ちたことをニュースのように扱っているメディアもありますが、それは声明が全く読めていないことを白状しているに等しい。そもそも12月の声明を読めていれば、そんな判断は出来ない筈です。前回の声明は以下のように述べていた。「Based on its current assessment, the Committee judges that it can be patient in beginning to normalize the stance of monetary policy. The Committee sees this guidance as consistent with its previous statement that it likely will be appropriate to maintain the 0 to 1/4 percent target range for the federal funds rate for a considerable time following the end of its asset purchase program in October, especially if projected inflation continues to run below the Committee's 2 percent longer-run goal, and provided that longer-term inflation expectations remain well anchored」。
つまり新しく入れた文言である「can be patient in beginning to normalize the stance of monetary policy」を説明するために、それ以下の 「for a considerable time」が入った文章を入れているわけで、要するに「説明文」。説明文を2回も入れるはずがない。(http://arfaetha.jp/ycaster/diary/14/12/18.htmlを参照)
まあでも景気判断は上げたんでしょうね。前回は労働市場だけに使っていた「solid」を今回は景気全般にまで使った。景気全般については今までは「moderate」です。「solid」は明らかに判断を上げている。
それでも物価上昇率がちっとも2%に接近しない。そこは日銀と同じように、「もうそろそろ」とFOMCは言っている。。FOMCも気にはしている。第一パラの最後の方に「 Market-based measures of inflation compensation have declined substantially in recent months」という文章がある。難しい表現をしているが、要するに「債券利回りは大幅に低下した」ということを言っているのです。28日も下がって指標10年債は1.718%。もっともドイツのそれは0.315%で限りなく日本(0.288%)に接近。
しかしFOMCは二度にわたって「低インフレは一時的」と言っている。その直ぐ後に「survey-based measures of longer-term inflation expectations have remained stable.」と述べているし、第二パラでも「the Committee expects inflation to rise gradually toward 2 percent over the medium term as the labor market improves further and the transitory effects of lower energy prices and other factors dissipate」と述べている。うーん、本当だろうか。
Release Date: January 28, 2015For immediate release
Information received since the Federal Open Market Committee met in December suggests that economic activity has been expanding at a solid pace. Labor market conditions have improved further, with strong job gains and a lower unemployment rate. On balance, a range of labor market indicators suggests that underutilization of labor resources continues to diminish. Household spending is rising moderately; recent declines in energy prices have boosted household purchasing power. Business fixed investment is advancing, while the recovery in the housing sector remains slow. Inflation has declined further below the Committee’s longer-run objective, largely reflecting declines in energy prices. Market-based measures of inflation compensation have declined substantially in recent months; survey-based measures of longer-term inflation expectations have remained stable.
Consistent with its statutory mandate, the Committee seeks to foster maximum employment and price stability. The Committee expects that, with appropriate policy accommodation, economic activity will expand at a moderate pace, with labor market indicators continuing to move toward levels the Committee judges consistent with its dual mandate. The Committee continues to see the risks to the outlook for economic activity and the labor market as nearly balanced. Inflation is anticipated to decline further in the near term, but the Committee expects inflation to rise gradually toward 2 percent over the medium term as the labor market improves further and the transitory effects of lower energy prices and other factors dissipate. The Committee continues to monitor inflation developments closely.
To support continued progress toward maximum employment and price stability, the Committee today reaffirmed its view that the current 0 to 1/4 percent target range for the federal funds rate remains appropriate. In determining how long to maintain this target range, the Committee will assess progress--both realized and expected--toward its objectives of maximum employment and 2 percent inflation. This assessment will take into account a wide range of information, including measures of labor market conditions, indicators of inflation pressures and inflation expectations, and readings on financial and international developments. Based on its current assessment, the Committee judges that it can be patient in beginning to normalize the stance of monetary policy. However, if incoming information indicates faster progress toward the Committee’s employment and inflation objectives than the Committee now expects, then increases in the target range for the federal funds rate are likely to occur sooner than currently anticipated. Conversely, if progress proves slower than expected, then increases in the target range are likely to occur later than currently anticipated.
The Committee is maintaining its existing policy of reinvesting principal payments from its holdings of agency debt and agency mortgage-backed securities in agency mortgage-backed securities and of rolling over maturing Treasury securities at auction. This policy, by keeping the Committee’s holdings of longer-term securities at sizable levels, should help maintain accommodative financial conditions.
When the Committee decides to begin to remove policy accommodation, it will take a balanced approach consistent with its longer-run goals of maximum employment and inflation of 2 percent. The Committee currently anticipates that, even after employment and inflation are near mandate-consistent levels, economic conditions may, for some time, warrant keeping the target federal funds rate below levels the Committee views as normal in the longer run.
Voting for the FOMC monetary policy action were: Janet L. Yellen, Chair; William C. Dudley, Vice Chairman; Lael Brainard; Charles L. Evans; Stanley Fischer; Jeffrey M. Lacker; Dennis P. Lockhart; Jerome H. Powell; Daniel K. Tarullo; and John C. Williams.

2015年01月27日(火曜日)
(17:55)新幹線の中で「ニューヨークの嵐」をスライド写真で見ていたら凄まじいですね。さすがニューヨーク・タイムズ。
ニューヨーク州全域で地下鉄は午後11時から運休、街には人影が少なく、商店の食料品は品切れ状態。一瞬3.11の後の東京のコンビニの棚を思い出しました。
ニューヨークに4年いましたが、こんな大嵐は経験しなかったな。天候が激しい場所ではあるのですが。30リンカーン・プラズというのが居た場所で、リンカーン・センターの直ぐ近くだったが、あの辺も当時とは随分と変わった。
うーん、写真を見ていたら久しぶりにニューヨークにも行きたくなってきた.....。

2015年01月27日(火曜日)
(11:55)「訪日外国人の来日は、明らかに加速している」「恐らく今年は、訪日外国人の数でトップに立つのは、台湾でも韓国でもなく、中国本土の人達だろう」と思いました。

むろん彼等が目指すのは心斎橋筋です。凄い人で、でも歩き方や着ているものから「観光客の方々だな」と直ぐに分かる。ちょっとどこかしらくすんでいるのです。着ているものが。当然飛び交っていたのは中国語です。韓国の言葉は聞かなかった。
今朝は大阪城の周りを回ったのですが、このお城の公式の駐車場は城の南の方にあって「バス駐車場」と「乗用車駐車場」に別れている。乗用車駐車場の方はがらがらですが、バス駐車城は入りきれないくらいバスが押し寄せている。駐車場は十分に大きいと思うのですが。
そこから降りた人達は、旗を持つ先導者を先頭に、概ね梅林の方向に向かうのです。しかし梅林までは行かない。途中で城の中を目指す。その行列の長いこと、切れないこと。言葉から判断すると中国語です。
むろん季節的な要因もあるのかもしれません。徐々に旧正月が接近していて、総じて中国の人達の旅予定が混む時期。ははは、「おお、一人23万円」と冗談半分に思いながら、「これは結構凄い」と思って見ていました。
むろん嘆く声も聞こえる。行きつけの和食の店の大将は、『うちはそういう店じゃないのに、突然来て「二人ですが」とか言う』『断ると、明日はどうか』という。それもダメというと、『明後日、明明後日はと詰めてくる』。

まあでも、彼等が来るおかげで潤っている店や業種は日本には一杯ある。来るなと言うわけにも行かない。言っていれば「New Reality」です。うまく付き合っていくしかない。
それにしても今日は既に27日ですか。一月はいろいろ用事があって忙しい。講演も多いし、待ち構えている原稿も多い。やっとその1月が終わりですが、ということは12分の1が終わったと。ははは。えらいこっちゃ。

2015年01月26日(月曜日)
(23:55)ギリシャはまたまたEUにとっての「頭の痛い問題」になった、ということでしょう。急進左派連合(Syriza、ティプラス 党首)が300議席中149議席獲得となれば、「(彼等の)明確な勝利」と言える。
むろん得票率一位の政党への50議席のプレゼントを入れての149議席ですが、それでも得票率36.5%で、新民主主義党(ND)の27.7%を大きく上回る。NDが獲得した議席は76議席に過ぎない。
過半数(151議席)に届かなかった急進左派連合は月曜日26日に、13議席を獲得した中道右派政党「独立ギリシャ人」と連立交渉し、協力を取り付けたという。同党は緊縮策に反対してNDから離党した議員らで構成する。
急進左派は「最低賃金の引き上げ」や「貧困層支援」などを訴えているが、問題はその資金をどうやって捻出するか。それらの政策はEUや国際通貨基金(IMF)が対ギリシャ資金支援の条件に抵触する。さらには「債務の一部免除」を求めているが、今のEUや支援機関の姿勢では交渉難航が予想される。それをどうするか、と続く。
一つ明らかなのは、欧州における「反緊縮派」の勢いが高まると予想される点。欧州では各国で反緊縮派と言われる政党が昨年の選挙で大きく躍進した。フランスの国民戦線やスペインの Podemos と呼ばれる政党は「予算削減」「失業率の急上昇」「各種社会保障制度の引き下げ」 を強く非難して、緊縮政策の見直しを要求してきた。
実はEUの金融政策は、一足先に一種の「反緊縮」の動きとなっている。実質的に無制限のQEを始めてしまったからだ。ドイツの反対を押し切っての欧州金融政策の「超緩和への舵切り」。
今世界のマーケットを見たら、ギリシャの選挙結果を無視するように欧州の株はドイツ株を中心に上がっているし、ユーロも対円で130円14銭から133円台前半に反発している。織り込んでいたということでしょう。典型的な「sell the rumour buy the fact」
しかしそれで欧州の問題はなかったのだ、とは言えない。常に欧州情勢は「不可解」ですが、今後もナローパスを歩むことになる。

2015年01月25日(日曜日)
(23:55)少し前に買っていた「イスラム国の正体」を読み始めました。「いったいどんな連中なんだろう」と思って。だって常軌を逸しているじゃないですか。
知りたいことは一杯ある。誰がファンディングしているのか、なぜ世界中の一部の若者を吸い付けるのか。「イスラム国はなぜ今のように勢力を持つに至ったのか」については、既にいろいろな分析がある。先日BS1の「世界のドキュメンタリー」でも、この問題を扱った番組があった。面白かった。
はっきりしているのは、イラクの混乱とシリアの混乱が放置されてきた、ということです。だから権力の空白が生まれ、妙な国が出来る余地が生まれた。特にマリキ政権のスンニ派敵視政策が流れを作ってしまった気がする。結局彼(シーア派)は宗派意識から抜けきれなかった。
シリアはやはり化学兵器を使った時、具体的にはオバマ大統領のあの時の不決断が未だに響いている気がする。曖昧にして形がつかなかった。それ故に特に北部では権力の空白が生まれた。
サダム・フセインのような体制が良いわけではない。しかしあれはあれで権力の空白を生まなかったし、一種の安定政権ではあった。非人道的ではあったが。しかしその後の政権が民主的で人道的だったかと言えばそうではない。これが難しい。
オバマ大統領は今日からインドに行っているようですが、「ふっきれた」のは良いが、きちんとした判断が下せるのかやや不安が残る。はっきりしているのは、テロ国家は可及的速やかに霧散してもらわねばならないということです。

2015年01月23日(金曜日)
(08:55)「危機拡大の芽を孕む金融政策=欧州版QE」がECBの今回の措置だと思うのですが、それ以前に今朝は各国の債券利回り表を見て、「あらら」と思いました。「ドイツの10年債の利回りが日本のそれを下回りそうだ.....」と。
むろん知ってますよ。昨日の日本の債券市場の”異変”は。黒田さんの「追加緩和なし」示唆で「高所恐怖症」もあって、大きく売られた。だから今日からまた買われている。しかしドイツと日本の債券利回り接近は、考えれば当然で今後も続き、場合によってはクロスする可能性もあると思います。
それにしてもこの表を見ると、世界の金利はたった10日間で日本を除き大きく下げた。これを全部「原油のせい」とするのはちょっと無理でしょう。やはり世界経済における物価上昇圧力が低下している、というのが根源的背景だと思う。
22日引け 12日引け
U.S. 10yr 1.877% 1.909%
German 10yr 0.398% 0.482%
Italy 10yr 1.550% 1.805%
Spain 10yr 1.409% 1.631%
U.K. 10yr 1.518% 1.578%
Japan 10yr 0.316% 0.278%
ECBが打ち出した「欧州版QE」の中味については、かなり強力です。事前のマーケットの予想は「月間500億ドルの購入を一年間続ける」というもの。しかし発表されたのは「月間600億ドルの国債など購入を少なくとも2016年9月まで続け、その後も物価目標(2%弱)が達成に向けた明確なシグナルが出るまで購入をやる」というもの。これは強い。
実施は今年の3月からで、ECBが既にギリシャ国債を大量に保有していることから、現在はジャンク(投資不適格債)に格付けされている一部同国国債を購入するかどうかの決定は先送りされた。
しかし一部でマイナスの利回りが付いているドイツ国債まで購入対象である、としている。これはそもそも保守的なドイツ連銀をモデルに作られ、今でもフランクフルトに本部を置くECBとしては実に画期的な措置だと言える。世界中の金融市場がその政策に驚いたのは当然だった。
しかし 少し先のことを考えてみる。もしこのECBの思い切った金融政策でもEUのインフレ率が高まらずに欧州がデフレに陥り、景気も今の成長率ゼロ近傍の状態を続けたらどうなるのかだ。
当然ながらECBには「もっとやれ」という圧力がかかるが、「金融での経済救済」という考え方そのものに反対のドイツは、これまで以上にQEの政策深化に慎重になるだろう。一方の南欧の国々は「もっと」と要求する。そういう図式が描ける。
金融市場の見立ては別れている。「今回の決定は規模も大きく効果的だ」という見方もある。しかし「フランスやイタリアなどの労働市場改革や、欧州全体での新産業の育成、規制緩和などが伴わなければ効果は限定的」という見方もあり、筆者はこの見方に賛成だ。
同じ金融政策実施の日本でも、「第三の矢」に有効な政策が出てこないなかでアベノミクスには脆弱性が指摘され始めている。「金融政策が出来ることは限られている」「金融政策は補助的政策」という各国中銀総裁の以前からの共通発言は、真実を突いているのだ。
そういう意味で筆者は今回のECBの措置を、「危機拡大の芽を孕む金融政策」と呼びたい。最初に指摘したとおり。

2015年01月22日(木曜日)
(16:55)大勢の方から朝からメッセージを頂きました。ありがとうございます。
「ハチガケ論者」なので今52才です。ははは。加えて、「相応にしよう」「らしくしよう」なんて気はあまりないので、多分今年もかなり動き、考え、書き、そして喋るの....日々になると思います。うるさいことで申し訳ありません。が、よろしゅう。
それにしてもオバマ大統領の一般教書演説を改めて思い出して、「先進国はどこでも同じ問題に直面しているな」と思いました。それは「薄くなってきている中間層をどう蘇らすか」です。
「中間層」が必要なのは、経済的には「消費が6〜7割を占める先進国経済では、そこが薄くなると経済そのものがおかしくなる(成長力が落ちる)」からだし、政治的には中間層の喪失は政治の不安定化、振れの大きさに繋がるから」です。役割の問題以上に、「より多くの人が豊かな生活を送れた方が良い」に決まっている。
しかしグローバル化、技術革新の進展に対する適応力の差、教育格差などで、どの先進国でも今までの安定した成長を支えた中間層を「薄くするベクトル」を受けている。それに気づいた一部の政治家たちが、どの国でも焦っているのです。
やり方にはいろいろあって、それが議論の対象です。日本のように政府や経団連が旗を振って「賃金を上げよう」と言っている国は珍しいと思ったら、少なくともオバマ政権は最低賃金引き上げでなるべく中間層に入る、入るチャンスの入り口に立てる人の数を増やそうとしている。しかしアメリカ企業は「中間層の賃金を上げよう」などとは考えていない。
ディーセントな生活を出来ている人が多い国の方が、安定していることは間違いない。それが理想なのですが、それはほっておけばできる事ではない。ではどの程度....、どうやって....が問題です。ピケティの言うような「グローバル資本税」は可能性が薄い。世界は当面「方策探し」「実現の為の経路探し」を続けると言うことになりそう。
それにしても、オバマさんはふっきれちゃいましたね。「残りは2年もない。言いたいことを言って、出来ればいいし、出来なかったら議会のせいだ」と思っているように見える。立ち居振る舞いから。一般教書演説を終えて行ったところがカンザス州(共和党の牙城)で、来週の初めにはインドに行く。
インドのテレビを見ていたら、「世界でもっとも狙われる政治家二人が会談する」と。オバマ大統領とインドのモディ首相です。確かにアメリカの大統領も、インドの首相も凶弾に倒れた歴史を持つ。
インドでの警備体制は強烈そうです。沿道のビルを「みな消毒した」とインドのテレビは言っていた。その上にスナイパーを配備するのだそうです。怪しい奴がいたら撃つということでしょう。「消毒」って何を消毒するんですかね。英語では「sanitize」と言っていました。
うーん、それにしてもキューバに行きたくなってきた。多くの方がそう思っているのでしょうが。

2015年01月21日(水曜日)
(12:55)多分1時間以上は続いたオバマ大統領の一般教書演説を聴いていましたが、なかなか「強さ」を前面に出して演説はうまかったと思いました。登場した頃の勢いが戻ってきたような感じがした。「危機の影は去った」「ページをめくった」と。
しかし彼の後ろに座っていた二人、つまりバイデン副大統領とべーナー下院議長(共和党)の立ち上がる回数の歴然たる違い(ある程度当然だとしても)が、「中間選挙後のオバマを取り巻く環境」を象徴しているように思う。二回も「拒否権を使うぞ」と警告しながら、しかし最後は「よりよい政治を」と共和党に呼びかけねばならない現実。厳しい。
全体的なイメージを言うと、新味はなく、海外のことも言ってはいるが、ほぼ完全に内向きというイメージ。日本や欧州を導くアメリカは完全に陰を潜め、経済的には「海外と競争し、海外に勝つ」ことを鼓舞しているように見えた。
恐らく意識していたのは中国です。「china」が5回も出てくる。ウクライナなどで関係をこじらせているにもかかわらずロシアは2回。日本と欧州が各1回。あとはキューバ、アフガニスタンなどなど。
しかし抱える国内問題でも国際問題でも、肝心の解決策は提示していなかったように思う。だから演説を聴いていて、「もっと触ってしかるべき所に触ってくれよ」という印象が残った。それにしてもオバマ大統領が
Here’s another example. Today, we’re the only advanced country on Earth that doesn’t guarantee paid sick leave or paid maternity leave to our workers. Forty-three million workers have no paid sick leave. Forty-three million.と言ったときには、「そうなんだ」と思いました。一番頻繁に出てきたかなと私が思った単語は「Middle-class」かな。「Middle-class economics」とか。まだ意味不明ですが、共和党が言ってきた「トリクルダウン経済学」に対抗する意味合いがあったのだと思う。
その結論は、資産保有額で上位1%から税制上の抜け穴を封じる形でより多く税金を取って、それを「Middle-class」に振り向けるという政策。むろん富の移行だけではなく、教育を受ける権利、社会人教育の必要性、学生ローンの軽減化、教育レベルの引き上げなどなどいくつかの事も言っている。
何を言うか聞きたいと思っていた一つのことはファーガソンやニューヨークでの人種が絡んでいると思われる事件でしたが、地名は出たが今後何をするかに関しては、「司法制度の改革」を指摘しただけだったような。
「黒人である自分自身が大統領であること」に関して少し長く喋ったのが興味深かったが、最後は例の「保守もリベラルもない、白人も黒人もない.....」「だから合衆国だ」という論理で締めていた。
「2回も選挙に勝った」「もう選挙には出ない」とオバマ大統領。確かに。残りは2年のみ。しかし聞いていて、オバマにとっての危機の影は去ってはいないように思う。特に外交で。

2015年01月21日(水曜日)
(10:55)「うーん、クロスするのは再来年、つまり2017年かも知れないな」と思いました。日本から海外に行く人と、海外から日本に来る人の数のクロスです。
去年日本に来た海外の人の数は1341万人。対して、去年一年間で海外を訪れた日本人の数は1690万人。政府は「(来日客について)来年は1500万人が目標」と言っているので、例え日本人が去年と同じくらい対前年比で海外に行くのを減らしても(3%)、来年のクロスはない。
日本に来る外国人の数は予想以上に伸びる可能性があるのですが、それでも来年のクロスは無理でしょう。もっとも海外に行く日本人より、日本に来る外国人の方がお金を使うらしいので(特に中国の人。23万円とか。平均の15万を大きく上回る)、「15年に旅行収支は均衡」と見込む向きもある。
しかし、日本はまだまだ「観光大国」には遠い。定住人口(日本に定住)に対する外国人旅行客の比率はまだ11%(今朝の日経)。この11%という数字は、「主要先進国の四分の一」だそうだ。確かに。フランスなどは人口を超える観光客を集めてきた。その比率は韓国でも28%。日本はそれを大きく下回る。
日本には、陸続きで旅行に来る人が全くいないという制約がある。そう考えると、他の先進国のベース(定住人口の約半分の旅行客を集める)を日本が達成するのはなかなか難しいということはある。イギリスも今は鉄道などで大陸と繋がっている。しかし空の旅が安くなってもきているので、まだまだ日本に来る外国人観光客は今後も増えると言うことでしょう。2倍にも、3倍にも。
しかし、それは準備なしには無理です。当面は2020年のオリンピックということでしょうが、その先を見る必要もある。

2015年01月20日(火曜日)
(19:25)大阪を見て、大阪を食べて、そして一日を終わりました。ははは。

というのも、朝少し雨が降ったのです。その後晴れた上に、空気が綺麗だった。「どうせ天王寺に行くなら、まだ一回も昇ってないハルカスに」と。運転手さんに聞いたら、以前やっていた「事前予約」はなく、入場料で誰でも入れる、と。
行ったらすきずきでした。もう一巡したのでしょうか。それとも平日だったから。土日は今でも「要予約」らしいのですが、今日は直ぐチケット(ちょっと高くて1500円)を買えて、直ぐに上がれた。

58階が「天空庭園」と呼ばれているところで、「庭園」と呼ぶのはちょっと大げさですが、緑も植えてあって、レストランもある。大きな「アベのベア」(どちらから読んでも)が飾ってある。59階がやや狭い土産物店。実は58階に降りると地上300メートルの空気を吸える。

遠く京都タワーも見えると表示されているが、私には目視できなかった。しかし奈良の方向はよく見えたし、和歌山の方向は高いビルもなく、景色良く見えた。後の仕事(講演)の都合で駆け足だったので、もう一度ゆっくり見たい。
仕事後新大阪の駅に向かったのですが、小腹が空いたので、「そうだ、今日はヤマモトだ」と。エキナカに入っているのです。安定した美味しさを誇る。十三の店にも、梅田の店にも行ったことはあるが、最近はもっぱら新大阪のエキナカで。
焼きそばと豚玉を食べましたが、やはり美味しかった。番組終わりの半日の行動でしたが、あとで考えて、「ちょっと大阪を堪能したかな....」という感じ。

2015年01月20日(火曜日)
(11:25) 今朝の新聞記事ではやはり毎日新聞の総合面(2面)にある「憎悪生む偏見と貧困」が一番心に刺さります。フランスの連続テロのうちコーシャーのスーパーを襲ったクリバリ容疑者(32)が育ったパリ郊外の街のルポ。
サブタイトルが「郵便も来ない、就職先もない」ですが、街のおどろおどろしい様子が鮮明に描かれている。自分で見たわけではないので実体はいつか行ってみたいものですが(危険なんでしょうが)、冒頭の文章が「今すぐ出て行け」「これ以上ここにいると死んでもらう」ですから強烈です。
当たり前の話ですが、「偏見と貧困の街」に育ったからといって、テロを引き起こして5人も人を殺しても良いということには決してならない。それは当然です。しかしこの文章を読むと、フランスに憎悪が生まれる土壌があり、一部の若者が道を外す経路(例えば刑務所での邂逅とか)が出来ていることは分かる。
事件に関連して、これも今朝の朝日新聞にはオピニオン欄に「連続テロの底に」というタイトルの下にフランスの作家・哲学者ベルナールアンリ・レビさんと、同志社大学教授の内藤正典さんの意見が掲載されている。
見るところレビさんの意見は今のフランスの多数派の意見を代表しているように見える。「政教分離の下で、宗教を批判することは絶対の権利です」と述べ、『イスラム過激派は、民主主義に宣戦布告しました。それは受けるしかない。テロの源に出向いて、「イスラム国」なりアルカイダをたたくほかありません』と述べている。
「受けるしかない」とは覚悟を感じますが、ニジェールなどを含めて世界各地で彼が言うところの「絶対の権利」故に暴動が起きて死者が発生し、世界全体が緊張を強いられ、フランスの社会も民族対立感情が高まっていることも「受けなければならない」ことなのか。またはフランスは「受けてくれるのか」と思う。
レビ氏は『テロの源に出向いて、「イスラム国」なりアルカイダをたたくほかありません』と述べているが、フランスはアメリカでも成功しない過激派叩きをどこまで本当にやる気なのか。
私は、「表現の自由」は民主主義社会にあっては当然の権利だが、そこには他の人が信じるもの、その信じ方に関しては、それなりの尊敬、配慮があってしかるべきだと思うし、我々は通常はそうした気配りの中で生き、社会を構成している。「あえてそこはつつかない...」ということが一杯ある。
内藤さんも私と似た意見のようで、「預言者を嘲笑されることは、自分を否定されるように感じる。彼等がヘイトだと受け取っている以上、差別なんです」と言う。そうだと思う。
レビさんは、「表現の自由にはもちろん限度がある」として、「人種差別や殺人の呼びかけ、反ユダヤ、名誉を傷つける表現などは、フランスでも法律が禁じている」と述べている。内藤さの意見では「預言者の嘲笑は差別」ということですから、ここはもう真っ向から見方がぶつかっている。
多くのイスラム教徒はシャルリが描いてきた預言者への風刺画は、「イスラム教徒の名誉を傷つけている」と考えているが、そこはどうだろうか。世界の多くのイスラム教の指導者達も、テロを否定しながらも、「名誉を傷つける行為」だとシャルリを非難している。
となるとこれは文化の衝突です。文明以上の。だからレビさんも言う。「我々は長く恐ろしい試練のどば口にいる」と。少し安心できることに、「試練には冷静に立ち向かうべきだ。愛国的行動のワナにはまってはならない」とも説く。しかし欧州の政治勢力の中には、「冷静さ」とはかけ離れた行動を民衆に求めている勢力も多い。
私が気になるのは、レビさんの意見の中に、たまたま行数がなく書けなかったのかも知れないが、「憎悪生む偏見と貧困」をなくす必要性に触れた部分がなかったことと、フランスが「表現の自由」を言っている割には逆方向の意見には不寛容なダブルスタンダードが存在することだ。
「とば口」ですか。ということは、どのくらいのスピードで進展するかは分からないが、「長く恐ろしい試練のどば口」を入ったらもっと恐ろしい対立が待っている可能性が高い。身構えざるを得ない恐ろしいことだ。フランスは好きだけど、ちょっと「尊大さ」が気になるな......。

2015年01月19日(月曜日)
(21:25)やっぱり1300万人越えですか。11月までの数字を見ていると「月間100万人」を遙かに上回っていたので、「その程度かな」と思っていたら、今日の発表で明らかになった。
日本のどこに行って”実感”できることです。先日の札幌でも、「こんなところまで」と思った。特にドンキホーテの前は多かったな。同社は株式市場でも「インバウンド銘柄の代表選手」といった様相です。
この記事には読んでいくと面白い指摘がある。「訪日外国人の増加を追い風に、観光業がGDPに占める割合は自動車産業を上回る水準に高まっている。」と。
内訳は『 国・地域別では、韓国が約1割増の276万人、台湾は3割弱多い283万人。中国からは241万人が訪れ、13年からの伸び率は8割を超えた。円安の定着で訪日観光の割安感が強まっているほか、航空便の就航・増便やクルーズ船の寄港が増えたことが大きい。』ということらしいが、私はいろいろ課題が見えてきていると思う。今後さらに増えるとすると。
といった点だ。それにしても、彼等はよく使ってくれる。『日本に滞在している間に買い物や宿泊、食事などに使ったお金は計2兆300億円程度と13年から4割以上増えた。費目別では買い物代が7千億円以上と全体の35%程度を占め、宿泊費(約30%)や飲食費(約20%)が続いた。2兆円超の消費額を1人あたりの支出に換算すると、約15万1千円になる。』と。
訪日外国人一人約15万1千円の金使いですか。対して、中国本土からの人は一回当たり23万円を使うと言うが、それは実感でもある。一般的に「訪日外国人9人で、日本人一人の消費者の年間消費額に相当」と言われるが、中国人客は7人くらいで日本人一人分程度か。
南欧のように「観光しかない」では困る。しかし他の産業をしっかり持っていながら、「観光も凄い」国になるのは大歓迎だ。

2015年01月18日(日曜日)
(10:25)「あらら、君の生産性は上がったの?」と思わず自問してしまいました。
今月からこの週刊誌の短い書評のコーナーを毎月一回担当することになり、常にではないが、比較的いつも頭の中を本が走り回っているのですが、今朝はなんだか走っている時に文章が浮かんできて、それを忘れないために歩行しているときにメールを起こしてsiriで入力していたら、なんだかんだで字数(800字)になっていたのです。
むろんこれから糾合と剪定はしますが、分量や発想、それにポイントとしては朝の走行、歩行の中でほぼ完成した。だから自分に、「ひょっとして、これいいかも」と問うていたのです。いや、以前から「思いつき」の文章、考えなどはsiriを起こして自己メールしていましたが、文章が分量的に出来上がったことはなかった。
不思議ですが、私は走ったり歩いているときに思いつくのです。考えだったり、文章だったり。発想もそう。それをほっておくと忘れるのです。私が話した範囲では、そういう人は多いみたいです。
以前は浮かんだ発想をメモする専用マシンもあった。しかし今はsiriの能力は劇的に向上して、ほぼ正確に私の発声を文章にしてくれる。同音異義語を間違えるのはしょうがない。それはあとで「糾合・剪定」で直せば良いのです。
私の場合、音声入力した文章は比較的細切れで一回一回送ります。なぜなら長い文章を入力した後、それが何らかの形で失われたら嫌じゃないですか。それに後でそれを順番を変えたりして入れ替えを行うので、いくつかのメールで送っておいて、それをテキストエディターに乗せるときに考えながら落としていく方が効率的です。
まあこれも、普段ずっと考えていたから出来るわけで、すべての文章で可能かというとそうでもない。しかし全般に言えることは、迷った文章をまとめる力が出るのは走ったり歩いたりしているときのことが多い、ということです。不思議。

2015年01月16日(金曜日)
(11:25)おやおや、あっという間にスイス・フランとユーロがクロスしてしまいましたね。今見たらユーロ・円が135円12〜17銭、対してスイスフラン・円が135円94銭〜137円02銭。私がまだ今朝のスタンバイの前に見たらユーロが135円台、フランが133円台でしたから。ユーロ・フランは1ユーロ=0.9939〜44フラン
しかも重要なのは「相場全体が不安定」だということです。今もって。それは昨日の夕方にスイス国立銀行(SNB)が1ユーロ=1.2フランのフラン上限を廃止したときから始まっている。何せ2011年9月から始まった上限を撤廃したのだからインパクトは大きかった。
私がFM番組の前に世界の動きをチェックしたときに、ちょうど相場表が大混乱だった。何せスイス・円の相場(ビッド、オファー)が消えていた。かつその他の相場も激しく振動し、オファーとビッドが激しく乖離していた。
最初何が起きたのか分からなかったが、ニュースを見ると「スイスが上限撤廃」と。私が直ぐに思ったのは1992年秋に発生したポンド危機だ。イギリスの通貨であるポンドの為替レートが、イングランド中銀の防衛意思(明確に表明)にも関わらずジョージ・ソロス達投機家との戦いに敗れてリリースされた時だ。つまりその時はポンド防衛をやめた。その時のポンドの下落は激しかった。
今回はむろん、SNBが上限維持介入をやめたので、フランが急上昇(時に30%も)したという経緯で、当該通貨の反応としては真逆だ。しかしある意味、「中銀の敗北」という面は共通している。スイスの株価は10%ほど木曜日に下落。SNBとしては出来たら上限を維持したかったはずだ。
しかし通貨のある水準での維持にはコストがかかる。ユーロは南欧危機などいろいろあって、ずっとスイスフランには弱かった。上限を維持するためには介入が必要で、SNBとスイスには外貨準備としてのユーロがたまった。貯まりすぎたので、その割合を落とすために「金を買うか」に関して国民投票もしている。
そしてSNBが今後直面しるのはECBの国債を対象とした量的金融緩和。またまた巨額のユーロ介入を余儀なくされることは明確。ユーロ安になりますから。だから今のタイミングで「外さざるを得なかった」というのが当たっていると思う。SNBとしては「ドルが強い今がチャンス」と見たのだと思う。それは声明にも出ている。
しかし「上限撤廃」の影響をフルにSNBが予測できていたかどうかは不明だ。SNBは「誰にも相談していない」と言っている。そりゃそうだ。こんな措置が漏れたら、外国為替市場は事前に大混乱する。
今後はどうか。一つのポイントは私はドイツの株価だと思う。市場全体が混乱したのは確かだが、昨日は欧州の株が全般的に大きく上がって、ドイツのDAXなど久しく回復できなかった10000の大台を回復している。
(指数、終値、上げ幅、その%の順)つまり「欧州の株式市場はユーロ安・フラン高」を歓迎したと言うことだ。それは分かる。外国為替市場は動揺したが、例えば海外からドイツ企業に投資したいと思っている人は「ラッキー」と思ったと言うことだ。ユーロ安になっただろうし、EU経済にもプラスと読んだのだと思う。FTSE 100 6498.78 +110.32 1.73%
DAX 10032.61 +215.53 2.20%
CAC 40 4323.20 +99.96 2.37%
IBEX 35 9982.50 +136.50 1.39%
日本はむろんフランに連れ高となっている円相場の動きを嫌気して、株式相場は下げている。しかし今後「このままフランが上げ続けるのか」と問えば、恐らくそうはならないと思う。時計を含めてスイスの輸出産業には痛い。
その辺をどう読むかが今後を見る一つのポイントだと思う。いずれにせよ、最近の中銀は「世界経済のヒーロー」的扱いを受けているが、その実、今までの政策を変えるときには膨大なリスクを負う、ということが示された。それは日銀が抱える問題でもある。

2015年01月15日(木曜日)
(09:25) ははは、コツを掴みましたよ。危なそうな圧雪の上は実は歩いても案外滑らない。一番注意しなくてはいけないのは、一見「雪がない舗装道路」。その上に薄い氷が張っているケースが一番危ない.....と。
今朝二条の市場までホテルから歩いたのです。「滑るだろうな」と思って。実際に2回滑った。転びはしませんでしたが。その両方とも雪の上ではなく、舗装の上に見えたところ。その上に薄い氷が張っていた。

ジョギングする人がいる一方で、実は札幌の人はあまり歩かない印象。ホテルのロビーで「二条の市場まで歩けます」と聞いたら、「いや、歩けはしないでしょう....」と。でもそうかなと思って、ググったら「歩17分」と。歩けるでしょう、なんでもなく。で歩いた。
写真は今朝私が見つけた中で一番「これは凄い」という部類の札幌の道路です。黒光りしているのが凄いし、写真で見るより高低差があるのです。圧雪の上部と舗装道路の上下間隔が。
でも狸小路の中はすいすい歩けます。言って見れば大阪の天神橋筋商店街をちょっと品良くした感じのアーケード街です。「7」まであるのですが、「7」はちょっと天井が怪しい。
惜しまれて閉店した中川商店もあった。私が札幌に着いたその日が閉店した日でした。残念。行けなくて。

2015年01月15日(木曜日)
(06:25)ほんまによう動きますね。今見たら夕べはドル・円のドル安値・円高値は116円06銭ですか。でも今は117円の35銭前後。ドルの高値はと見ると117円91銭。

そのニューヨークの株式市場は186ドル59セントも下げていて、引値が17427ドル09セント。高値の1800ドルちょい超えから見ると、それほど大きく落ちている訳ではない。これは下がるときには下がっているが、上げるときには上げていて、差し引きすると下がってはいるが、パーセンテージにするとそれほど大きくはない、ということ。
今のマーケットは今後に対する身構えと、昨年までに上げてしまって足下が不安定になっていることの反映で、原油という産業基礎資材の価格不安定もあって「落ち着きどころが見つからない」という現状でしょう。身構えとは、ECBの緩和の先行き、ギリシャの総選挙、アメリカの利上げの時期などいろいろある。落ち着くにはちょっと時間がかかりそう。
札幌は今日までですが、大勢の新しい人に出会えたし、古くからの人にも会えて、よかった。冬の札幌も堪能しました。新しい方々とはこの会社の方々でしたが、このあまり円国的には知られていない会社が北から日本全国を目指して展開中な事を確認しました。
古い方はこの方ですが、北海道の魚を一緒にいただき、話に花が咲いて面白かった。わざわざ遠方からすみませんでした。でも思ったのは、札幌には新しい息吹が吹き込まれている、ということです。

私が昔から知っている札幌ではなくなってしまったことはあるのですが、それは日本のどこの都市も同じ事で、新しい産業が芽吹き、新しい人が増えて、面白い活動の形が出来るのなら興味深いことです。
一つ札幌が東京など一大消費地に進出する地方企業のパイロット地区になっているというのが面白かった。札幌や北海道は「結婚式が割り勘」など日本の他の地域にはない特徴を持つ。それは昔からの因習がない、人間関係が新しいなどの特徴が有るからですが、「そこでの成功は、東京など大都市での先行事例になる」とのことです。そこが面白かった。

2015年01月13日(火曜日)
(22:25)ははは、夜一緒に食事をしていた人が外を見ながら、「なんか暗いですね。札幌、こんなに暗かったでしたっけ?」と問わず語りに。中島公園近くのビルの11階で5人で食事をしていた時です。
私は大阪から札幌に午後に着いたばかりで「常日頃の札幌の夜の灯りの程度」は知らない。しかし私以外は全員北海道の方で、多くの方は今は札幌に住んでおられる。その方々が、異口同音に「暗い」と。
話題は北海道電力の値上げに発展した。見ても分かるが結構でかい。今年3月までは軽減措置があるが、その後は規制部門(低圧)で15.33%、自由化部門(高圧)で20.32%。
認可分がそれですから、もっと申請は大きかったのですが、それにしても支払う側からしたら「ちょっと仰天」の値上げではある。北海道に来て初めて知ったのですが、確かに消費者としてはたまらない幅の料金値上げ。だから北海道の各家庭で、「こまめに電気を消せ」と必死らしい。
その結果「札幌の夜が暗い」というのが一緒にいた4人の見立て。私は来たばかりで知りませんが、確かにそう言われれば、今日の夜景は記憶にある札幌の夜の明るさではないような。電力のような基礎的エネルギーが値上がりするのは、北海道には打撃でしょう。どうですかね、北海道に住んでおられる方々。
一方、私の印象です。それは「札幌は凸凹」というもの。歩行者として。だって本当に道が凸凹なんですから。ちゃんと雪かきが出来ている部分と、そうではなくいわゆる「圧雪状態の場所」とが市内の歩道を歩いていると交互に出てくる。だから凸凹です。
圧雪状態の場所は、雪かきが終わっている場所に比べて多分10センチほど高い。だって先日降ったどか雪がそのまま「圧雪されている」わけですから。例えばこうです。大きなビルの出入り口や駐車場の出入り口は除雪されている。しかしそこをちょっと外れると、誰も除雪していないためかただ雪が踏み固まっているだけ。つまり歩道全体がelevated されている。
危ないですよ。段差はかなり急で10センチほど。雪の急斜面があちこちにあるわけです。「東京を出るときから大阪を経由して短いブーツ(長靴)を履いてきて本当に良かった」と思う。それがなかったら、普通に東京・大阪で履いている革靴など一日でだめになりそう。
ホテルにチェックインしてその食事まで2時間半ほど札幌中心部を、「へえ、ここはこうなったんだ」とか歩き回りましたが、やっぱり街並みが東京や大阪とは違うから面白い。レストランは食材が違うし、デパートも置いてある衣類が防寒、防雪中心で。
木曜日の午前中までいます。調べたら2012年の2月に札幌は通過していました。旭川から新千歳にスーパーカムイで移動した時に。あの時見た岩見沢の雪は凄かったが、今もそうなのかな。今回は多分行けませんが。

2015年01月12日(月曜日)
(20:25)今見てちょっとビビったのですが、明日、明後日の朝の札幌の気温は−4度とか−5度とか。木曜日の朝は−6度。ありゃ。そりゃ寒い。
今は大阪にいますが、実は明日、明後日とこの寒さの中札幌に行くのです。仕事ですが、気温は分かっても天候(風)とか足場はちょっと今聞いている最中で不明。先日あったような猛吹雪ではなさそうだし、日中はプラス4度とか5度に上がりそうなので。ちょっとは安心ですが。
でも今日東京を出るときに、短めの長靴(ブーツ)で出てきました。あまり長靴らしく見えない靴で、場合によってはそれで札幌に行く予定。となると仕事の靴も必要かな ?ちょっと情報を集めて。
ははは、仕事もおもしろいものですが、その他にもいろいろ確認したいことがある。まだタクシーはあの寒空の中でドアを開けて客待ちをしているのか、とか。2年前に行ったら、旭川でもやっていましたからね。あれは協会で禁止すべきでは。
あと全般的な街の様子かな。80年代の初めから札幌に定期的に行っている身には、街の変化は顕著です。良い悪いは別にして。80年代後半は深夜2時になっても大勢の人が、若い女性を含めて歩いていましたから。
大きな変化は官官接待批判からですかね。街が変わってしまった。今は観光客が沢山来ているとして、それが街にどう影響しているのか。その辺を聞きたい。この2〜3年は北海道は札幌以外が多かった。西も東も。だから久しぶりの札幌です。

2015年01月11日(日曜日)
(23:25)日本時間の11時(パリ時間の午後3 時)を過ぎてもまだ行進は始まっていま せんが、それにしてもCNNを見ている と、凄い人出です。セキュリティを守るのは至難の業でしょう。何事もなく終 わって欲しいもので す。
出席者の顔ぶれを見ると、「Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas are due to attend, as are Ukrainian President Petro Poroshenko and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. In all, about 40 heads of state and government will participate in the event, including German Chancellor Angela Merkel and U.K. Prime Minister David Cameron」と多様です。ロシアのラブロフ外相が来るのは知りま せんでした。ここで報じられていない人も多いに違いない。
世界の都の一つと言えるパリでも、これだけの数の人が行進するのは稀でしょ う。欧米の新聞を読んでいたら「The throng is likely to mark one of the city’s biggest gatherings in decades, and French officials say they are adopting “exceptional” measures to manage the crowd and guarantee the security of foreign leaders. Large swaths of the city will be sealed off from traffic and subway lines will shut down」とある。
オランド大統領は、「Today, Paris is capital of the world,” President Hollande told members of his cabinet ahead of the march, according to a presidential adviser. “The whole country will stand up.」と。嬉しい形での「世界の首都」ではない。地下鉄も止めたと。
テレビを見ていると、オランド大統領など要人達が今バスから降りてきて、大 統領の右側にメルケルやレンツィ・イタリア首相、ポロシェンコなど。 左が キャメロン首相やネタニヤフ首相など。今25分遅れで行進が動き出しました。 止まったり、進んだり。
終わったばかりのいま世界はでもこの話題が最大のものでしたが、実は問
題は極めて複雑です。行進は短時間で終わるが、その後はまたフランス、欧州、
世界は複雑な 問題の一つ一つ直面することになる。

2015年01月11日(日曜日)
(17:25)まだちょっと遠いけど、しかし春は着実に接近中.....と今朝は思いました。

もうかなり大きくなっているでしょう。なんていう木かと気になったのです が、あまり一カ所にいると体が冷えるので、ちょっと写真をとってまた動 きま したが、「この膨らみはもうすぐだな」と思いました。
それにしても、今朝もそうだがこの週末は天気が良いので、寒いけど皇居周り はすごい人です。実にカラフル。そういえば、土曜日は少し長く「カラ スおじ さん」とお話をしました。ちょうど取り壊し中の物産の前にいらっした。
一緒にいたのは「ツン君」というらしい。オジさんの周りになん羽かカラスが 来て、他のカラスに餌をやっていると、「俺にも寄越せ」とツンツンと オジさ んの腰をつつくのだそうです。だから「ツン君」。
話していて面白かった。
などなど。オジさんはいつもはパレスの前にいることば多いのですが、最近は
物産の前が多い。「なぜですか」と聞いたら、なついていた「つがい」 が追わ
れて、他に移ったとか。その理由が面白い。「あまりに美味しいものをやった
ら、どうやら弱くなったりして、追われたらしい」と。はは は。

子供の頃「木の上の巣から落ちたカラス(確かカー子と名付けた)を育てたこ とがあった」と私の子供時代の話をしたら、「巣から落ちていたのです か。そ の時親が居なくて良かったですね」と。確かに。見られていたら、その後攻撃さ れていたと思う。とっても記憶力が良いの で。
カー子は結局、私のおばあちゃんに一番懐いたな。だって私や弟はおもしろ がってカー子が少し大きくなったら意地悪しましたから。カラスはちゃん と 「自分に一番優しい人」を見ていた。
結構皇居周りに発見のあった土日でした。ところで、今夜は午後7時からいま世界はです。連休中ですが、時間があったらご覧下さい。恐らくパリでの unity
rally の時間と重なります。中継がたっぷりあると思います。

2015年01月10日(土曜日)
(06:25)他のメディアの多くは「犯人(3人) は全員射殺され、事件は一応の解決」と 伝えていますが、CNNは「食料品店襲撃 の容疑者(射殺)の妻がまだ逃げている」と伝えている。事件はまだ続いてい る、ということで す。
フランスの警察、特殊部隊に射殺されたのはパリの風刺新聞社を襲ったクアシ 兄弟と、パリ南郊で8日に発生した女性警官殺害事件に関与したとして 公開手 配中だったアメディ・クリバリ容疑者(32)とみられるが、同事件では妻のア ヤ・ブメディン容疑者(26)も手配されており、彼女が逃げて いるというの がCNNの見立て。
CNNはさらにパリ近郊で起こった二つのテロ事件(新聞社襲撃とその後の立て こもり事件、それにコーシャー食料品店襲撃)は、「同じ ジハード・グループの犯行」と伝えている。これは「無関係のグループ が連動 して事件を起こした....」というよりは、フランス当局にとっては 「今後の捜査が進めやすくなる」という意味合いはある。
しかし今度の事件で亡くなった方々の数は、思い出すだけでも16人に及ぶ。 コーシャー(ユダヤ教の教えに基づく食品の数々)食料品店で、人質4 人の方 がなくなったと伝えられている。パリでは編集者や風刺画家など12人が死亡。
人種差別になるので人種や宗教を特定した人口調査をしていないので、実際に フランスにどのくらいのアラブ系の人々、それにイスラム教徒が住むか は実は 分からないらしい。しかし全人口(6000万ちょっと)の一割、つまり500万〜600 万というのが一般的な見方だ。
もちろんオランド大統領が「犯行を起こしたグループは、本来のイスラム教の 考え方をはき違えた連中だ。一般のイスラム教徒とは一緒には出来な い」と 言っているのは確かであるにしても、フランス社会、さらにはヨーロッパの国々 の社会に大きな緊張をもたらすと考えられる。そしてこの”緊 張”を利用するグ ループ必ず出てくる。
オランド大統領は事件後の短い声明の中で、「unty」と「solidarity」を強
調。それこそが「過激派に対する最大の武器になる」と。 その通りだと思う
が、問題は一杯残る。
など。一週間前までヨーロッパの土地(イタリア)に居た人間としては、ある
種の空気は感じていたので、欧州にとってとっても大きな問題だと思 う。

2015年01月09日(金曜日)
(12:25)今日のスタンバイを終わってTBSの玄関から出たら、いつもお世話になっている運転手さんが、 「伊藤さん、あれでしょ」と。
見ると、トヨタの水素自動車「MIRAI」が運搬車に乗せられて、TBS玄関前に横 付けになっている。私も「あ、MIRAIだ。(運転手さん に)そうですそうです」 と。TBSの前のサカスの広場はいろいろなアトラクションをやるが、恒常的にト ヨタ(多分スポンサーなんでしょう)の車が 展示されている。今はジーンズ車 など。
その濃紺(ブルーマイカ)のMIRAIは、次の展示の為にサカス広場に運び込ま
れたのだと思う。ナンバーがまだ付いていない状態で、運搬車から 降ろされる
模様。それをずっと見ていました。移動する時に全く音がしない。思ったよりも
大きい。
運転手さんに「そうです、そうです」と言ったのは、昨年末ですがスタンバイ の放送の中で森本さんが、「金曜日の伊藤さんはMIRAIを発注した と言っていま した」と言ってしまって、運転手さんがそれを聞いていたからです。その話を昨 年車の中でした。
出荷はまだ相当先なので接近したらと思っていて、このコーナーではこれまで 書かなかったのですが、去年の11月にMIRAIについて購入契約を 結び、手付金 も支払いました。多分「今年中には配車の予定」です。
水素ステーションがまだ多くないとか、安心して地方にはなかなか行けないと
かいろいろ考えました。しかしここに 掲載した『「MIRAI」の「未来」、
「日本」の「ミライ」』という文章での最後に書いた いろいろ調べて私が達した結論は「買い」だ。
「MIRAI」(ミライ)は 日本の未来の少なくとも一角は担う。よってそれに関与
する、消費者として参加するのは良い選択だと思 う。
という思いもあって。むろんお金がかかるので「一生懸命あちこちで原稿を書
き、財布をひっくり返して買います」ということになる。むろん手元に 届くの
はいつになるか分からないのです。だから「届いたらまた報告します」となる。

今はこうして展示用とか、補助金を出している官公庁用に出荷しているのだと
思う。だから、私のような一般消費者の手元に届くのはいつになるのか は不
明。早くて連休明けでしょう。お台場に行くと試乗車があって、それには乗れる
と知っています。ディーラーさんがそう言っていたの で。
しかし、配車されて初めて乗るというのがいい
んじゃないでしょうか。だからじっとまっているので す。ははは。

2015年01月08日(木曜日)
(22:25)確実に言えるのは、戦後という区切り
で見ると「今は前代未聞の時代」という ことでしょう。先進各国の10年債金
利の利回りを今見たら、以下の通り。
U.S. 10yr 1.996%
日本の0.3%割れはよく報じられていますが、ドイツの0.5%割れはちょっと驚
きです。しかし考えてみれば、昨日の発表でEUの昨年12月の 消費者物価上昇率
はマイナス0.2%だった。
German 10yr 0.493%
Italy 10yr 1.897%
Spain 10yr 1.705%
U.K. 10yr 1.634%
Japan 10yr 0.289 %
重要なのはこの数字が事前の市場予想である「マイナス0.1%」に輪をかけた ものであったということと、前月の「0.3%上昇」から見ると5ポ イントもの低 下になったこと。どの国でも、ただでさえのこの低インフレ環境下で、たった 一ヶ月の間にインフレ率が5ポイントも下がるのは、実に例 外的でしょう。
欧州のマイナスのインフレは2009年10月(マイナス0.1%)以来。原油安でエ ネルギー価格が大幅に下落したことが大きいが、見方によって は「欧州はもう デフレに突入した」とも言える。仮に「原油安」が欧州のインフレ率低下の要因 だとすると、日本も同じような状態になっている可能性 が高い。
今の債券相場の世界的な上昇(利回りの低下)は、「2%の物価上昇を目指 す」という世界の中央銀行のターゲット、その背後にある知恵が「一体ど うな のか」という根本的な疑問を投げかけているように思う。
なぜなら、今の世界的な、そして着実な利回り低下を見るならば、少なくとも 当面の間には「(2%の物価上昇の持続は)達成不可」に 思えるからだ。「不可」なことをターゲットにし た政策が許されるの か。
いずれにせよ、欧州や日本だけでなく世界的なディスインフレの時代というこ
とです。

2015年01月07日(水曜日)
(22:25)今日銀座三越の地下2階を歩いていた ら、写真のような「本日のみの販売」として「七草餅」 が売っていました。ナイスなアイデアだなと 思って一つ。「本日のみ」 なんて買って食べないと。
見た瞬間に「そうだ、今日だ」と思った。七草がゆを発想の原点としているの は明らか。本当は「かゆ」は朝なんですよね。ははは、朝から皇居一周 をした りしていたので、そんな時間はなかった。朝のニュースを見ていたらくどいほど やっていたのでしょうが、それも見なかっ た。
それにしても、2015年はマーケットは荒れているし、つい今しがたですが、パ
リでは二人組による銃乱射事件があって12人の方がなくなった と。詳細は不
明ですが、狙われたのは風刺画が売り物のフランスの週刊紙「シャルリー・エブ
ド」。「自動小銃を持った男らに襲撃された」とい う。
詳細は不明ですが、オランド大統領は「テロ」だと発言。二人の男は事件を起 こした後黒い車に乗って「逃走中」だと。ということはこの事件の続報 がある ということです。つい先日まで欧州にいた人間としては、いつも以上に緊張感の あるニュースです。
それはそうと、やっぱり10日も海外にいて日本の事をやっていないと、帰っ てきてこなさなくてはいけない事が結構ある。郵便物はたまっている し、各種 の届け出もある。帰国すると食べたいものも多い。ははは。
その中でちょっとカチンときたのは”配達”かな。暮れからいなかったので、そ れが郵便局に返されて、1月1日いっぱいとか、1月4日いっぱいで 「受け取 り」となっている。しかし取りに行ったのは6日。大阪から帰ってきてからで す。
当然ながら発送主に「送り返され」ている。送り主は銀行さんとか、その他公
的機関。年末年始は家に居ない人が多いと知っている筈なのに。発送時期を考
えて欲しいなと思いました。

2015年01月05日(月曜日)
(22:25)帰ってきて久しぶりにマーケットを覗いたら、やはり目立ったのは「ヨーロッパの苦境」ですね。
モスクワで一つ文章を書いたのですが、そこで改めて「(国民の多くが)クリスマスのプレゼントさえ抑制する」厳しさの中にあるイタリアに関しても書きました。リアルな現実だと思ったからですが、今日のマーケットを見る限りユーロ安、株安で一人イタリアのそれではなく、欧州全体の問題のように見える。
イタリア出身のドラギECB総裁は、そのヨーロッパの金融政策の舵取りをどう取るのか。それが当面のマーケットの不安材料です。飛行機の中で読んだ記事の中には、「たとえドラギが国債対象の大規模な量的金融緩和をしても、欧州経済は救われない」とあった。
私もその意見に賛成で、「しかしそれ以外に中銀としてやることはない」という選択肢の狭さの中にある。ドイツなどの反対をどう乗り切るのか。旅行中ずっと弱いユーロを目にしましたが、帰ってきてもそうでした。今は1ユーロが143円弱しか買えない。
むろん今のユーロ安は、過去一年日本に来た旅行者が目撃した円安ほどのスピードではない。しかし足早なことは確かで、特に対ドルでは1ユーロ=1.2ドルのレベル割りの中にある。
ヨーロッパと言えばギリシャが特に問題です。直近の独誌シュピーゲルは「ドイツはギリシャのユーロ離脱の覚悟は出来ている。影響も小さいからと判断しているから」との記事を掲載した。独政府は否定しているが、マーケットの受け止め方は「ありうる話」と見た。
ギリシャの総選挙は今月25日ですが、実際に急進左派連合が政権を取れば、ギリシャのユーロ離脱は現実化する可能性がある。その場合、ユーロはお荷物の一つであるギリシャの負荷がなくて強くなるのか、それとも「“ユーロという制度”の一角の崩壊」を嫌気して弱くなるのか。
今は後者のように見えるが、まだ即断は出来ない。まイタリアもそうですが、南欧は皆問題を抱えているんですよ。行くと楽しいですが。

2015年01月04日(日曜日)
(10:25)でも、今回の旅で一番「これがあって助かった」と思ったのは、やはり「グーグルマップ」かな。どこに行くにも複雑な道をしっかりとガイドしてくれる。加えてタクシーの運転手が正しい道を通っているのかも検証できる。
だってローマはまだしも、フィレンツェでもベネチアでも旧市街は本当に道が入り組んでいる。あれを「地図を頼りに歩く」というのは時間がかかりすぎる。無理ではないですし、街の楽しみ方としては「あり」なのには賛成です。
しかしやはり「時間」がある旅には、「どこどこまで歩いて何分、車(タクシー)で何分、電車で何分」というのが分かるのは非常に便利。しかも時間計測をまず間違わない。
海外の街は「なるべく歩く」主義の私は、おおよその所要時間を調べるときにはまずiPhoneに情報を入れて見るし、さらに「何時までにここに行きたい」と言うときにはて「現在地からの経路」と「所要時間」を表示させます。それでナビ開始させて行動を起こす。
また海外のタクシーは「回り道してんじゃないか」という心配もあるし、多少の回り道は地元還元で良いとして、「必要以上に時間がかかる」のは許せない。なので最近は、マップに目的地を入れておいて、それをタクシーの運転手に見せることにしている。
彼等もそれを歓迎する。やはりちょっと違う発音で地名を聞くと問題が起きることがあるし、乗ってくる人の現地把握の程度を知ることが出来る。むろん「smartphone-aided」ですが。お互いのレベルが知れて、逆に一種の連帯感が生まれる。
ナビ音声を出した状態でタクシーをスタートさせると、結構彼等も聞いていて、話題が出来る。面白いですよ。タクシーの運転手も、「まっとうな道を進もう」という気になるというものです。
海外で使っても、最近のグーグルマップは表示が日本語化されているし、日本語化されていない所でも、現地の綴りで目的地を入れればほぼ正確にその行く先を認識できる。ベネチアもフィレンツェも非常に狭い道が多いのですがほとんど迷うことなく動けました。
使い方も別に誰かに教わったわけではない。使っていれば分かる。それも便利です。

2015年01月04日(日曜日)
(09:25)イタリアはやっぱり「食の国」というのが一つの側面かな。日本にも最近進出してきているイータリーのプリミドの店に行ったら、それはそれは美味しいそうなものが一杯。直ぐに「美味しそうだ」と分かるのは、写真の魚もそうなのですが、輝いている。

ピラミデのイータリーは確か食材は3階建ての建物全体に入っていて、ほぼ全部見たし、イートインも試してみましたが、レベルは高かった。フィレンツェで美術館(確かウフィッツィ)のガイドをして下さった方が、「ここの人から食べることを取ったら、何も残らない」と。ははは。ちょっと酷くないかと思いましたが、現地で生活する人の意見は重い。

フィレンツェのガイドさんは、「最近はイタリア人はクリスマスのプレゼントもなかなかしなくなっている」と言っていました。私には確かめるすべがありませんが、そういう面もあるのかもしれない。しかし彼女は、「でも最後の意地で、食は別です」と。

だから朝から掃除は大変です。私が写真にとった掃除の人は、二人一組で遺跡の傾斜の激しいところを掃除していた。大変だな....とお思いました。観光地ローマを支えているのは、こういう人達です。
イタリア人と言えば「宵っ張り」のイメージですが、結構な数の人が早朝から働いている。ベネチアであの階段の多い道で荷物運びをする人はほんとうに大変そうだった。彼等の生活が陽の目を見ますように。

2015年01月02日(金曜日)
(08:25)フィレンツェは言って見れば「まいる街」です。「まいったまいった」の「まいる」です。
中心を流れるアルノ川の橋の上や周りから見た朝焼け、夕焼けの綺麗なこと。ぽっかりと浮かぶ薄い雲の塊が、繋がらずに時に丸く、小さく浮かび、それは朝日、夕陽に輝いてピンクやオレンジになる。

二番目は歴史でしょうか。覚えきれないほどの長い、そして彩られた歴史がある。そして建物。その多くは現存するか、または地下に眠る。今の大阪城の下に太閤の大阪城が眠るように、歴史は多く地下にある。

そして料理。なにせ「まいる」のは、たまたま元日の夜で「開いているところで」と入ったホテルの直ぐ向かいのレストランの「オリーブ油を使ったアンチョビ」と「トマトソースのスパゲッティ with ロブスター」の、それはそれは美味しかったこと。たまたま入ってレストラン、しかもトラットリアがそのレベルの高さですから。
宿泊したのはカッライア橋からの一方通行となるモロ通りを少し入った、部屋数10の小さなホテル。レストランはまさにそのホテルの入り口から道幅3メートルの反対側です。名前も知らずに「よさそう」だから入り(あとで名前が GARGANIと分かった)、そしてたまたま口に合いそうで頼んだ料理の中の二つがびっくりするほど、いや私にとって歴代一位(それぞれのジャンルで)くらいおいしかった。

歩くと世界的に名前のしれたブランド名も小さく見える。しかしここで主張が強いのは建物です。その建物にお店は間借りしている。日本は店があって、その建物があるように店名の主張が強い。そのコントラストが面白い。だからなかなか店を探せない。
美味しいものが多いのは、多分この街が「商売の街」だからでしょうね。それに豊かな大地。一生懸命働き、そしてその成果としての利益で、体に活力を与える。その循環があってこその美味しい料理です。日本で言えば昔の大阪。
常に”毒”と”糖尿病”と闘った権威と権限の街(日本で言えば江戸、京都などか)には、基本的には美味しい料理は発症しなかった。だって体を使いませんでしたから。世界を見ても美味しい料理の発祥は、かなりの部分が「商人街」です。
多分フィレンツェはそうだろう、と私は読んだ。あまり詳しくない歴史を見ても、この街にはメディチ家の発展がある。としたら、この家のお嬢様がフランス王の后になったときに料理人を連れて行ってフランス料理の基礎が作られたことを考え合わせると、「世界の一大料理群の発祥の地」ということになる。ナイスな、そして「まいる」街だ。

2015年01月01日(木曜日)
(08:25)今朝は二つの写真をフィレンツェからお送りします。皆さんには良い新年をお迎え下さい。