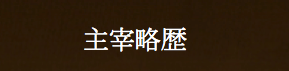川原郁雄
■昭和53年
早稲田大学建築学科卒。
■昭和55年
同大学院建築歴史専攻修士課程修了。
■昭和56年
株式会社乃村工藝社入社。
西武つかしん、つくば科学博政府出展歴史館、横浜市立人形
の家博物館、
日本経済新聞社主催ジャパンショップのテーマゾーン等、
商業/文化/マーケティングコミュニケーション施設の基本
構想に参画し、
主にコンセプトワークとデザイン戦略立案に携わる。
■昭和61年
株式会社スィーディーズ設立。
都市再開発や企業施設の構想、新型のマンションやホテルや
住空間関連商品のコンセプト開発などを手掛ける。
その後、新車コンセプト開発、新AV商品コンセプト開発、
電力会社や競馬組合、建設省道路局など広報戦略再編構想、
コンビニ企業の新業態開発、コンビニ型IT事業構想などに
参画する。
■2000年以降
IT業界専門誌出版社の新規情報事業構想、
知識創造の場と場のネットワークの観点から、事務機メー
カーの商品開発や事業開発や企業ヴィジョンづくりに従事。
音と映像とドキュメント、ハード/ソフトとコンテンツと
サービスを融合した異業種コラボレーションを、具体的な
アイデアをもとに様々な切り口から仕掛ける。
若い頃たくさん良い事を経験させて
くださった先達への義務、
当然担うべき課題
■2005年以降
1986年の独立前後にお世話になったある家電メーカーの
経営危機の深まりを予測、それを回避して起死回生を図る
外部協力者としての活動を、年数回の社内研修(1996年
から依頼されていた「コンセプト思考術」講座)の受講者
のアフターフォローを通じて行う。
研修は報酬を頂戴しての仕事だが、5年に及んだ起死回生
を図るブログを主要な手立てとする検討と提案という形の
日常的な応援は、あくまで若い頃お世話になった者として
の無報酬の勝手連的な活動だった。
そのような活動に専念して当たり前と思うほど、そのOB
の方々にはお世話になった。そして彼らが体現していた
創業精神を踏まえた思考や行動の素晴らしさを誰かが伝え
なければならなかった。
(浪花節、プロらしくないと笑う者や、仕事が欲しくて
やっているのではないかという勘ぐり、下請けのくせ
に生意気だという非難も多かったが、
人にどう見られるかなど私にはどうでもよかった。
ちなみに研修は私の本業ではなく、この会社の依頼と
そこの紹介に応えて自作カリキュラム1本するだけで、
売り上げに占める割合は1割程度だった。)
<モノ割り縦割りの事業部門分断経営>の事業部門それぞれ
がレッドオーシャン市場に没入して消耗戦で疲弊していき、
実権を握る採算部門が「選択と集中」の名のもとに不採算
部門を切り捨てていく、切り捨てられる方の主力たちも自
ら競合に身売りしていく、という予測がそのまま現実化。
アップル社や任天堂のような、
◯ハード〜システム
◯ソフト〜コンテンツ
◯オンウェブ・サービス〜異業種異業界ネットワーキング
を三位一体化する
<コト割り横ぐしの事業部門統合経営>の「選択と集中」と
対外的コラボレーションの事業展開を、具体的な叩き台ア
イデアを持って提唱し続ける。
社内有志たちの賛同を得て経営改革機運の盛り立てに協力
したが芳しい成果を見なかった。
現実の大きな壁の前に、私は余りに不徳にして非力だった。
当該メーカーは、2009年、公的支援を受けることを狙
いながら最終的な大リストラを断行。ところが予想以上に
基幹事業の新興市場向けOEM売り上げが伸びて、自立再生
を目指すことに。2010年初めの現在、一応経営破綻は
免れている。
しかし、これまでの経営経緯は、決して合理的なものでは
なく、部分最適ばかりを追求する派閥のポリティカルな争
いと妥協の産物だった。全体最適を期待する株主からみて
不条理とも言える経緯も含んでいる。
たとえば身売り同然に競合に評判商品の開発主力が移籍し
関連特許を売却したことなど。開発には巨額な投資が行わ
れ、有力特許の取得に貢献した主力たちには多額な報奨金
が支払われた。それに見合う売却価格だったのかどうか、
競合への主力移籍と特許売却という結論ありきの価格設定
だった。
事業撤退で、工場閉鎖による派遣社員の解雇という社会的
影響も与え、また創業精神を貫く創造的な正社員の多くが
希望退職という形で去らざるを得ない事態に追い込まれた。
たまたま不採算部門に配属された者、経営の失敗で不採算
に陥った部門で働いていた社員と派遣に割を喰わせるだけ
の事業部門分断経営。
それはいったい誰のための経営だったのか。
かかる一連の状況を外部ブレインとして目の当たりにした
主宰川原はタンジュンな原理原則に気づかされました。
それは、
「競争にしろ共生にしろ
その枠組みが開放系である集団や組織は、
自身の内的世界を外的世界に重ねてイメージするため、
対内的にも対外的にもオープンマインドで冒険的である。
しかし、閉鎖系である場合はすべてがその逆になる。」
ということです。
実際に四半世紀前、若造の主宰がお世話になった当時の
当該メーカーは、企業風土は冒険的であり人材体質はオー
プンマインドだった。
そして当時の基幹事業部門同士は、全体最適を図る企業
家精神をもって、具体的にハードとソフトとサービスを
連携させる<コト割り横ぐしの事業部門統合経営>を俊
敏に展開していた。
このメーカーのここ20年の変容は、まさに日本の企業
社会の縮図でした。
そこで、主宰川原はライフワークとして、
「日本型の集団独創」その2タイプ
<家康志向>
「集団を前提として固定しておいて、その集団が独創する」
知識創造体制
<信長志向>
「個々の独創を放任しておいてそれを適宜に集団に組織する」
知識創造体制
の内、
変革期に登場するパラダイム転換者とその周辺の暗黙知に
に留まっている<信長志向>の歴史的な研究*とその現代
的な促進ノウハウの明示知化に取り組み始めました。
(*<信長志向>は、織田信長だけでなく中世自社勢力
の聖や一向一揆、堺の国際商人、江戸の町人文化の
担い手、明治維新前夜の坂本龍馬の動き、戦後復興
期のホンダやソニーの創業や成長などにも現出。
一方、<家康志向>は、徳川幕府の体制として江戸
時代を通じて成熟し、精緻に明示知体系化されると
ともに日本人の特徴的な自然体の言動として血肉化。
安定的である良い面もあるが、限界的である悪い面
もあり、現代日本の膠着状況の多くはこの悪い面が
呪縛している。これを打破するのは、<信長志向>
しかないことは歴史が教えている。)
アメリカ由来のマネジメント論マーケティング論だけでは、
理屈は分かっていても理屈通りにはしない不合理や不条理
はけっして乗り超えていけない。
合理性の主張だけではまったくもって不十分であったこと、
私自身の非力として猛省します。
今後もこれまで同様、日本の企業社会の現実を直視して、
愚直に実践的な対策を追求するのは、若い頃たくさん良い
事を経験をさせてくださった先達への義務、当然担うべき
年輩者の課題と考える次第です。
 HOME
HOME