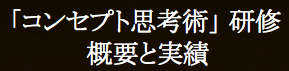2日コースの初日は、
午前中の講義で「コンセプト思考術」の骨子を解説します。
午後のグループ演習で、「思考フォーマット」を活用する基礎テクニックを会得してもらいます。
「コンセプト思考術」の骨子は、中学校の国文法程度の知識で理解ができるとてもタンジュンかつ明快な原理原則でしかありません。
要は、話し言葉は4つの概念要素から構成されていて、パラダイム=「考え方の基本的な枠組み」とはその4概念要素の組み立て方に他ならない。
「パラダイムの転換」とは、この組み立て方の転換であり、それに応じた4概念要素の内容の入れ替えなのです。
「コンセプト思考術」では、<送り手側のモノ提供の論理>と<受け手側のコト実現の論理>という二項対立の組み立て方を捉え、前者から後者へのパラダイム転換を主題とします。
それは、この転換を理解することで、マーケティング&マネジメントの基礎を、その根幹となる<商品〜商売(サービス)〜店舗(インターフェース)>の捉え方を通じて、その筋の専門用語を使わずに理解してしまえるからです。
(この点が、新入社員研修や、商店街組合のおじさんおばさんのワークショップに役立てられる理由です。
主宰に講師を依頼しなくても構いません。
是非、講師やインストラクターをするお立場の方には、本サイトの「*コンセプト思考術」を参照してお役立て戴ければと思います。
思考フォーマットは「演習成果」にあります。)
また、話し言葉の4概念要素の組み立てで物事を考えるのは、何もマーケティング&マネジメントなどの経済に限りません。行政サービスや政策といった政治から、日常の生活や仕事の仕方、人生の送り方まですべてにおいてです。
<人〜暮らし〜地域社会>の捉え方を、自分という人間を商品化する<送り手側のモノ提供の論理>ですることもできますし、自分という人間をいろいろな諸事情諸状況に遭遇しそれを受け入れ活かす者とする<受け手側のコト実現の論理>ですることもできます。そして誰もに明らかなように、どちらの捉え方をするかで真逆の価値観の人生、生活、社会を形成していく。
「コンセプト思考術」は、以上のような一見抽象的な内容を、4概念要素を組み立てる2つのピラミッド構造の概念関係図として、逃れようのない具体性において捉えます。
パラダイムというと一般的には文章なり話し言葉により散文的に表現されるために、概念要素の優先順位を恣意的に動かせば、人によっていかようにも都合の良い解釈ができます。
しかし「コンセプト思考術」の思考フォーマットはピラミッド構造の概念関係図であり、ある概念要素が土台になければ、中段に他の概念要素が乗ってこない、中段がなければ上段に残りの概念要素が乗ってこない、という明快さがあるのです。
また、主題とする「パラダイムの転換」は、4概念要素の組み立て方の逆転であって、それは極めて具体的に文脈の異なりを明快化するものであり、散文的な表現のように玉虫色の解釈を受け付けません。
以上のことは、初日午前中の講義を1時間受ければ明快に頭に入ります。
そして一度入った原理原則は、頭から抜けなくなるほどタンジュン明快で、誰もが腑に落ちる確かさがあります。
以下掲載する「演習成果」の、受講者グループによって記入された思考フォーマットを一つでもご覧になれば、その実際に具体的な感触を得ることができます。
ただし、原理原則を頭で理解することと、原理原則に従って出来上がった他者の成果を理解することは簡単ですが、実際にご自分がある課題について原理原則に照らしつつパラダイム転換発想をするのは、当初は想像したようには簡単に行きません。
それは、私たちには得意の思考パターンがあって、4概念要素のどれかを重視して起点としたりそこだけに思考をとどめたりしがちだからです。
4概念要素を過不足なく調和的に統合的に俯瞰しつつ全体最適の文脈づくりをする、そういう思考パターンをあまりしていないからです。
たとえば一般的に、
技術者であれば <モノの機能>
を重視し、
デザイナーであれば <モノの感覚> を重視し、
広告マンであれば <コトの感覚> を重視し、
人材育成者であれば <コトの意味> を重視する
という傾向があります。
それ自体は問題ではないのですが、重視が偏重であれば話は違います。
各職能の知識が孤立して連携する対話が困難になっていきます。
企業の知識経営としては、全体最適を組織として知識創造していくことが困難になっていく、ということに他なりません。
そしてこれは実際に、現代の企業社会において起こっていることなのです。
ちなみに<モノの機能>の概念要素は、数字と単位、型式、化学式などで表現される内容です。
経験からの判断として、組織や制度を機械論的に設定するシステムや、人間や人材を機械の部品のように交換可能な無個性なモノとしてとらえる管理や制御も<モノの機能>として捉えます。哲学的には「物化」ということです。
企業社会には、売り上りや資金繰りだけに専念し、創業理念も企業ヴィジョンもなく、ただこれを作ればいくら儲かるかばかりを捉え、部分的な採算性を競うばかりの経営者が多く見受けられます。このような経営者は<送り手側のモノ提供の論理>で<モノの機能>ばかりを偏重していることが多い。
顧客、生活者、社会そして社員ほかの就労者といった<受け手側のコト実現の論理>を軽視して、製品の高性能化と低価格化に専念するばかりで、実際に新製品販売の蓋を開けると売り上げ不振であったり、経営危機に陥っても内部を結束させられなかったり、社会的に支援の手を求めても応じてくれる協力者が少なかったりします。
(このような近視眼的な部分最適思考の経営者では、会社の将来が危ぶまれるという声を多く聞きます。
話し言葉の4概念要素の組み立てにより大局をタンジュン明快に捉え、戦略方針を他者に明快に説明できる「コンセプト思考術」は、経営者向
けのカリキュラムにも活かされます。)
主宰川原が企画開発のクライアントである自動車や家電のメーカーから依頼されて始めた
「コンセプト思考術」講座ですが、
事務機メーカーや鉄工メーカー、さらにはデザイン振興をする財団や自治体商工課からも
依頼されるようになり、
唯一の対応可能な講座ながら20年のロングランとなりました。
■「コンセプト思考術」講座
パイオニア・マーケティング・スクール年間研修
パイオニア・チャレンジ研修
パイオニア・階層別合同研修
パイオニア・マイクロ・テクノロジーズ
(1996~)
リコー営業マン実践マーケティング研究会
リコー中部営業マン年間研修
リコー中部SA年間研修
(2004~2008)
富士ゼロックス技術マネージャー研修
富士ゼロックス研究所研究者ワークショップ
(2001~2003)
クボタ幹部候補年間研修
(1999~2001)
仙台デザインマネジメントセミナー「戦略コンセプトづくりの方法」
(1996)
名古屋デザインマネジメントセミナー「戦略コンセプトづくりの方法」
(1995)
足利市COMPO`89ザ・デザインウィーク「いまデザインの時代-コンセプトデザインの提案」
(1989)
■マーケティング関連
パルコ・ディレクターズ・クラブ研究会「品種/業種/店種から品態/業態/店態への転換」
(1993)
西武百貨店新生活雑貨研究会セミナー「新生活雑貨の商品マーケティング&企画」
(1991)
■空間プラニング関連
JR東日本快適性研究会「戦略コンセプトワーク概論と列車における快適性について」
松下電器産業システムプラニングセンター研修会「ニュートラル空間ビジネスの基本戦略」
■地域活性化関連
長崎県異業種交流フォーラム・イン・佐世保「コンセプト時代のモノづくり」
(1992)
佐世保市商工会議所セミナー「まちづくりの中での商業コンセプト」
(1992)
熊本県デザインデー`91くまもと「地域の活性課とデザイン」
(1991)
大分県地域デザイン会議`91大分「デザインと90年代の地域企業」
(1991)
佐世保市デザインワークショップさせぼ「ハートフルマリンシティをめざして」パネラー
(1990)
■AVシステム関連
パイオニア/レーザーディスク高度利用セミナー「映像化店舗分科会」アドバイザー
(1988)
西武百貨店/衛星通信利用映像化店舗研究講座「映像化店舗とは何か-映像と人間心理」
(1987)
日本経済新聞社`87ジャパンショップ記念セミナー「AV機器による店舗活性化」
(1987)
日本経済新聞社/ビジネスビデオ・シンポジウム「広がる映像利用の現状」
(1987)
日本BGM協会定期大会・記念講演「コトづくりとしての店舗映像化」
(1986)
日本ビクター/第一回映像化店舗シンポジウム「ディスプレイから見たAVの位置づけ」
(1985)
2007年よりオフィスを東京代々木から伊豆高原に移転しました。
誠に勝手ながら一身上の都合により、上京と地方出張の頻度を制限しております。
但し、伊東市周辺のオフィスから通える会場での開催であれば随時対応可能です。
 HOME
HOME