|
|
国によって、地方によって、太陽光線の入射角が違う。そして、日本の左官たちのような、土へのこだわり。そんな吟味から生まれた「インディアートCERA」の人気が続いている。それは日本の壁の表情をつくる意匠塗料。
|

 |
|
|
 |
|
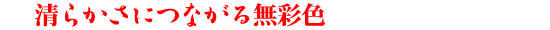 |
■色を忘れるひととき
日本の神社の質素さと清楚さは、ヨーロッパの宗教建築物と比較して、まさに異色です。
作家の曾野綾子さんは、神道の建築物や儀式が素朴である理由について、その著『近ごろ好きな言葉』(新潮社)のなかで「神道の儀式は人に見せるためのものではないから」「平野の宗教ではなく森の宗教だから」「他の宗教と徹底して争わなかったから」としておられます。しかし、実は、もう一つ理由をあげる人もあり、それは「神道が布教活動をしない宗教だから」ということでした。
余談になりますが、こんな話も思い出されます。かなり昔のこと、来日中のヨーロッパの富豪の子息が海の事故で亡くなりました。日本の関係者は白木の最上級の棺を用意して死者を納めました。ところが駆けつけた両親は「板きれを打ちつけただけの箱ではないか」と激怒したというのです。辛い話です。ともかくも、伊勢神宮にしても出雲大社にしても、日本の神社の建物は無色の感覚に近く、神に奉仕する人、神に祈りを捧げる人の服装も白と黒が基調。わずかに赤が混じるだけです。
「日本の美は抑制の美である」としたのは、元京都大学文学部教授、多田道太郎さんでした。(『日本人の美意識』筑摩書房)
|
 |
■時間と色の関係を想う
 伊勢神宮の始まりは『日本書紀』によると垂仁天皇26年の秋。いまの言い方をすれば紀元前29年のことになります。当然、その時代の社殿の建物は、掘建柱による素朴な造りでした。そのころの建築様式が長く継承されてきたものと思われます。
しかし、現在の日本には赤い神社もあります。豪華絢爛の日光東照宮は特別としても、宮島の厳島神社や京都の平安神宮、稲荷大社系の神社も丹塗りです。住吉造りや春日造りの神社も丹塗りですが、住吉の場合、時代が下がってから彩
色されたともいわれます。 お寺の場合も、現状は無彩色的であっても、もともとは赤いお寺だったという例が多いのです。仏教が日本に入ってきたのは6世紀から8世紀のころでした。仏教建築も同じころに入ってきたのでしょう。それまでの日本の建築物のような素朴なものではなく、大陸から入ってきた仏教建築は礎石の上に柱を建てる本格的なものでした。ごくしぜんな発想として、柱は赤く塗られたでしょう。そして、寺院はもちろん、神社でも、柱の赤い建築物が増えだしたのです。祈りと、悪霊ばらいと、防腐に力を貸してくれる赤い塗料。
一方、伊勢神宮の建物が現在のような構造に定式化したのは、7世紀末。しかし、中国文化に関心を示さなかった伊勢神宮の場合は、ひたすら無彩
色を通すことになり、江戸時代の桂離宮や現代の数寄屋建築などを生み出す原動力にもなったのです。 伊勢神宮の始まりは『日本書紀』によると垂仁天皇26年の秋。いまの言い方をすれば紀元前29年のことになります。当然、その時代の社殿の建物は、掘建柱による素朴な造りでした。そのころの建築様式が長く継承されてきたものと思われます。
しかし、現在の日本には赤い神社もあります。豪華絢爛の日光東照宮は特別としても、宮島の厳島神社や京都の平安神宮、稲荷大社系の神社も丹塗りです。住吉造りや春日造りの神社も丹塗りですが、住吉の場合、時代が下がってから彩
色されたともいわれます。 お寺の場合も、現状は無彩色的であっても、もともとは赤いお寺だったという例が多いのです。仏教が日本に入ってきたのは6世紀から8世紀のころでした。仏教建築も同じころに入ってきたのでしょう。それまでの日本の建築物のような素朴なものではなく、大陸から入ってきた仏教建築は礎石の上に柱を建てる本格的なものでした。ごくしぜんな発想として、柱は赤く塗られたでしょう。そして、寺院はもちろん、神社でも、柱の赤い建築物が増えだしたのです。祈りと、悪霊ばらいと、防腐に力を貸してくれる赤い塗料。
一方、伊勢神宮の建物が現在のような構造に定式化したのは、7世紀末。しかし、中国文化に関心を示さなかった伊勢神宮の場合は、ひたすら無彩
色を通すことになり、江戸時代の桂離宮や現代の数寄屋建築などを生み出す原動力にもなったのです。
|
 |
|
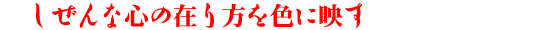 |
■霊を送る白装束の人々
 例えば京阪神といった範囲内でも、各地の風習の違いというのは意外に大きいと思うことがあります。それが、例えば関東と上越、関西と北陸といった距離になると、これはもう、ずいぶん違ったものもあるようです。
福井市や鯖江市からもそんなに遠くない福井県丹生郡あたりの葬式は、いまも明治時代そのままといってもよいような形式で、各地からの客人を驚かせます。新しい仏さまの息子たち、娘たちは、白装束になるのです。実際には、モーニングや略礼服、黒い着物など、都会の人と同じ黒い衣装の上に、簡易な白い衣装をつけます。昔は、もっと本格的な白装束だったのでしょうが。明治時代までは、こうした風習が全国で普通
だったといわれます。葬式に参加する女性が、いまの花嫁のような綿帽子をかぶったり、絹の薄い白布をかぶるなど。
近代化が進み、欧米の風習が怒濤のように入ってくると、黒の式服が正装として普及していきます。白から黒への劇的な転換です。喪服が黒くなったのは東京が最初で、次第に全国に広がっていきました。もともと黒は江戸の武士社会で重んじられた儀式の色でした。だからこそ、江戸に対するイナカは白や赤を用いたのだといわれます。
血の色であり、生命の色である赤。それはまた、太陽を、火を、思わせる色でした。そのため赤は、悪霊をはらう魔除けの色になったのです。神社の柱をはじめ、巫女さんのハカマ、飾り陣幕や縁起物、女性の腰巻…。みんな赤くなりました。 例えば京阪神といった範囲内でも、各地の風習の違いというのは意外に大きいと思うことがあります。それが、例えば関東と上越、関西と北陸といった距離になると、これはもう、ずいぶん違ったものもあるようです。
福井市や鯖江市からもそんなに遠くない福井県丹生郡あたりの葬式は、いまも明治時代そのままといってもよいような形式で、各地からの客人を驚かせます。新しい仏さまの息子たち、娘たちは、白装束になるのです。実際には、モーニングや略礼服、黒い着物など、都会の人と同じ黒い衣装の上に、簡易な白い衣装をつけます。昔は、もっと本格的な白装束だったのでしょうが。明治時代までは、こうした風習が全国で普通
だったといわれます。葬式に参加する女性が、いまの花嫁のような綿帽子をかぶったり、絹の薄い白布をかぶるなど。
近代化が進み、欧米の風習が怒濤のように入ってくると、黒の式服が正装として普及していきます。白から黒への劇的な転換です。喪服が黒くなったのは東京が最初で、次第に全国に広がっていきました。もともと黒は江戸の武士社会で重んじられた儀式の色でした。だからこそ、江戸に対するイナカは白や赤を用いたのだといわれます。
血の色であり、生命の色である赤。それはまた、太陽を、火を、思わせる色でした。そのため赤は、悪霊をはらう魔除けの色になったのです。神社の柱をはじめ、巫女さんのハカマ、飾り陣幕や縁起物、女性の腰巻…。みんな赤くなりました。
■四十八茶百鼠の美意識
 日本の色名は文字の植物園です。おそらく、他の国ではみられない日本の色名の特徴でしょう。
牡丹色、撫子色、桔梗色、菖蒲色、桜色、茶色、小豆色、茄子紺、勿忘草色、露草色、杏色、柳茶、草色…。染織家の志村ふくみさんは、さまざまな植物の、花の色、実の色、葉の色、幹の色、根の色で、布を染めてきました。そして、「ある時、私は、それらの植物から染まる色は、単なる色ではなく、色の背後にある植物の生命が色をとおして映し出されているのではないかと思うようになりました。それは、植物自身が身を以て語っているものでした。こちら側にそれを受けとめて生かす素地がなければ、色は命を失うのです」と書いています。(『一色一生』講談社)なんと厳しい色づくりの道ではありませんか。
もう1つ、日本の色名を見ていて思うのは、日本人の色に対する繊細な感覚でしょう。例えば、茶色の周辺に、葡萄茶、柿茶、樺茶、江戸茶、枯茶、丁子茶、鶯茶、媚茶、桑茶、納戸茶、御召茶と、無限の広がり。なにしろ「四十八茶百鼠」というのですから、ニュアンスというか、色の階調の違いは無限です。
微妙な美しさの違いを的確にとらえて楽しもうとする日本人の感覚は、まことに素晴らしいものといえるでしょう。 日本の色名は文字の植物園です。おそらく、他の国ではみられない日本の色名の特徴でしょう。
牡丹色、撫子色、桔梗色、菖蒲色、桜色、茶色、小豆色、茄子紺、勿忘草色、露草色、杏色、柳茶、草色…。染織家の志村ふくみさんは、さまざまな植物の、花の色、実の色、葉の色、幹の色、根の色で、布を染めてきました。そして、「ある時、私は、それらの植物から染まる色は、単なる色ではなく、色の背後にある植物の生命が色をとおして映し出されているのではないかと思うようになりました。それは、植物自身が身を以て語っているものでした。こちら側にそれを受けとめて生かす素地がなければ、色は命を失うのです」と書いています。(『一色一生』講談社)なんと厳しい色づくりの道ではありませんか。
もう1つ、日本の色名を見ていて思うのは、日本人の色に対する繊細な感覚でしょう。例えば、茶色の周辺に、葡萄茶、柿茶、樺茶、江戸茶、枯茶、丁子茶、鶯茶、媚茶、桑茶、納戸茶、御召茶と、無限の広がり。なにしろ「四十八茶百鼠」というのですから、ニュアンスというか、色の階調の違いは無限です。
微妙な美しさの違いを的確にとらえて楽しもうとする日本人の感覚は、まことに素晴らしいものといえるでしょう。
|
|
|
