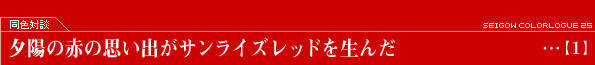|
|
 |

藤嶋輝義
(ふじしま・てるよし)
日本ペイント社長
石川県生まれ。
1963年、金沢大学理学部卒業後、日本ペイントに入社。以後、二輪やバスを含む自動車用塗料全般
の開発にたずさわり、数多くの優れた製品を生み出し、ついには“技術のエース”と呼ばれる。91年4月、自動車塗料部長に就任。その後、取締役研究開発本部長、自動車塗料事業本部長、取締役常務に就任し、98年には代表取締役専務となる。
2001年6月、技術が高く評価され、技術系出身では初めての代表取締役社長に就任。座右の銘は「原点回帰」。問題をあまり複雑に考えすぎず、迷ったり悩んだりしたときは原点に立ち返って解決の糸口を見つけるよう心がけている。現在、日本ペイントを「スペシャリティケミカルカンパニー」「エコカンパニー」としてグローバルな企業に成長させるべく、目標達成に向けて陣頭指揮を執る。趣味はゴルフ、囲碁、読書、野球観戦。
|
|
 |
 |
|
|
 |

松岡●出身は金沢ですよね。
藤嶋●はい。大学を卒業するまで、20年以上住んでいました。
松岡●金沢は私も大好きなまちです。自然が美しくて、とても色彩
豊かなところではありませんか。
藤嶋●そうですね。有名な観光地である兼六園などは、四季折々の花や緑が本当に綺麗です。
松岡●そんな情緒あふれるまちに長く身をおいたことで、ご自身の考え方や感覚のなかで何か影響を受けられたことはありますか。
藤嶋●あまり意識したことはないのですが、おそらくさまざまな部分で活かされているでしょうね。決して楽しいことばかりではなかったはずですが、ふり返ってみますと、良さだけが印象に残っているという感じです。
松岡●「ふるさとは遠きにありて思うもの」と言った室生犀星も金沢の人ですが、その心境でしょうね。金沢時代では、色にまつわる思い出とか、印象に残った風景とかはありましたか。
藤嶋●私は田舎の農家で育ちましたので、色といいますと、やはり自然の色がいちばん印象に残っています。
松岡●たとえば、どんな色ですか。
藤嶋●学校から帰ってきて、毎日のように親に畑に行かされるわけです。
松岡●仕事の手伝いに。
藤嶋●そうそう。乳牛の世話とかで、夕暮れどきは、だいたい外に出ていました。冬場は雪が降りますから、作業は本当に辛かった。そんななか、夕暮れどきにふと空を見上げると、なんともいえない鮮やかな夕焼けが目のまえに広がっているのです。赤というのかオレンジというのか、とにかく鮮烈な色で。
松岡●夕焼けの太陽の赤さって、表現しがたい美しさがありますよね。
藤嶋●それと、もう1つは雪の白。積もった雪を掘り起こしたときに葵の葉っぱが顔を出すのですが、そのツヤツヤした緑色と雪のキラキラした白のコントラストが、なんともいえず美しかった。ですから、太陽の赤と雪の白は、少年時代の苦しい生活の中で強烈な印象として残っている色です。
松岡●青年時代は、どうでしたか。
藤嶋●うーん、そうだなぁ(笑)。苦しい思い出が少なかったのか、あまり色の印象がないんですよ(笑)。
松岡●色に無関心?(笑)。では、そもそもどうして日本ペイントに入社されたのですか(笑)。
藤嶋●この会社に入ったら化学ができると思ったからです。大学で学んだ知識を活かし、さらに化学の分野を突き詰められるんじゃないかと。
松岡●なるほど。望みは叶えられましたか。
藤嶋●そうですね。ただ、実験器具に関しては少々驚かされました。大学では、ちゃんとしたガラスの容器で実験を行っていたのに、会社ではブリキ缶
とかを平気で使っている。その落差に、なんだこれはと思いましたよ(笑)。
松岡●それはすごい(笑)。会社に入ってからつねにペイントの研究開発に従事してきたわけですよね。そんな経験のなかで、この色はうまくいったというか、好きになったというのは、どんな色ですか。
|

|
藤嶋●あるメーカーの自動車用に赤い塗料を開発したことがあり、手前味噌になりますが、このときの赤は本当に満足のいくものでした。その後も自動車向けの塗料を数え切れないくらいに生み出してきたのですが、いまだに、その赤を超えるものはできていません。
松岡●なんていう名前の赤ですか。
藤嶋●「サンライズレッド」です。
松岡●ははぁ、思い出の太陽の赤。色の名前も技術者が考えるのですか。
藤嶋●当時は技術者が何もかもやっていましたよ。
松岡●色のネーミングも大変でしょう。
藤嶋●車種が増えてくると、普通に色名だけを使っていては間に合わなくなってきます(笑)。苦しまぎれに、星座の名やギリシャ神話などからイメージに近いことばを探し出すこともありましたよ。「マースレッド」とか「マーキュリーブルー」とかね。
松岡●なかにはピタッとハマる色名ができることもあるんでしょう。
藤嶋●そうですね。色のネーミングをたくさん考えなければならないということは、それだけ色の種類が多様化してきているということの証明ともいえますね。
|

|
|
|