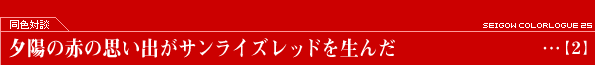|
|
 |

松岡正剛
(まつおか・せいごう)
京都生まれ。編集工学研究所所長・帝塚山学院大学教授。1977年、オブジェマガジン『遊』を創刊、斬新な編集とビジュアル感覚で、アート・思想・メディアに大きな影響を与える。その後、独自の世界観にひそむ方法を「編集工学」として確立、87年編集工学研究所を設立、現在にいたる。以降、美術全集からテレビ番組まで、祭から国際会議まで、展覧会からテーマパークまで、企業戦略から地域政策まで、数々の編集企画やプロジェクト、システム開発にかかわる。おもな著書は、『ルナティックス』(作品社)、『フラジャイル』(筑摩書房)、『知の編集工学』(朝日新聞社)、『色っぽい人々』(淡交社)、『知の編集術』(講談社現代新書)、『日本流』(朝日新聞社)、『日本数寄』(春秋社)ほか多数。現在、インターネット上に壮大な図書街を出現させるプロジェクトISISを推進中。また99年より、編集工学研究所ホームページで「千夜千冊」を毎日連載中。
|
|
 |
 |
|
|

松岡●色の世界というのは非常に幅の広いものですよね。例えば、各民族はそれぞれが独自の色を持っていますし、動植物の世界を見渡してみても、あらゆる色が存在する。結局、人間というのは何らかの色を通
して世界を見ているのだろうと思うのですが。
藤嶋●たしかに、ひとが好む色とか差別化ができる色とかは、塗料をつくるうえで常に私どもの念頭にありました。
松岡●塗料というのは、そもそもいつごろからあったのでしょうか。
藤嶋●塗料の起源をどのあたりに定めるのかは非常に難しいところなのですが、何らかの素材を用いて色を塗るという行為は古代から生活の場にありました。
松岡●日本の場合だと、古くから漆塗りがありますよね。
藤嶋●そうですね。明治の初めごろまで、塗料といえば漆を使うことがほとんどでした。そんななか、洋式の塗料が製造され始めたのは、明治14年に日本ペイントの前身の光明社が設立されてからです。
松岡●つまり、その年こそが、産業として近代塗料が現れた瞬間だったと。
藤嶋●そう。鉄製品に塗るさび止め塗料も創業当初から取り扱っておりました。最初、塗料は「保護と識別
」を目的につくられていたのです。カラフルなペンキがつくられて生活用品に彩
りを与えるようになったのは、昭和になってからです。
松岡●ペンキで思い出したのですが、私は高校生のときに京都から横浜へ引っ越しまして、家族と一緒にロシア人が家主だった洋館で生活することになりました。それで、業者に建物の塗り替えをやってもらったのです。
藤嶋●それはペンキで?
松岡●ペンキです。それで、塗り替えが終わった家を見て、びっくりしました。柱とか壁が真っ白に生まれ変わっている(笑)。自然な木の色合いを大事にする京都では、そんなこと考えられなかった。
藤嶋●ご両親も驚かれたでしょう。
松岡●もう、母親なんかショックで怒っていましたよ。「こんなんアカン!」って。ところが、しばらく住んでみると、家族全員が「案外、ペンキの色もええもんやね」と言うようになった(笑)。あのとき、ペンキというものの力を初めて認識しました。
藤嶋●ペンキのよさというのは、誰にでも塗れて、モノを自分の好きな色に変えられるところです。実際、家庭用の塗料としてペンキが売り出されたときは、「誰にでも塗れます」というのが謳い文句でしたから。
松岡●さきほど、塗料が持つ役割について「識別
」という言葉をお使いになりましたが、いま日本では、色をサインカラーとして用いる傾向が強くなってきていますよね。「あの人のカラーは」とか「あの会社のカラーは」だとか。
|

|
藤嶋●だんだん、色の持つ意味が心理的な作用に変わってきたのでしょう。
松岡●アイデンティティーが色で表されることが多くなった。
藤嶋●例えば、絵具の使い方ひとつとっても、使う人のセンスや考え方で、まったく違った色が出ます。
松岡●アイデンティカル・エクスプレッションですね。
藤嶋●私どもは、完成した色を商品として提供しておりますが、「自分で色を塗る」という行為そのものは、文字どおり十人十色です。
松岡●たしかに、絵具というのは、使う人がその色を出したわけじゃない。いくつかの絵具を組み合わせて、別
の自分の世界を見せる。だから、色そのものを表現しているのではなくて、絵具ではない別
の心境をイメージしている。
藤嶋●そういう意味では、商品としての塗料は、色自体が表現といえます。
松岡●要するに、ペイントというのはアイデンティカル・エクスプレッションで、絵具はアイデンティカルじゃないのでしょうね。
藤嶋●すでに決められた色といえば、最初にお話したクルマもそうですよね。クルマには、すでに完成品として何種類かの色が塗装されていて、買う人は、そのなかから好きなカラーのものを選ぶ。
|

|
松岡●以前、私はトヨタの車体デザインの企画に関わったことがあるのですが、クルマの場合、色を決めるのは最後なんです。
藤嶋●まずボディーを完成させて、それから車体の色のバリエーションを考えるということですか。
松岡●そのとおりです。結局、半分はデザイナーたちが色の種類を決めるのですが、残りの半分はお客さんが選択する余地として残したいと。半々にすることを前提として、最初のモデルカラーをどう選ぶのか、その選択が難しいらしい。
藤嶋●何系の色にするかで、あとあとのバリエーションも変わってきますものね。
松岡●何色でも出そうと思えば出せますが、全部やっちゃうと、お客さんがついてこない。ある程度やっておいて、「もう少し濃いグレーのものはないかな」と言わせるところが大事なんです。
藤嶋●なかなか興味深い話ですね。そういえば、海外に行ったときに現地で見かけるクルマも、日本のとはまた違った感じで面
白いですよね。車体の形状と色の組み合わせが同一でも、気候、環境で、ガラリと印象が変わりますから。ただ、さまざまな色のバリエーションがあるなかにも、全体的には何か共通
したものがあるような気もします。
松岡●衣服なんかでもそう。どんな民族でも、各個人は独自の色を持っています。ところが、あるところからは共通
のものになっていく。それをカジュアルカラーというのかどうかは別として。われわれが使う言葉で表現すれば、コモンランゲージ(共通
言語)になっています。
藤嶋●具体的には、どういうことですか。
松岡●またクルマの話に戻りますが、クルマの色こそ、まさにコモンランゲージそのものです。フォードが初めてクルマを大量
生産したとき、ボディの色は黒にした。
藤嶋●大昔のクルマって、ほとんどが黒でしたもんね。
松岡●つまり、電話機や万年筆が黒からスタートしたことも含めて、黒という色が20世紀初頭のメインカラーだったのです。で、そのあとに飛行機が誕生しますが、機体は黒ではなく白に塗られた。その白が、のちにクルマの色に転化しました。だから、民族の色というよりも産業の色が変化し、その時代を象徴する色が誕生してきたわけです。
藤嶋●色文化の時代性は商品の色から、ということですね。
|

|
|
|