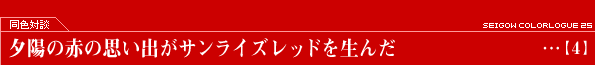| |
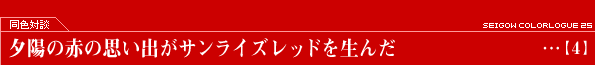 |
|
|
|
|

松岡●環境問題といえば産業廃棄物が頭に浮かびますよね。色の付いたものというのは、産業廃棄物になったとき、焼却の面
で問題を抱えているのでしょうが、それをいま、技術改良されてきているわけですか。
藤嶋●そうですね。私どもの場合でいえば、化学物質の総合安全管理ということで、さまざまなリスクの低減をめざしています。
松岡●環境と技術の関係を考えるとき、いつも思うことがあります。事実として、人間は環境を変えてきたわけですよね。そんななかで、何が自然の原型で、どこまでが人が阻害した部分かという、そこの線引きが難しいのじゃないかと。
藤嶋●技術によって自然や人間が救われている部分もたくさんありますしね。近年、電波障害や電磁波障害が問題となっていますが、それを防ぐためのシールド材やコーティング材もたくさんつくられるようになりました。
松岡●塗料でいえば、やはり深刻な問題となっているシックハウス症候群の予防として、有害物質がほとんど含まれないものも考案されていますよね。だから、技術というものが全部、自然や環境にとって悪いものだとは思わないんですよ。もっと技術が進んで、環境に対応した素晴らしいモノが出てくる可能性だって大いにあるはずですから。
藤嶋●まさしくおっしゃるとおりです。私どもでは、創業以来、一貫して「事業を通
じて社会に貢献する」という企業理念を掲げてまいりました。塗膜によって資源を保護し、塗料によって景観を高めるというスタンスは今後も変わりません。
松岡●本当は、木だって緑だって、少なからずバイオテクノロジーの恩恵を受けてきたんです。もともと自然には技術が半分入っているといってもいいんじゃないでしょうか。それに対して、さらに技術が何を加えるのかというのは、相互作用だと思います。だから、そのあたりがもう少し理解されるようになれば、自然が絶対的なもので人工物は駄
目だというインジケーターも、ある程度は変化していくんじゃないでしょうか。
藤嶋●自然と技術の相互作用がうまく働くことが、最も望ましいといえますね。そんな理想的な状況に近づくためには、やはりペイントの根幹を成す基礎化学の研究を続けなければなりません。
松岡●塗料業界における基礎化学というのは、簡単にいえば、どういうものなんですか。
藤嶋●これは、たいへん学際的なジャンルです。さまざまな物質の反応や性質を研究して、構成原子や分子の構造を調べ、新たな物質を合成しようとする学問です。
松岡●膨大な数の物質を合成し、解析することが基本になるわけですね。
藤嶋●塗料の材料的にいえば、高分子化学やレオロジーの研究が、より重要になってくる。
松岡●レオロジーというと、物質の流動とか変形を取り扱う学問ですね。
藤嶋●そうです。塗料と流体力学は切っても切れない関係にあります。
松岡●流体系は本当に面白いですよね。そうするとペイントは界面
化学になるわけですか? |

|
藤嶋●ペイントの場合、技術者が経験やカンに頼る部分が少なくなかった。が、やはり界面
化学の知識は非常に重要になっています。
松岡●やはりそうですか。相転移というか、ある物質が臨界値や一定の飽和に達したとき、別
のものに出会うというところが、化学で最高に興奮する瞬間ですよね。まさに、それこそが界面
性の面白さでしょ。
藤嶋●塗料は界面化学やコロイドの応用技術によって進化してきましたが、レオロジーも含めて、基礎化学の世界は本当に奥が深い。
松岡●私は昔から寺田寅彦が好きだったのですが、ある時期、彼は「割れ目の科学」とか「崩壊の科学」という研究をしていました。物理科学において、モノが割れたり、ヒビが入ったりする現象は、いったい何なのかということを解明する研究です。こうした研究というのは、やはりペイントでも行われてきたのですか。
藤嶋●いかに塗膜を美しく保つかという研究は、つねに行われてきました。輝きのある光沢を維持するために、ツヤが無くなる原因やペイントが剥離する要因を探ったりね。
松岡●変化のプロセスを追うことで、塗膜の劣化を防ぐ対策を考えるわけですね。
藤嶋●そうです。色を出すときに、同時に欠点を消す効果
を出すことが重要です。こうした研究もまた、広い意味でのレオロジーといえるでしょう。
松岡●そもそも色に光沢が付き始めたのは、いつごろのことなのですか。
藤嶋●最も光沢が必要なのはクルマなんです。むしろ、建築関係はツヤ消しです。あまり住空間に光沢があり過ぎると、なんか居心地が悪いでしょう。
松岡●落ち着かない。
藤嶋●クルマは光沢が非常に重要ですから、そういう意味では、やはり昭和30年代後半から光沢を出す塗料が出始めました。
松岡●いままでおっしゃった技術に加えて、何が必要となってくるのですか。
藤嶋●ツヤが出やすいように原料の配合を変えることが基本としてあります。高分子の樹脂というのは本来ツヤがあるのですが、顔料が入るとツヤが出にくくなる。そのあたりのバランスを変えてツヤの具合を調整するのです。
松岡●塗膜の表面の、さらに奥の層には光沢は無いのですか。
藤嶋●無いです。表層で初めてツヤが求められるのです。で、最終的に最上層にクリアコートすればパーフェクトになります。つまり、素材の配合プラス塗装技術で、ベストな光沢を出すというわけです。
松岡●なるほど。クルマの光沢っていうのは、今後も無くなりそうにないですね。
藤嶋●クルマの買い替えで最も多い理由は、車体がみすぼらしくなったから、というものらしい。ボディに傷が付いて色が剥げると、愛着も無くなってくるのでしょうね。
|

|
|
|
|
|
|